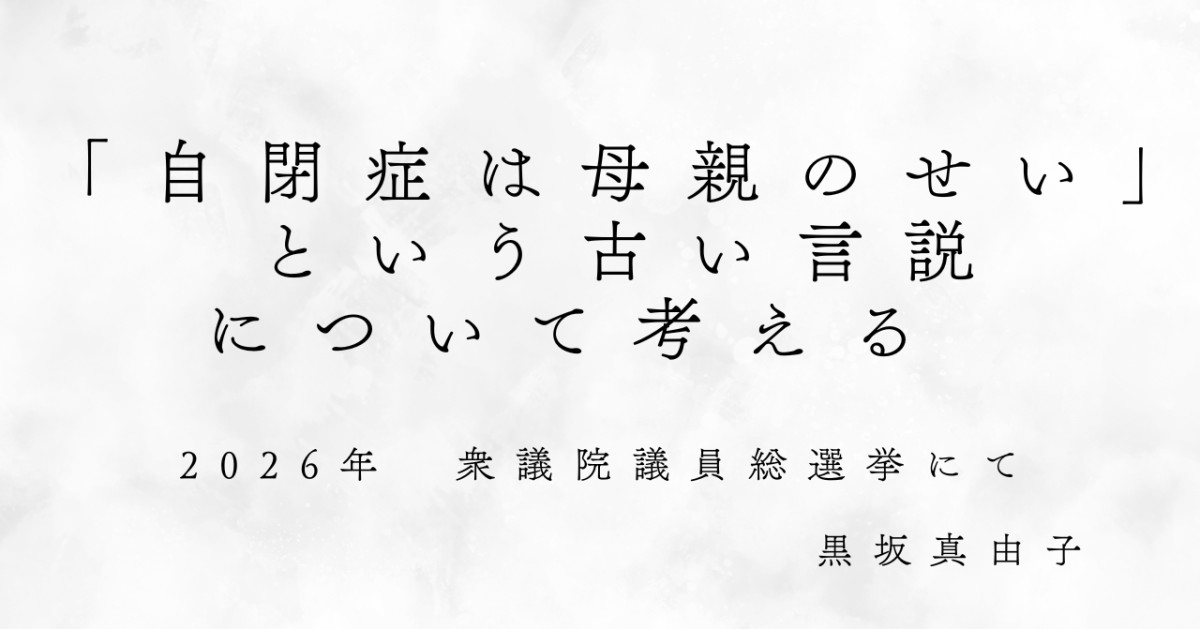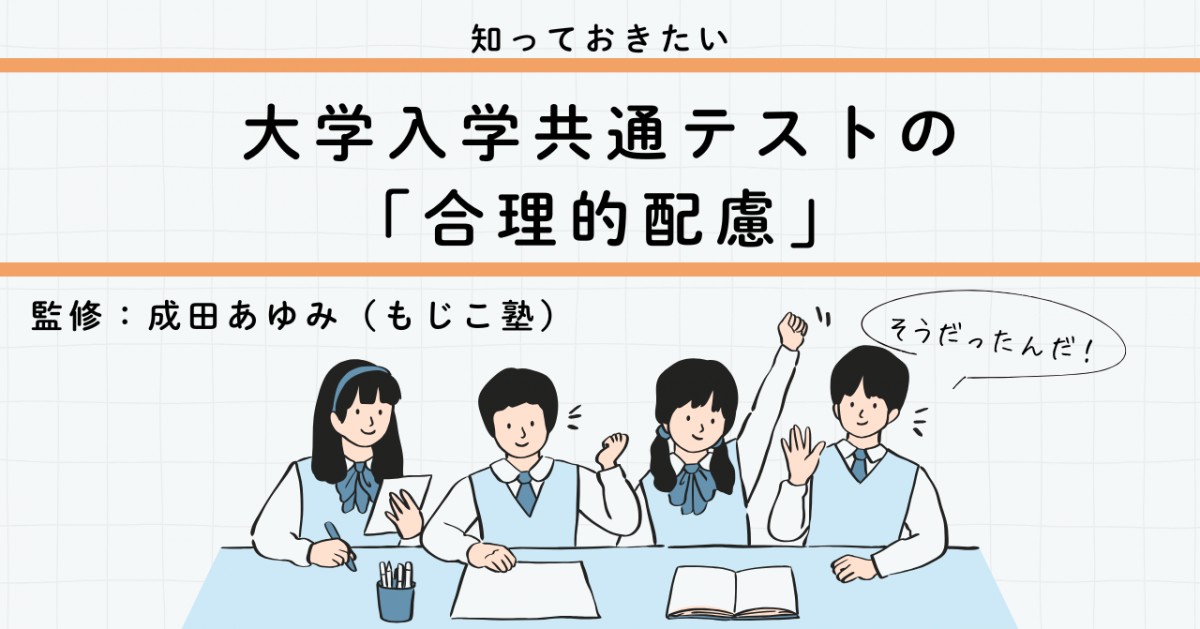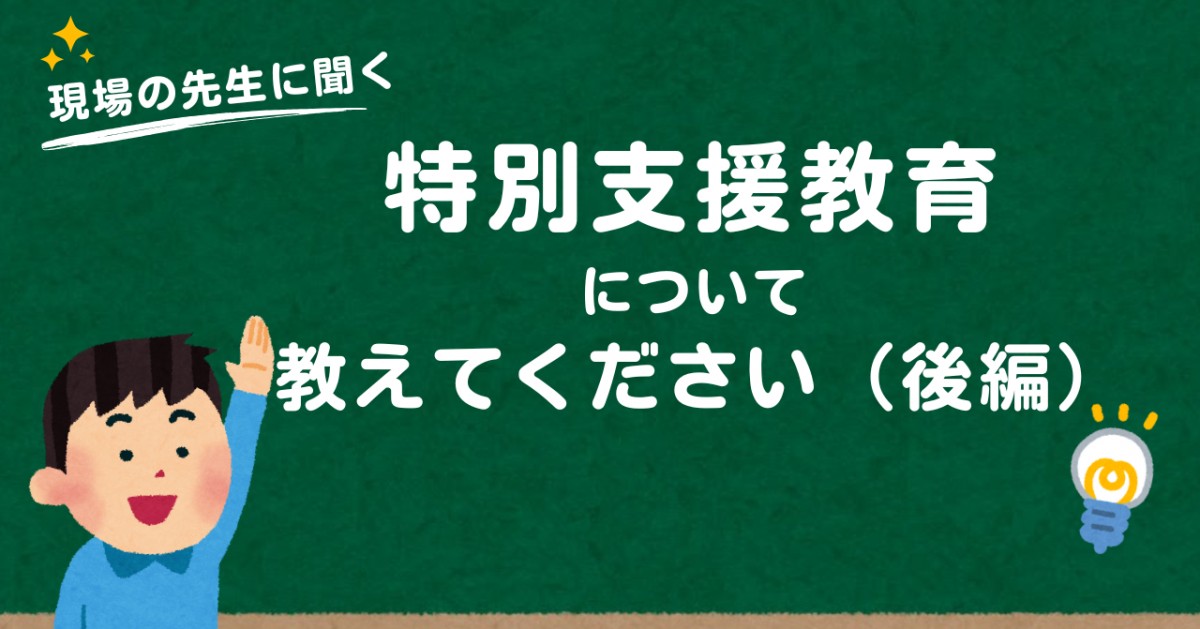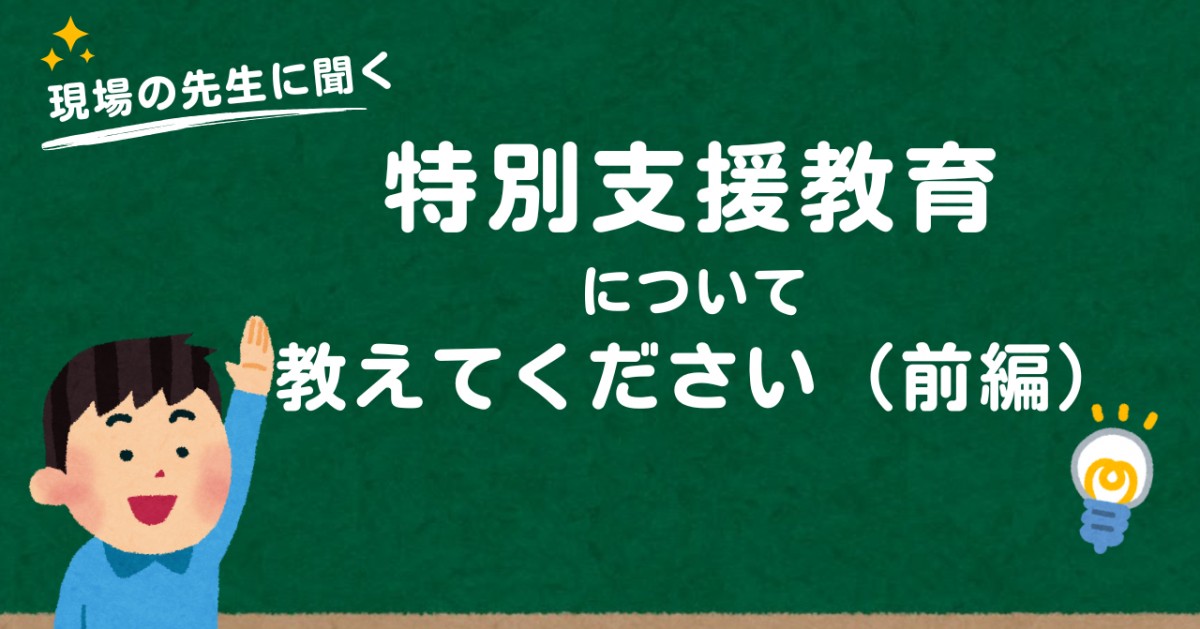合理的配慮受験への歩み 北海道道立高校を目指して
北海道で初の合理的配慮受験に向けた取り組みを行った「十勝読み書き友の会」代表の大久保育美さん。その道のりは、平坦ではありませんでした。高校受験へ向けて、どのように学校や教育委員会と話し合いをしてきたのか、大久保さんに詳しくお聞きしました。
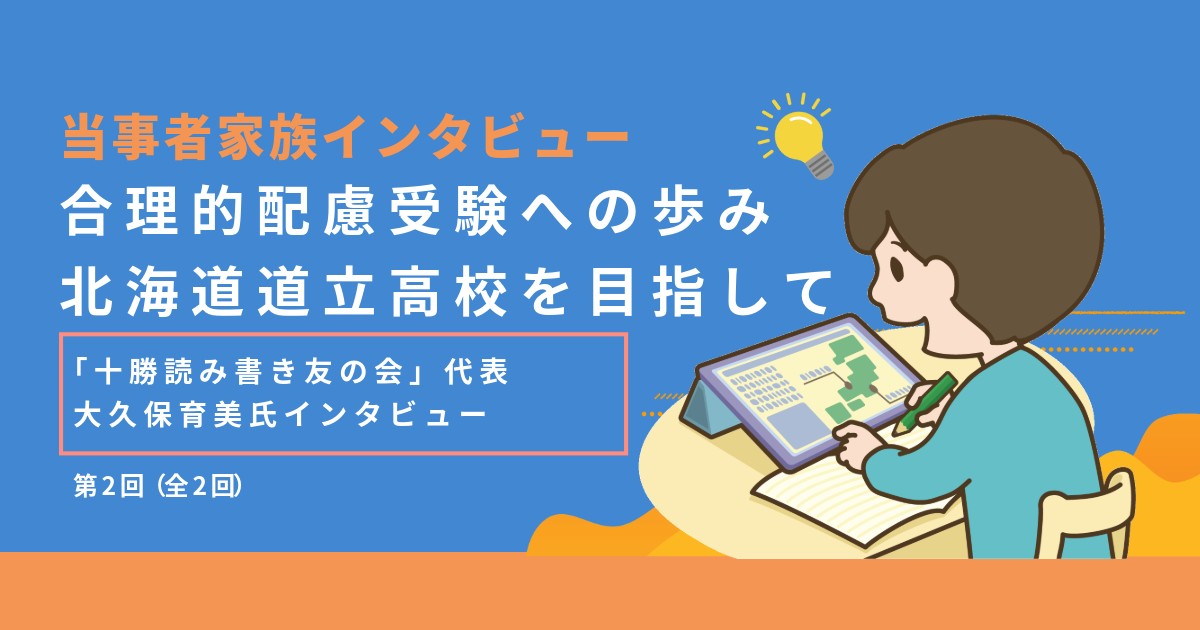
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験談を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。発達障害について発信を続けていくために、ご登録をお願いいたします。
本記事は、個人の体験談です。発達障害においては、たとえ同じ診断であっても、症状や困難は一人一人違います。また時期や地域によって、医療や教育、サポートの体制も大きく異なります。
●プロフィール
大久保育美(おおくぼ いくみ)
限局性学習症の我が子が自分のタブレット端末を使って学べるように、2014年から環境調整を続けた母親。その経験から2021年に「十勝読み書き友の会」を設立。オンラインで全国の保護者らと情報交換ができる機会を設けている。自らの子育てを通じ、学校での学びだけではなく、将来の自立に向けたあらゆる場面での合理的配慮を活用した実践を発信。個別の相談にも応じている。看護師・保健師・養護教諭二種免許等を持ち、さまざまな分野で勤務をした経験がある。
●中学校の高すぎる壁
大久保育美氏(以下、大久保):中学校での壁は高いものでした。そもそも合理的配慮というものを学校はしたことがなかったために、その方法を息子に聞くという感じになってしまって。担当の先生がうまく対応できなかったのです。例えば、夏休みの宿題はみんなと同じワークブックが配られました。そこで息子は、「データで欲しい」と教頭先生にお願いしたのですが、「できるわけない」と断られてしまいました。
−− タブレットの使用は、許可されていたのですよね?
大久保:されていました。ただコロナ前だったので、まだ1人1台という形には広がっていなかったのです。ですから小学校から使っていたタブレット端末(iPad)の持ち込みの許可を取るためだけに、大変な苦労をしました。息子は同じ端末を中学校でも使いたいという希望を出していました。しかし当時の中学校の校長先生に、「僕の権限では決められない」と匙を投げられてしまったのです。
入学前年の11月くらいから交渉を始めて、翌年1月になっても結論は出ませんでした。仕方なく弁護士を入れて、示談交渉を行いました。町の教育委員会と学校に対してです。それでやっと使っていいという結論に至りました。どうやらその校長先生は退任が決まっていたために、ご自身で「タブレットを持ち込んでよい」という判断を下したくなかったようです。
−− 「始めてのことを認める」ということをしたくなかったのですね。
大久保:また、とにかく管理職の先生達はICTに弱くて、宿題のデータを欲しいとお願いしても、「右から左に書き出して写せばできるよね?」などと言われて。これでは子どもは潰れてしまいます。
「気合い・努力・根性」という精神論を大切にしてきた方たちが、町の教育委員会や学校の管理職になっているようでした。ですから、こちらが言っていることが全然伝わらないんですね。もう、こちらが宇宙人、というか。
−− 「頑張ればできる!」という感じなんですね。それは厳しい。
大久保:最終的には、「特別な教育を受けるつもりはないか」と言われて。つまり、特別支援学校(養護学校)に転校してくれということです。
町の教育長は、こちらが言っていることは理解してくれていました。ただ、「早すぎる」と。
−− とはいえ、2018~2019年頃のことなんですよね。
大久保:はい。どうしても現場の理解が追いつかないと。ですから冗談半分で「大久保さん、2、3年どこかで氷漬けで寝ていたらいんじゃない」と言われました。できるんだったらそうしたかったです。
−− 町の教育長としては、大久保さんの言っていることはわかるけれど、それを現場に落とし込んで実行するのは無理だと考えていたと。わかるけど、できないってことですか。
大久保:そうです。やはり町の教育委員会は、北海道教育委員会の考えに基づくことになりますから、町だけ先に何かをするということは難しいのです。あと、教育長が事務方から上がってきた方だったということもあって、学校現場の指導に対して、そこまで口出しできないという構造もあったのではないかと思います。
−− そういった組織構造も、壁になっていたのですね。
大久保:後ろ盾がないままで、こういった交渉をするのは無理だと考え、DO-IT Japan (ドゥーイット・ジャパン)(*1)に申し込みました。締め切り3日前でした。それで特別聴講生に選ばれ、ホッとしたことを覚えています。
−− 東京大学先端科学技術研究センター(先端研)のプログラムですね。以前のインタビューでも、先端研の話がでました。こういった機関の名前が、個人が学校と話すときに意味をなしているということがわかります。
●入試の準備をスタート
−− 高校入試で合理的配慮を得るために、具体的に動き出したのはいつですか?