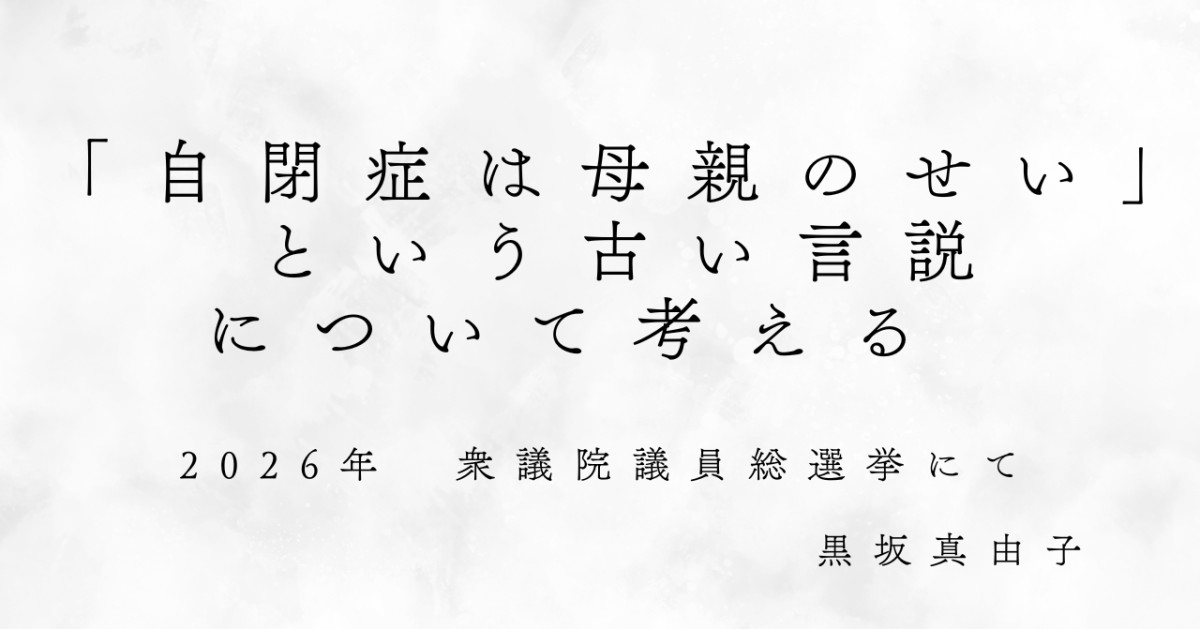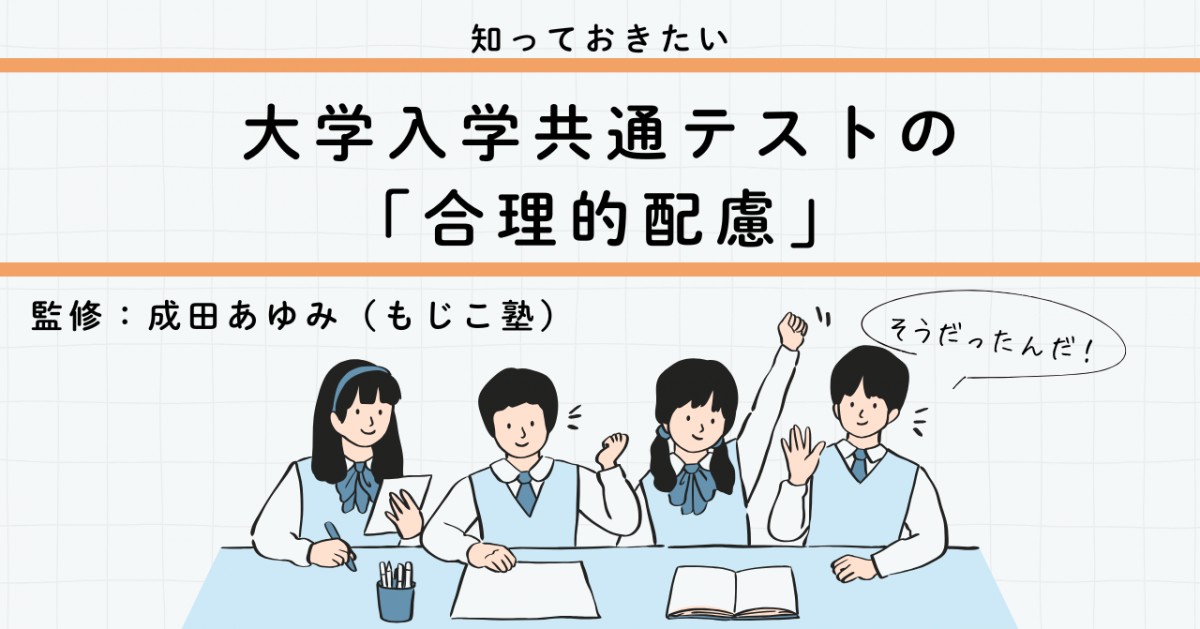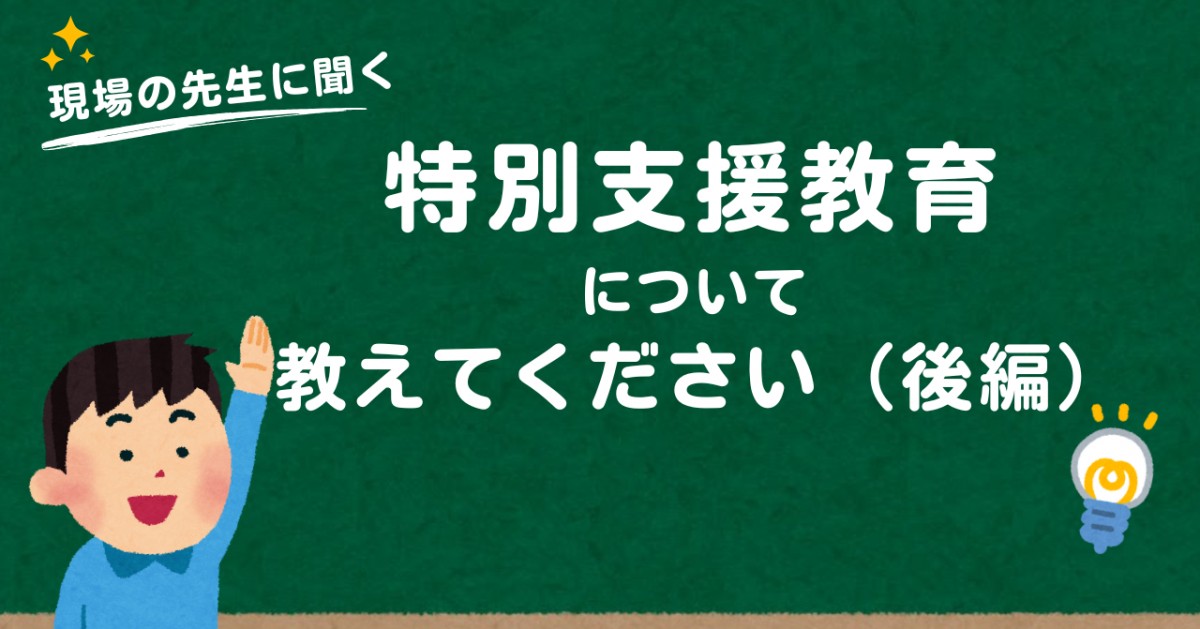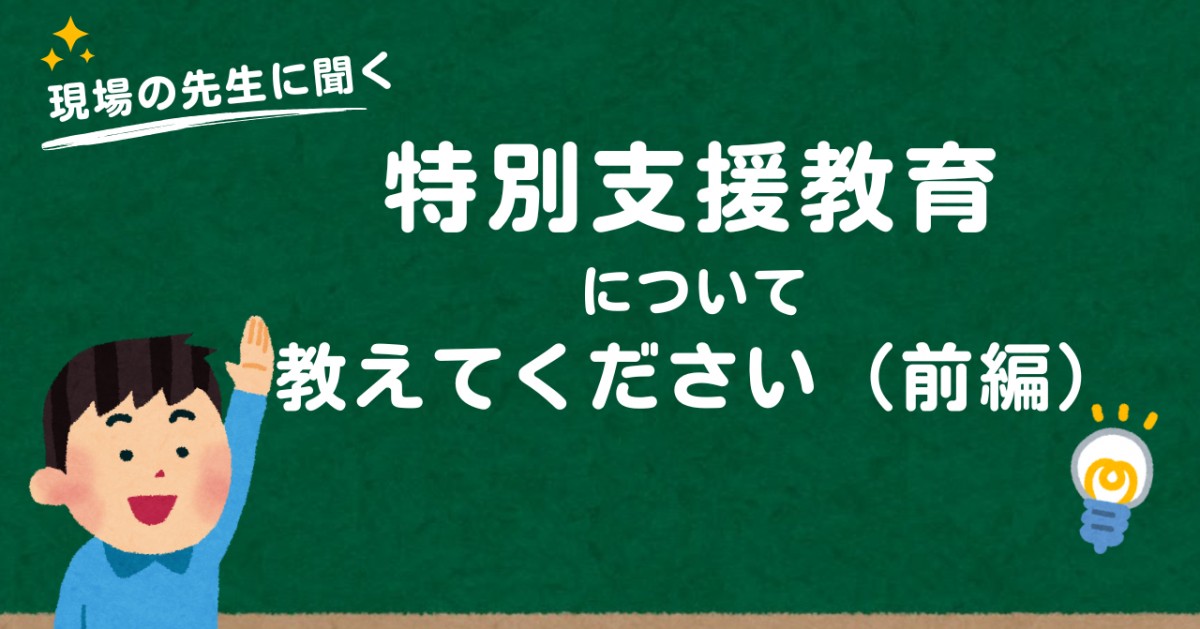障害者雇用での就職の難しさは、どこにあるのか
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験談を読むことができます(いつでも解約可能です)。発達障害について発信を続けていくために、ご登録をお願いいたします。
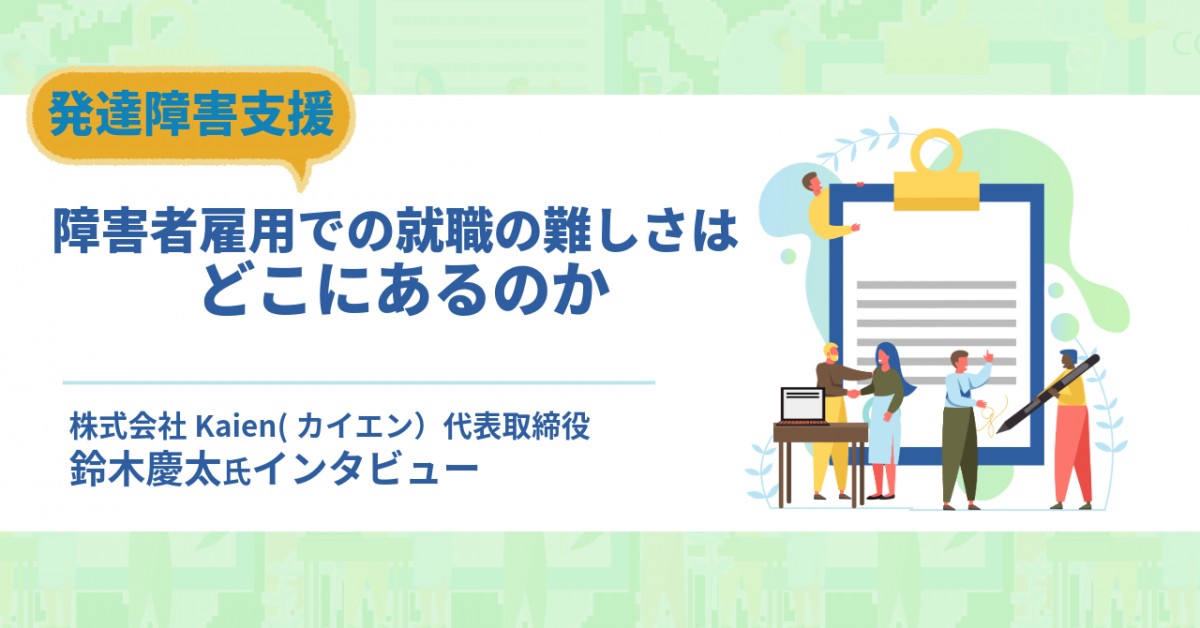
●プロフィール

鈴木慶太(すずき けいた)
長男の診断を機に2009年9月にKaienを起業。これまで1,000人以上の就労支援に現場で携わる。日本精神神経学会・日本LD学会等へ学会登壇や『月刊精神科』、『臨床心理学』、『労働の科学』等の専門誌への寄稿多数。著書に『フツウと違う少数派のキミへ: ニューロダイバーシティのすすめ』(合同出版)、『発達障害の子のためのハローワーク』(合同出版)、『知ってラクになる! 発達障害の悩みにこたえる本』(大和書房)など。元NHKアナウンサー。東京大学経済学部 2000年卒・ノースウェスタン大学ケロッグ経営大学院 2009年修了(MBA) 。星槎大学共生科学部通信制課程特任教授。
●ガクプロを始めた理由
−− なぜガクプロを始めようと思ったのでしょうか?
鈴木慶太氏(以下、鈴木):以前から中高生向けのサポートをしていたのですが、ある親御さんから「大学生になると通うところがない」と言われたのがきっかけです。2013年のことです。放課後等デイサービス(*1)の制度が始まった翌年のことで、当社もガクプロと同時にティーンズ(放課後等デイサービス)を始めました。
−− 放課後等デイサービスは、基本的に小学生から高校生までの障害のある子どもが利用できるものですね。
鈴木:そうです。発達障害の人が障害福祉を受けるということが、ようやく始まったのがこの頃なんです。ただ、大学生が利用できるような障害福祉サービスがなかったんですね。Kaienではすでに、放課後等デイサービスに当たる「ティーンズ」の前身のプログラムがあり、「就労移行支援事業(*2)」も2012年からスタートしています。この間をつなぐプログラムとしてスタートしたのが「ガクプロ」です。
−− 大学生向けにどのようなことが求められていたのでしょうか?
鈴木:就職へ向けての準備です。そのため、就労移行支援のプログラムを学生向けにアレンジしました。やっていて面白かったのが、ガクプロにおけるサークル活動です。大学のサークル活動に馴染めない学生が、ここでは楽しく飲み会をしていました。すごく仲良くなった子たちもいます。土曜日の1時くらいに集まって、セッションをした後に飲み会をするような本当にサークル活動みたいなものでした。
−− 当時と今とでは、内容や目的は変わっているのですか?
鈴木:就職へのサポートは、当時から変わっていません。ただガクプロを始めた頃より、就職市場はよくなっています。当時は障害者雇用においても、なかなか発達障害の人は受からなかったですし、一般的な雇用においてはもっと難しかった。今の方がずっと就職しやすくなっているのです。現在はある意味、発達障害を隠すことなく、胸を張って障害者雇用で就職する時代になってきたといえるかもしれません。
−− 売り手市場になり、発達障害がある人も就職しやすくなっているんですね。
鈴木:この10数年運営していく中で、障害福祉が使えるタイミングが明確になってきました。例えば就労移行支援的なものや、自立訓練(生活訓練(*3))は、大学生の最終学年で卒業がほぼ確定していれば使える場合があります。ただ、1年生や2年生のうちから参加できるようなものがない。その福祉の隙間の時期に利用できるプログラムが必要だと考えるようになりました。
−− 大学卒業が近くなると、就労移行支援や自立訓練(生活訓練)という公的な障害福祉サービスが利用できる。ただ、大学や専門学校での1年生、2年生が使えるような公的なサービスはまだないということなんですね。
鈴木:そうです。ガクプロは民間のサービスとなりますから、なるべく料金をおさえて気軽に使えるようなものにしようと、我々も努力しているところです。今年の4月からは、開催時間を短くする一方で、利用していただける期間を長くしました。内容も、土曜日は「就活前のプレ講座」のようなもの、平日はグループホーム(*4)や特例子会社(*5)など、将来暮らす、働く可能性のある場所の見学ツアーを行っています。
ただ、こういった均一なプログラムではカバーできないニーズがあることもわかってきました。例えば履修登録が大変だとか、就活にやる気がでないとか。そういった学生のお尻を叩く親のような役割が必要とされていることがわかったのです。
−− 計画を立てたり、スケジューリングをしたりすることが苦手な学生が多いと。
鈴木:ええ。ただ、そういうことが苦手な子でも、就労移行支援には来られるのです。つまり毎日であれば、問題ないんですね。同じ時間に同じ場所に通うことができる子でも、「自分が困ったときにつながる」とか、「1週間に1回通う」ということができない。そういう場面で困っている学生が多いということに気づいたのです。
−− 高校までは、毎日同じ時間に同じ場所に行けばなんとかなるけれど、大学だとそもそも行く時間も教室もバラバラです。一人暮らしを始めたりすると、なおさらスケジュール管理が難しくなるかもしれません。
鈴木:そこでコーチングのサービスを始めました。ガクプロの追加メニューですが、こちらを利用してくれる方が多いのには驚きました。コーチングだけを希望される方もいます。例えばうまく履修登録ができなかったり、締切りまでにレポートが提出できなかったりということがありますよね。大学の姿勢としては、「相談に来てくれれば対応します」というスタンスです。これだと動けない学生が多いのです。かといって、親がうるさく言ったら余計動かない。
−− 高校までは、先生が注意してくれますもんね。コーチングではどのように学生をサポートしているのでしょうか?
鈴木:個人面談をするだけでなく、LINEを使って日常的にスタッフからプッシュ型で連絡します。伴走するイメージです。「レポートの締切りはいつ?」「期末テストに向けた勉強の時間配分をしよう」「来週は会社説明会だね」とかですね。
−− 親代わりみたいですね。
鈴木:「意識し、選択し、動く」というステップを、自分でできるようになるためにサポートする仕組みです。
−− 10数年前と比べて、ガクプロに参加している学生に変化はありますか?
鈴木:以前より発達障害であることを隠している人は減っているかもしれません。「自分はこういうキャラだからガクプロに来た」という人は多くなっていると思います。
−− 納得して通っている。
鈴木:ええ。ある程度納得して、ガクプロを使ってもらっているのは大きいですね。ただ、大多数の学生は「自分はできる限り皆と同じ、『普通』の道を行きたい」と思っています。でもそれがうまくいかなくて、モヤモヤする。それを見た親がガクプロにつなぐという構造は、以前とあまり変わっていません。そういった学生は、半分納得、半分納得していないという感じで通っています。
また、以前はASD(自閉スペクトラム症)が多かったと思うのですが、今はADHD(注意欠如多動症)の学生と半々くらいだと思います。ADHDは、薬が一般的になってきたことである意味掘り起こされた感があります。少ないのは、LD(学習障害)ですね。これは可視化されてないと感じています。実はいるのに、福祉的なサービスにつながっていないのかもしれません。あるいは、他の発達障害との重なりがあることで見逃されている可能性もあります。ASDやADHDに注目してしまうからです。あと割合は定かではありませんが、「境界知能(*6)」での困り感を抱えた方も相当数いるのではないかと思います。
●障害者雇用での就職の難しさ
鈴木:ガクプロの利用者は半分弱くらいの方が障害者雇用で就職するのですが、障害者雇用での就職は一般的な雇用(以下、一般雇用)よりもはるかに難しいんです。
−− 一般雇用より、障害者雇用の方が難しいのですか?