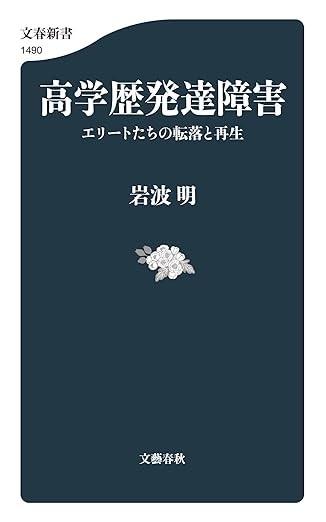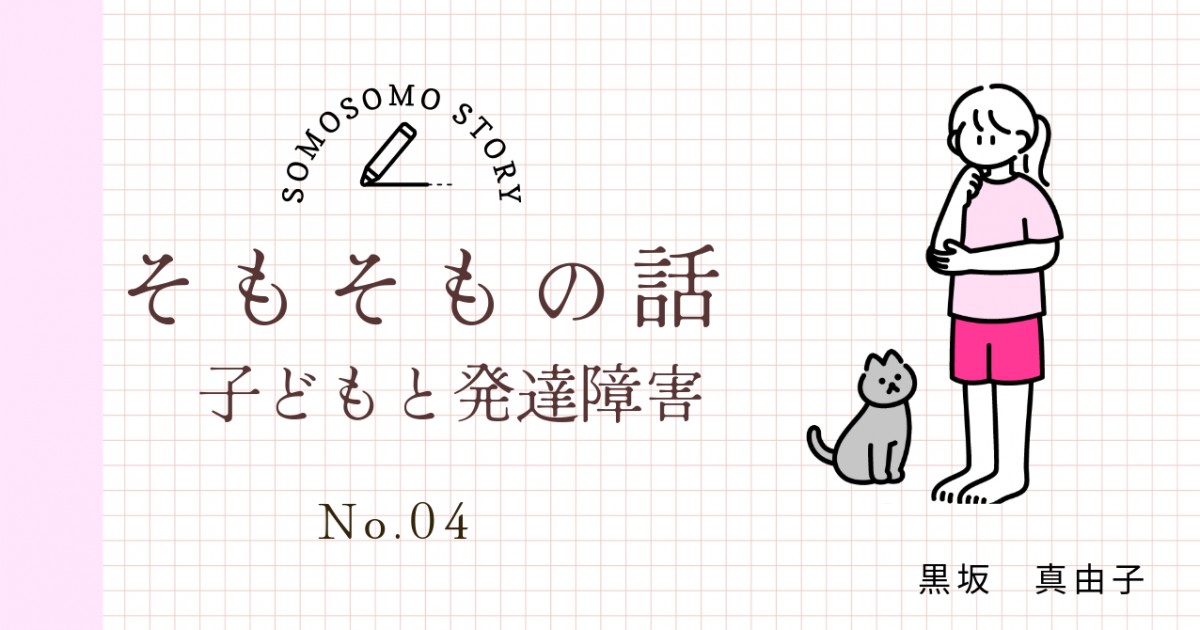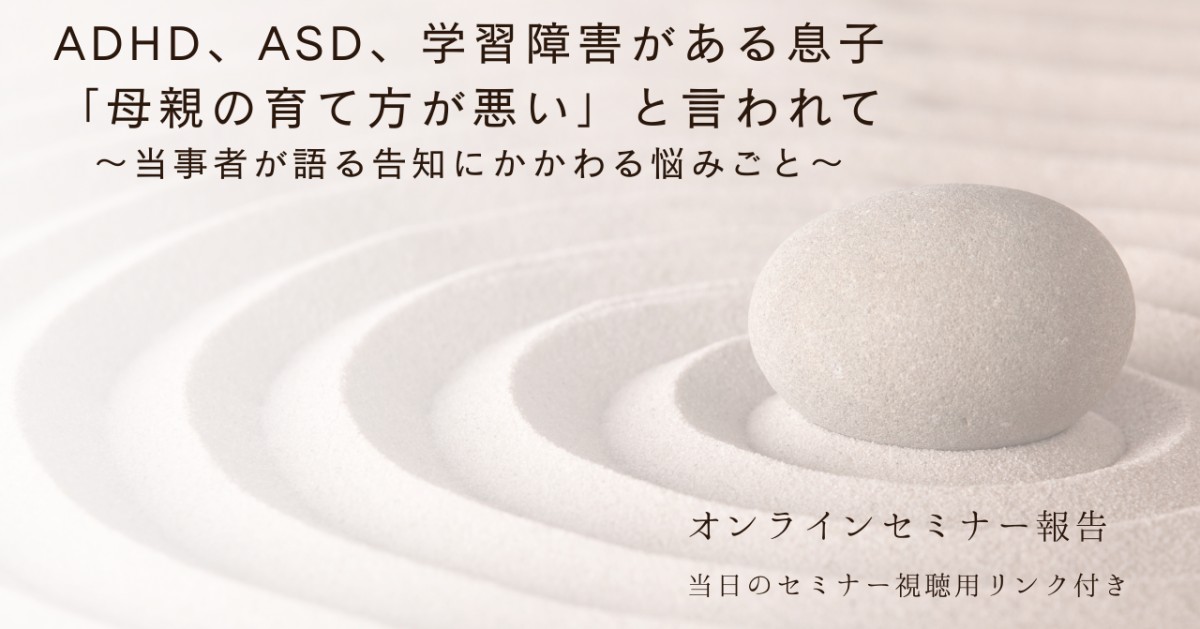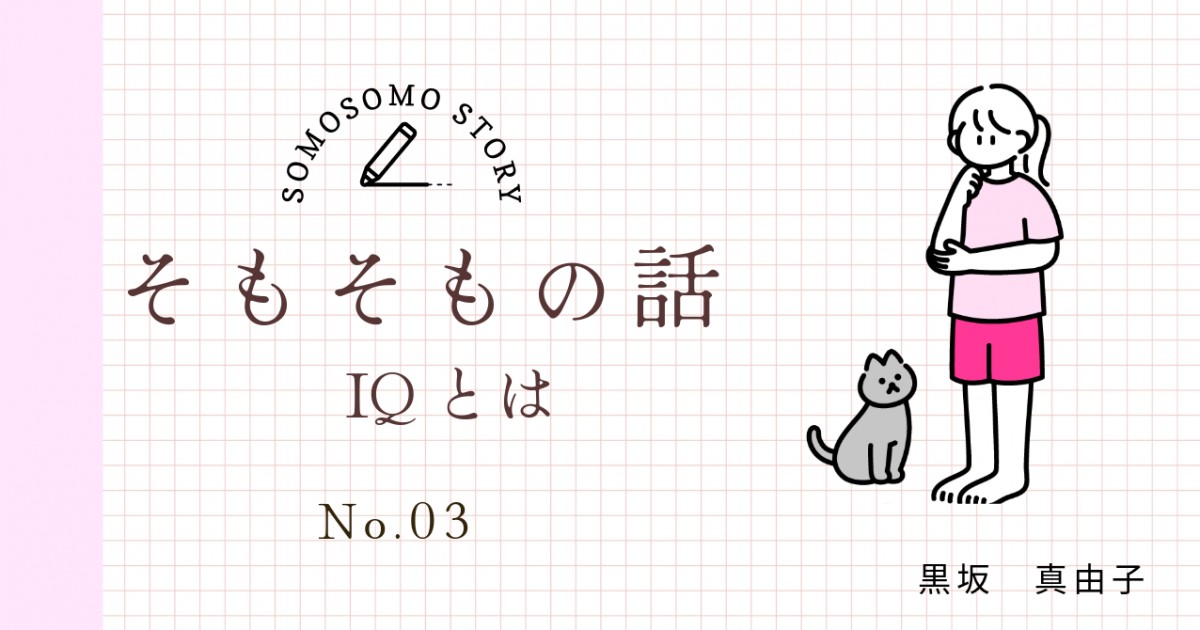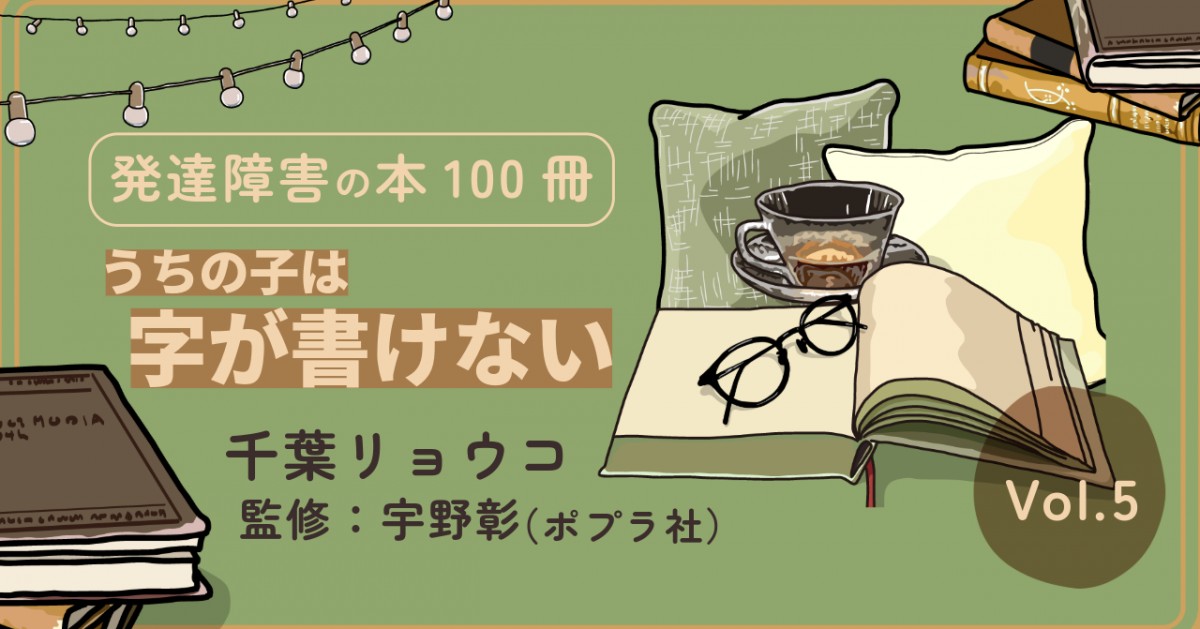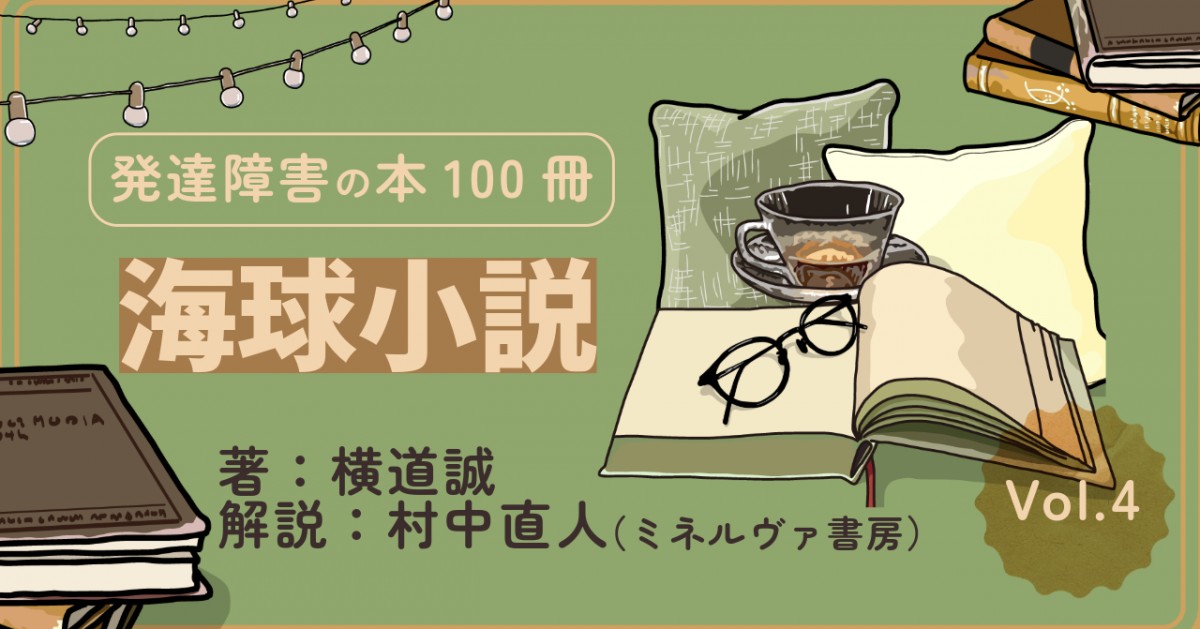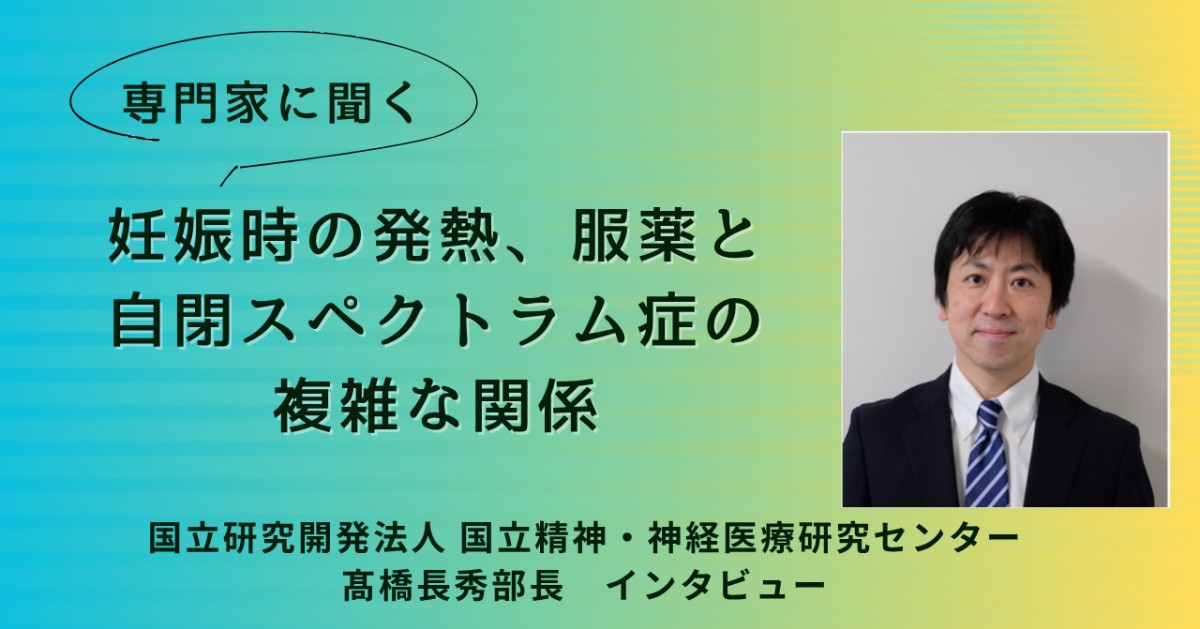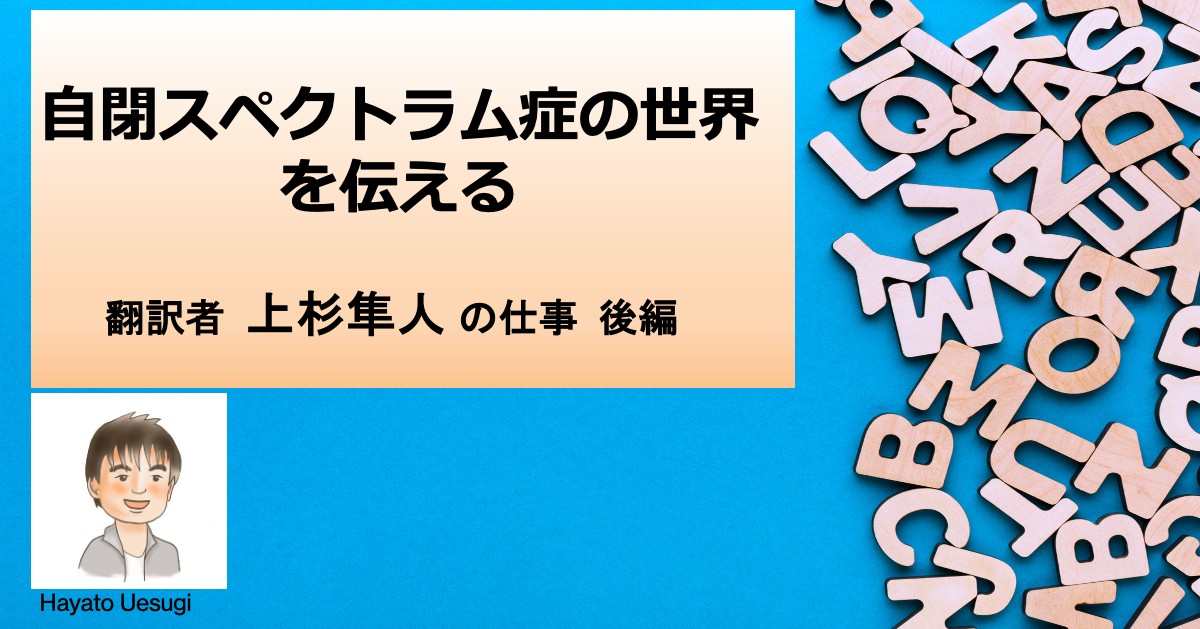『高学歴発達障害』岩波明(文春新書)
(2025年3月刊行)
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(いつでも解約可能です)。 発達障害について発信を続けていくために、ご登録よろしくお願いいたします。
本の紹介というと、どうしても新刊にかたよってしまいます。そこでこのコーナーでは、新刊・既刊に関わらず、これまで私が読んだ発達障害関連の本の中から、オススメの本を紹介していきます。また、インタビューに登場してくださった著者の本もご紹介します。インタビューと合わせてお読みいただくと、より理解が深まるはずです。
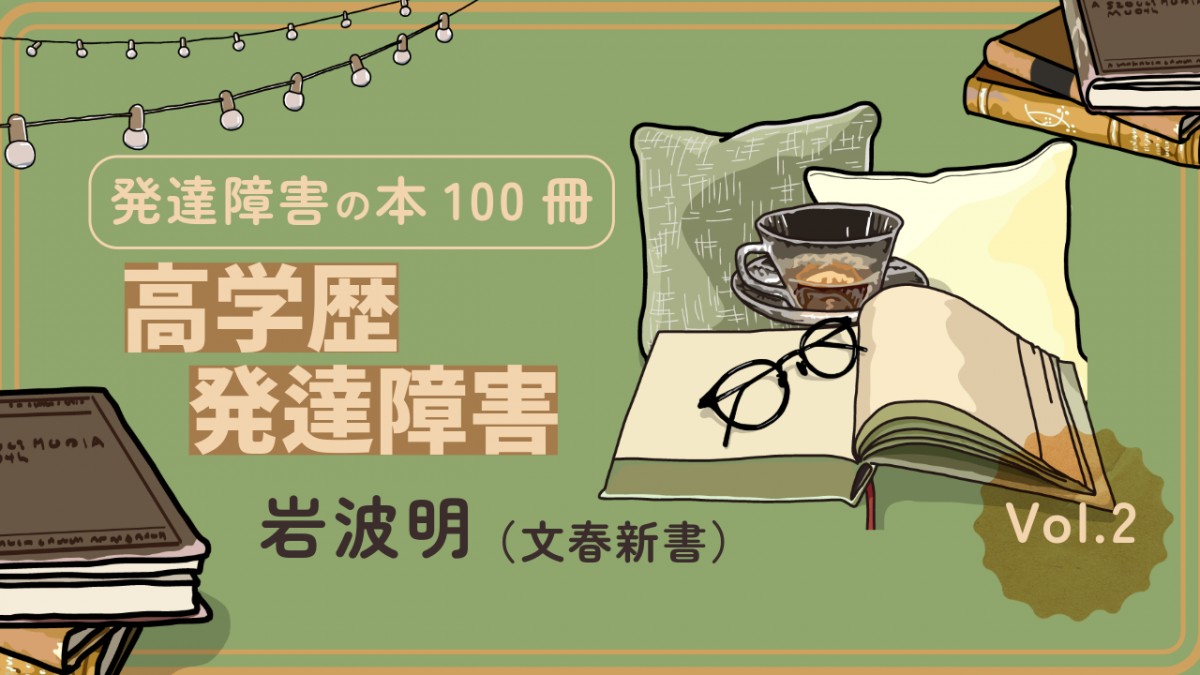
●著者プロフィール
岩波明(いわなみ あきら)
1959(昭和34)年、神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業後、都立松沢病院などで臨床経験を積む。東京大学医学部精神医学教室助教授、埼玉医科大学准教授などを経て、2012年より昭和大学医学部精神医学講座主任教授。2015年より昭和大学附属烏山病院長を兼任、2024年より昭和大学特任教授。ADHD専門外来を担当。精神疾患の認知機能障害、発達障害の臨床研究などを主な研究分野としている。著書にベストセラーとなった『発達障害』(文春新書)のほか、『狂気という隣人 精神科医の現場報告』(新潮文庫)、『大人のADHD もっと身近な発達障害』(ちくま新書)など。
*画像をクリックすると、アマゾンのサイトに移動します。
発達障害をもつ高学歴の人々の転落と再生
発達障害の中でも、高学歴であったり、能力がもともと高い人々の転落と、その再生を描いた書。岩波明氏は、長年臨床の現場で大人の発達障害を診療しています。大人になってから病院に来る人の中には、高学歴の人が少なくないといいます。それまで、なんとか社会に適応してきた人が、なんらかのきっかけ、例えば大学への進学や就職などで不適応となる事例が後を経たないのはなぜななのか。そのような人々の事例を、丁寧に解き明かしていったのが本書です。受験エリートの中高生から、自由を謳歌できるはずの大学生、社会人やフリーランス。「転落」から「再生」へ。その道のりをともに歩んできた岩波氏。そこには何があったのでしょうか。
岩波氏は、中高生について語る1章で、次のような近年の変化を述べています。
しばらく前の時代、不登校や引きこもりといった現象はどちらかというと特殊な現象で、その生徒や家庭環境に何らかの「問題」が存在するものと考えられていたように思える。(中略)1990年代の後半以降、不登校や引きこもりがより「一般化」するにつれて、これまでは目立たなかったパターンが認められるようになった。それは、一見したところ、「普通の家庭の普通の生徒」のケースである。「普通の家庭」といっても、経済的には比較的豊かであり、両親の知的レベルは高く、当事者の生徒も優秀な能力を持っていることが多い。
これまであまり問題にならなかった比較的豊かな家庭の優秀な子どもが、不登校に陥っているというのです。発達障害の専門外来を担当している岩波氏は、そのようなタイプの生徒を診療することが増えているといいます。
そしてこの不登校の原因として、中高の規則の厳しさを挙げています。
この点について岩波氏に実際に話を伺ったところ、東京においては特に、都立高校と女子校において学校の厳しさが増しており、発達障害がある生徒が適応するのが難しくなっているといいます。都立は出席日数に厳しく、規定を超えると留年となり、結果として退学して通信制に移るというパターンがみられるそうです。ADHD(注意欠如多動症)の人の中には、朝起きることが難しい人がおり、遅刻・欠席が増えてしまう。そうなるとあっという間に不登校から退学になってしまうのです。
また、女子校の「進学校化」も不登校を生む土壌になっていると岩波氏は推測します。これまで割とのんびりとした校風だった女子高が、学校の生き残りをかけて大学進学率を競うようになってきており、中堅の女子校にそれは顕著だとしています。もはや付属の女子大への進学が当たり前ではなくなり、その変化についていくのが難しい生徒がでてきているのです。
本書に登場するTJさんも、その1人。のんびりした学校生活を送ろうと思い、女子大付属校を中学で受験したものの、ADHD傾向のあるTJさんに毎日の予習復習と宿題をこなすことは難しく、不登校の末、退学。TJさんは紆余曲折ありながらも、通信制の高校からAO入試で難易度の高い女子大に合格しています。
本書は、このような実例を通じて、高学歴の人々や、能力があるのにそれが発揮できていない人々の事例を多数掲載。そして何より、適切な治療によってそれまで以上に能力が発揮できるようになった人々の姿を描いています。発達障害の特性や症状のために、自分が持っている能力を思い切り発揮できずにいる人は少なくありません。
長年現場で悩む人々を見てきた岩波氏の次の言葉に勇気づけられる人も多いはずです。
彼らはメンタルダウンし不登校や引きこもりを続けていた場合でも、治療の手助けを受けながら、自らの特性を自覚して対応策をとれるようになると、見違えるように回復し、以前のレベルよりもさらに良い状態に達することが可能なのだ。
もともと持っているポテンシャルの高さを生かせれば、再生への道は開けるのです。
しかし、それは同時に諸刃の刃でもあります。「治療困難な人」について岩波氏は、「高学歴であるために自分なりに勉強して思い込みが強くなりすぎ、結果として回復が困難となる人も存在する」としています。治療法や薬の処方を自ら医師に指示したり、体裁を気にして受診や治療を拒否する傾向も見られるというのです。中には医師やスタッフに反論を繰り返す人まで。治療に対する「理論武装」は、自らの回復を妨げてしまうこともあります。
治療と投薬、サポートのケーススタディとしても
本書では、それぞれの患者にどのような治療がなされたかが記されているのも特徴です。そのため、今後本格的な治療に入ることを考える方にとって、治療に関するケーススタディーになっているのもポイント。発達障害の治療がどのような経過をたどるのかを、まとめて確認することができます。例えば投薬一つをとっても、「Aという薬からBという薬にスイッチ」したり、「AにBを追加」したり、「Aを増量」したりなど、同じ薬を使用するにしてもさまざまな方法があることがわかります。
また薬を使わずに、就職移行支援(障害のある人の社会参加をサポートする国の支援制度)を利用して就職したり、行動変容を目的とした精神療法に活路を見出したケースもあります。治療のみならず、サポートや精神療法を通じて、新たな道を歩み出す人がいるということがわかります。
現在の日本社会において、高学歴であることは生きやすさの指標の一つであったことは間違いありません。しかし、それだけではうまくいかない。そこに発達障害が関わっているかもしれないと思った時に、手に取りたい一冊です。
すでに登録済みの方は こちら