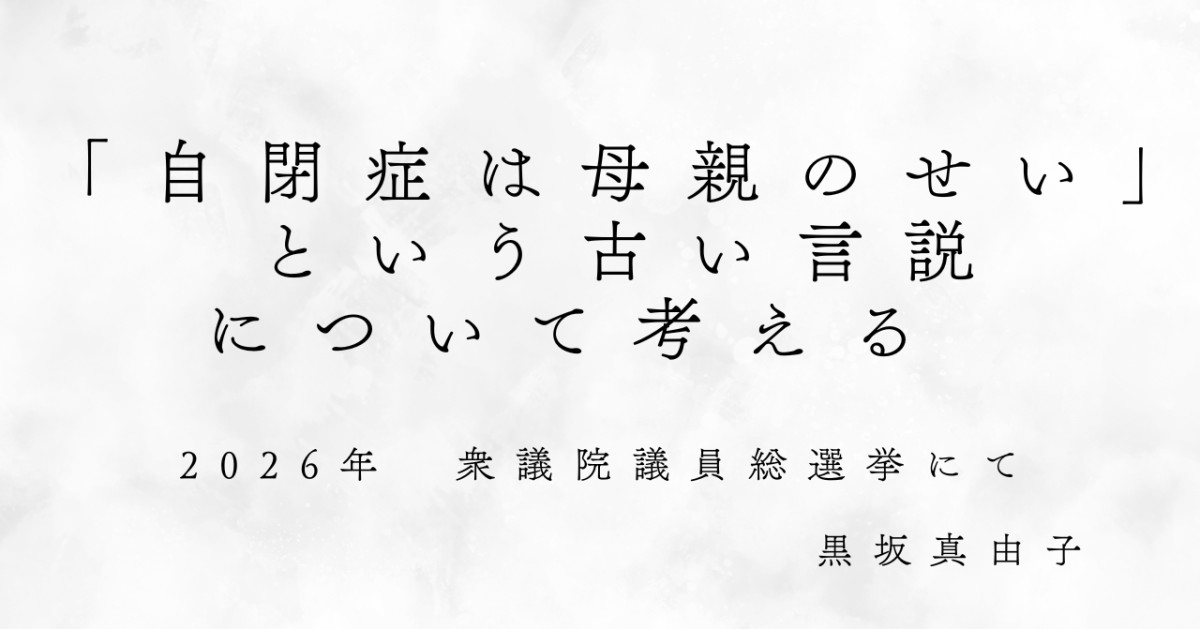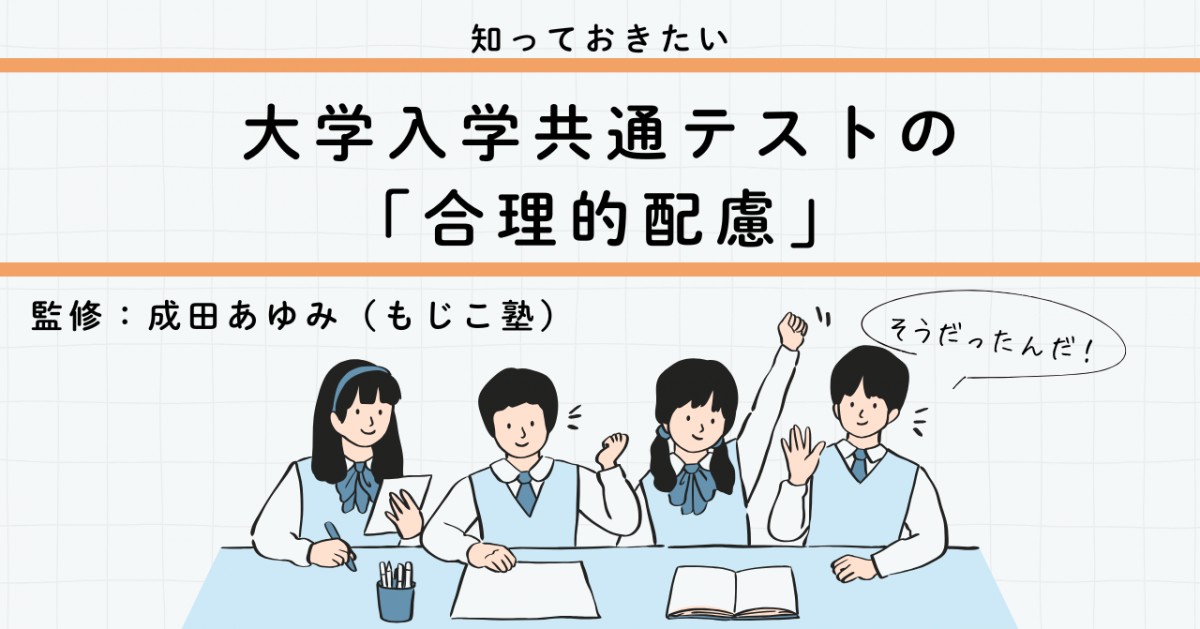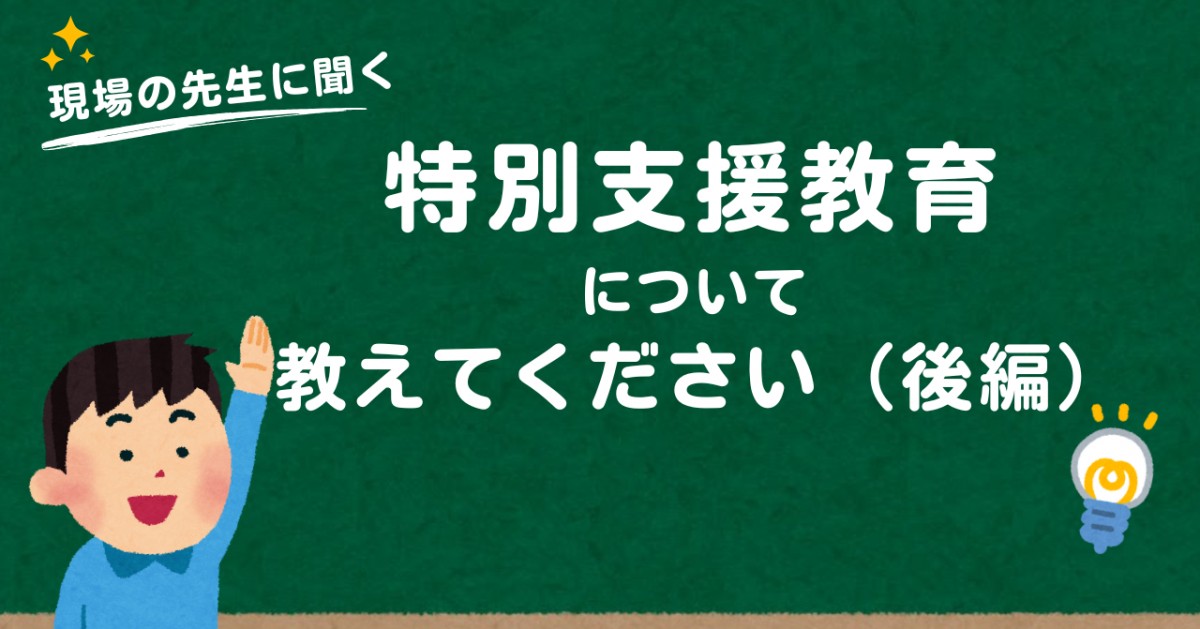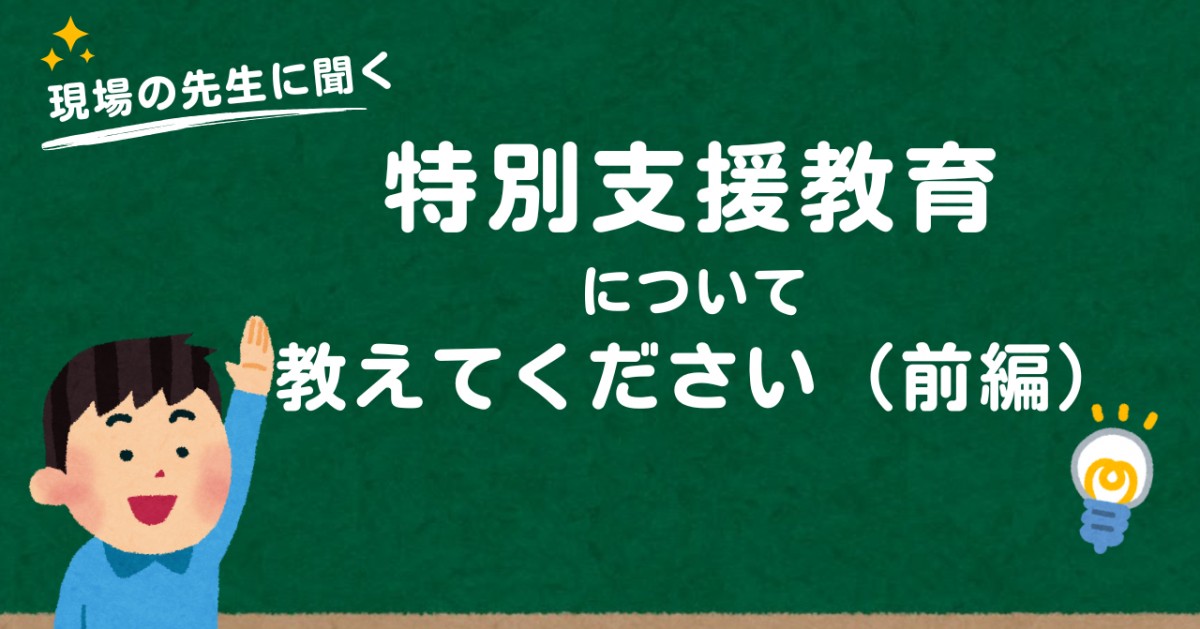発達障害の子どもの教育
弱視学級への在籍と放課後等デイサービスの利用
学習障害(LD、限局性学習症)のある息子さんをサポートし、北海道で初の合理的配慮を受けて道立高校入試に挑んだ経験について、「十勝読み書き友の会」代表の大久保育美さんにお話をお聞きしました。 第1回(全2回)
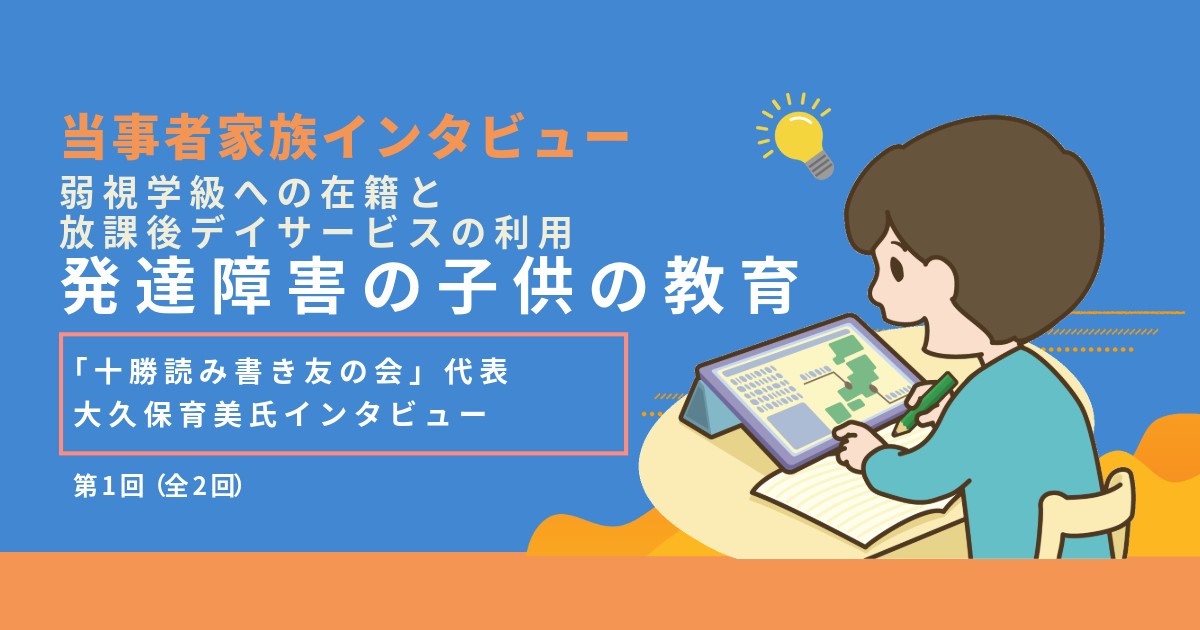
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験談を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。発達障害について発信を続けていくために、ご登録をお願いいたします。
本記事は、個人の体験談です。発達障害においては、たとえ同じ診断であっても、症状や困難は一人一人違います。また時期や地域によって、医療や教育、サポートの体制も大きく異なります。
●プロフィール
大久保育美(おおくぼ いくみ)
限局性学習症の我が子が自分のタブレット端末を使って学べるように、2014年から環境調整を続けた母親。その経験から2021年に「十勝読み書き友の会」を設立。オンラインで全国の保護者らと情報交換ができる機会を設けている。自らの子育てを通じ、学校での学びだけではなく、将来の自立に向けたあらゆる場面での合理的配慮を活用した実践を発信。個別の相談にも応じている。看護師・保健師・養護教諭二種免許等を持ち、さまざまな分野で勤務をした経験がある。
●弱視学級で学ぶ
−− 特別支援教育を受けたのは、いつからですか?
大久保育美氏(以下、大久保):小学校3年生からです。弱視学級に籍を置くことになりました。1、2年生の間は、通常級でした。なぜ通常級で学べたかというと、町の教育委員会の方針で1、2年生は少人数学級だったからです。1クラス20人を切っていたんですね。ただ、3年生以降は国の基準になり、1学級40人になるといわれて。息子が通常級で学ぶのは難しいのではないか、という話になりました。
たまたまコーディネーターの先生が、WISC−Ⅳ(ウイスク・フォー)(*1)、WAVES(ウェーブス)(*2)やフロスティッグ(フロスティッグ視知覚発達検査)(*3)ができて、検査をしてくれたのです。大学院まで出ている特別支援教育を勉強された先生でした。それで息子は、特に書くことと図形の認識に困難があるということを見つけてくださったのです。「これは本人の努力ではどうにもならないから、弱視学級を考えては」ということになりました。
−−それで 3年生から、弱視学級に籍を置いたのですね。
大久保:はい。現在の文部科学省の弱視学級の「障害の程度」(*4)には、「拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能又は著しく困難な程度のもの」とありますが、そのような困難があれば弱視学級に在籍できることを先生が知っておられたんですね。「図形の認識が困難」という部分が当てはまるということで、弱視学級に在籍できるよう申請を出してくれました。
ただ、その先生が5年生の終わりにいなくなってしまって。それで、病院で正式な診断を受けた方がいいかもしれないと考えたのです。自治体の発達相談センターから北海道大学病院につないでもらいました。ですから正式に診断を受けたのは、小学校5年生です。ただそこでの最初の診断は、ASD(自閉スペクトラム症)でした。
−− 学習障害(LD、限局性学習症)ではなく。
大久保:ええ。なぜ最初にASDという診断がついたのかといえば、学習障害と診断するための十分な時間がなかったからというのが、正直なところです。診療時間の関係です。ただ、教員とぶつかる、気持ちを自分の中で抑え込んでしまうなど、対人関係の問題が明らかだったために、ASDという診断はつけられたということになります。診療を受けていく中で、学習障害の方に重点が置かれるようになっていきました。WISCやKABC-Ⅱ(ケーエービーシー・ツー)(*5)の検査をして、知的障害があるわけではないけれど字が書けないことがわかったからです。「これはかなり苦しかったね」と先生からも言われました。ですから6年生の頃には、完全に学習障害という診断がつき、特に書くことへの困難が大きいということがわかりました。
ただ、なかなか学習障害というのは理解されなくて。唯一理解してくれていたのが、その転任してしまった先生と、大学病院の先生しかいなかったのです。
●理解されない発達障害
−− 息子さんが小学生の頃というのは、「発達障害」という言葉自体は広まっていましたか?