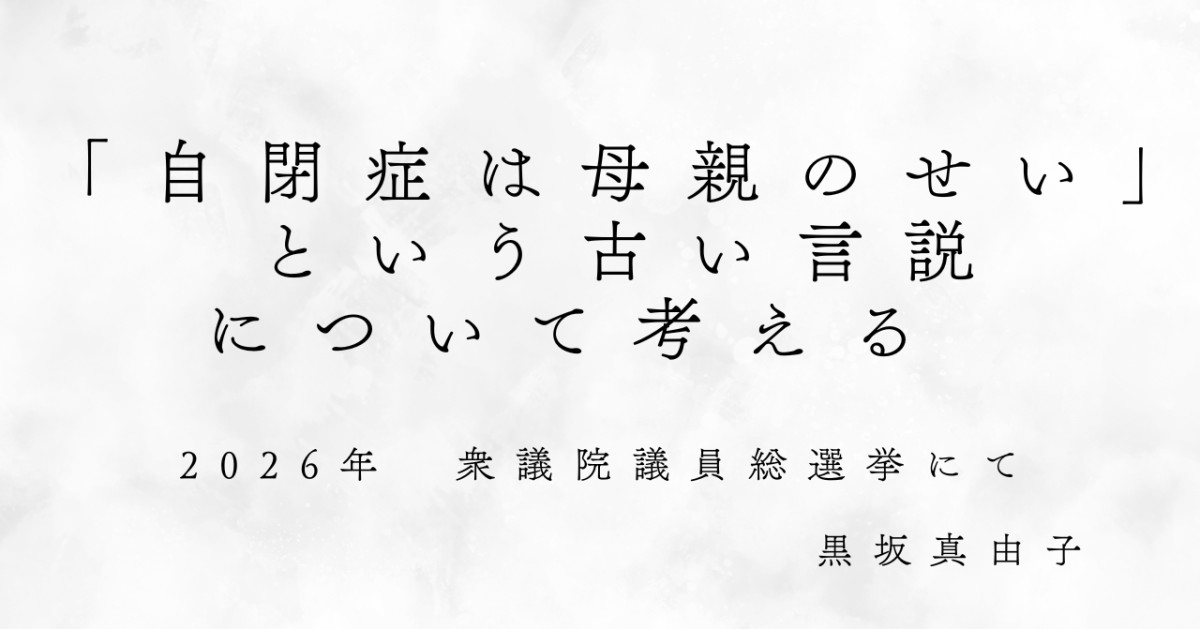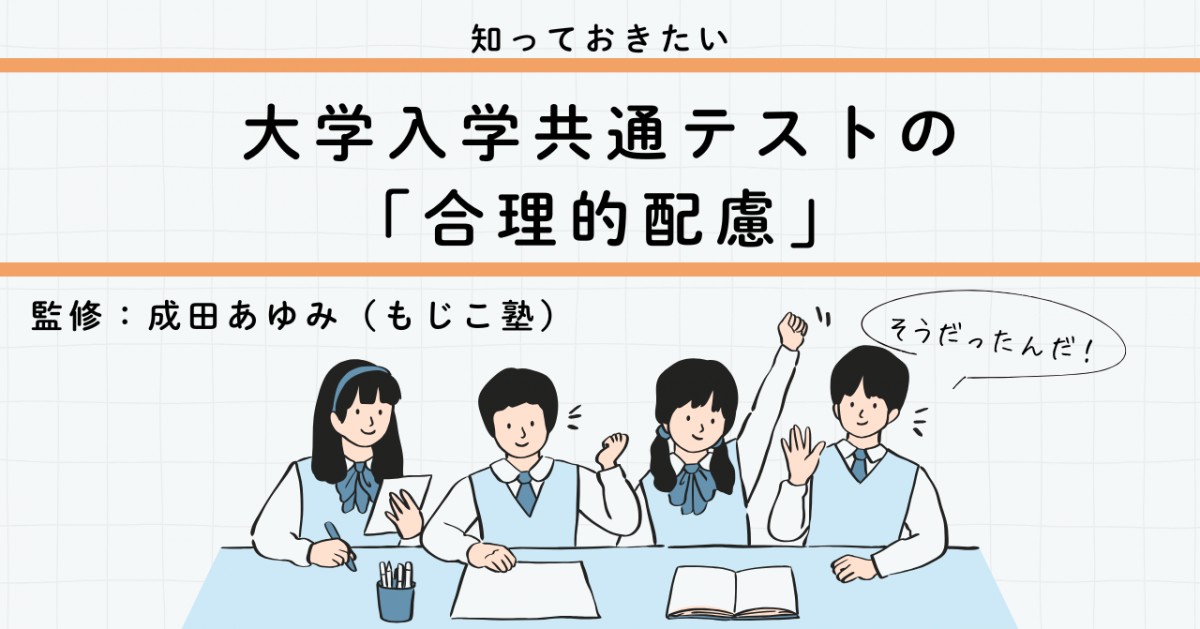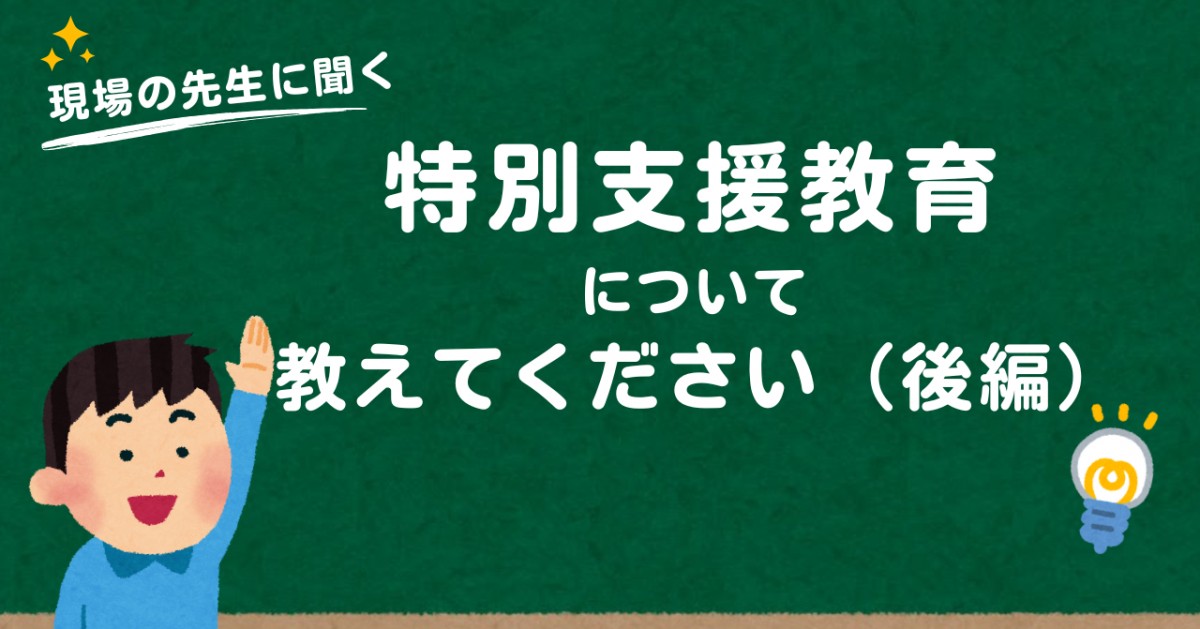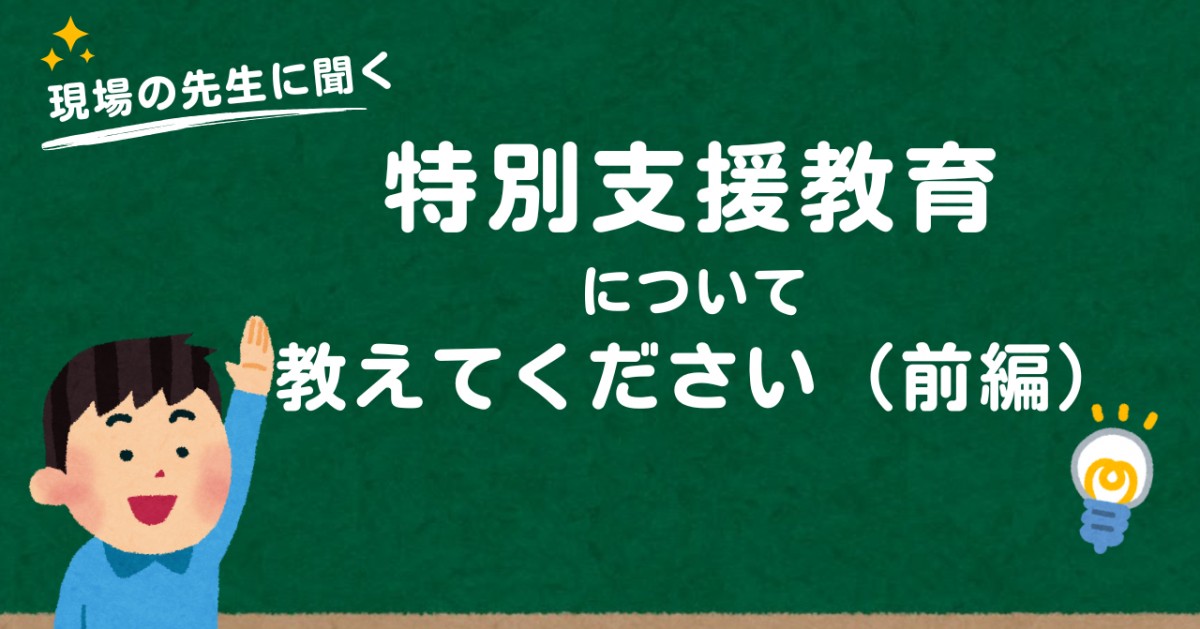発達障害と投薬 発達障害の薬は、どのような症状にどう効くのか
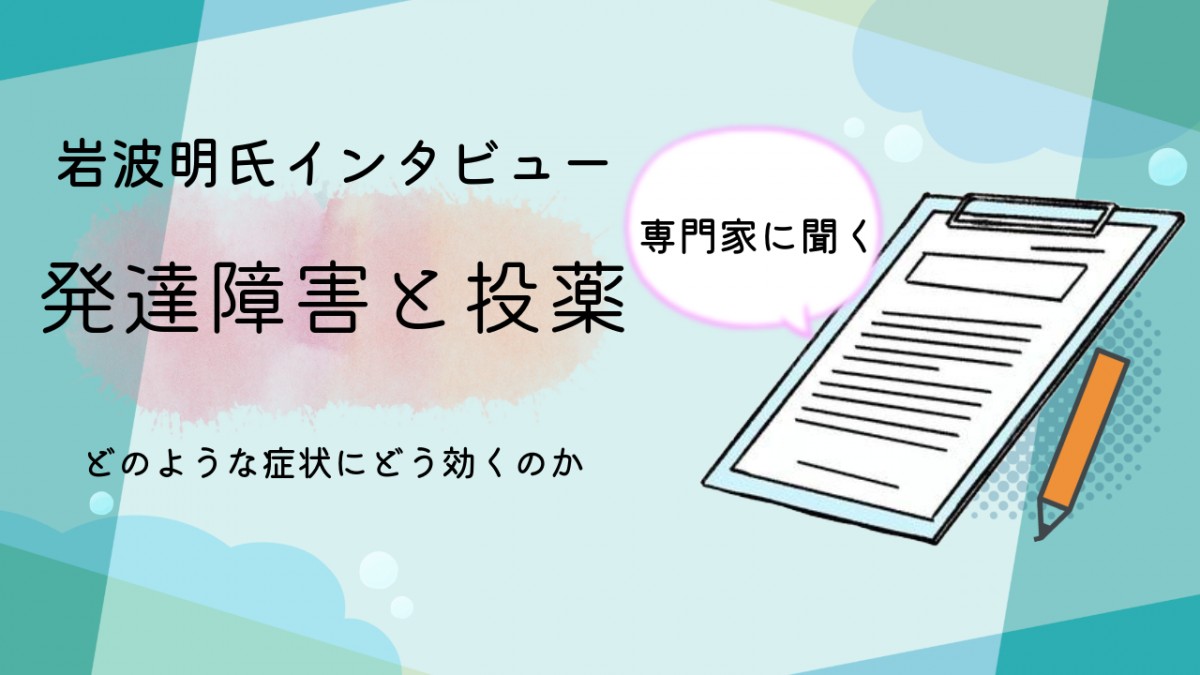
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(いつでも解約可能です)。ご登録よろしくお願いいたします。
●プロフィール
岩波明(いわなみ あきら)
1959年、神奈川県生まれ。東京大学医学部卒業後、都立松沢病院などで臨床経験を積む。東京大学医学部精神医学教室助教授、埼玉医科大学准教授などを経て、2012年より昭和大学医学部精神医学講座主任教授。2015年より昭和大学附属烏山病院長を兼任、2024年より昭和大学特任教授。ADHD専門外来を担当。精神疾患の認知機能障害、発達障害の臨床研究などを主な研究分野としている。著書にベストセラーとなった『発達障害』(文春新書)のほか、『狂気という隣人 精神科医の現場報告』(新潮文庫)、『大人のADHD もっと身近な発達障害』(ちくま新書)など。
●ADHDに薬があり、ASDにないのはなぜか
−− ADHD(注意欠如多動症)に薬があって、ASD(自閉スペクトラム症)にないのはなぜですか?
岩波明氏(以下、岩波):ADHDの薬に関しては、偶然見つかったのです。アメリカの大富豪夫妻が、娘のために薬を探し回ったことに端を発します。1879年生まれのエマ・ペンドルトン・ブラッドリーという娘さんはADHDではなかったのですが、7歳の頃に発症した脳炎の後遺症があり、多動のような症状がみられたそうです。親御さんは私財を投じて、それこそ世界中をまわって治療法を探していたのですが、エマさんの薬を見つけることはできなかったんですね。それで遺言で、これまでなかった子どもの精神疾患を扱う病院を設立することにしたのです。ロードアイランド州に現在も娘さんの名前を冠した大きな病院があります(*1)。
ADHDの薬は1930年代に、その病院で見つかりました。
−− 娘さんのために設立した病院で見つかったんですね。
岩波:多動に対して、精神刺激薬が効くとわかりました。これが現在のADHDの薬である「コンサータ」や「ビバンセ」の開発の第一歩でした。
実はASDに対してもいろいろと試されているのですが、あまりいい結果は出ていません。「オキシトシン」というホルモンが効くのではないかという話があり、アメリカなどで臨床試験が行われていたのですが、成功しませんでした。
−− オキシトシンというと、いわゆる「幸せホルモン」と呼ばれるものですね。授乳時に分泌される。
岩波:そうです。対人関係を良くする効果があるのではないかと考えられてのことです。
−− ADHDの方が薬を使うメリットには、どのようなことがありますか?
岩波:大部分のADHDの人が注意・集中の問題で受診されます。要するにミスが多いとか、パフォーマンスが悪いとかですね。本人自らの病院に来る場合もあれば、会社から言われてということもあります。こういった注意・集中の問題は投薬によって改善する場合が多いです。
−− その方が本来持っている能力がADHDの症状によって阻害されているから、薬を飲むことで本来のパフォーマンスが出せるということになるのでしょうか?
岩波:人によっては、期待以上のパフォーマンスが出る場合もあります。IQ的にかなり高い方でも、不注意があったり、集中できなかったりすれば、仕事上の問題が多数生じます。ですから、その部分が改善されればよい結果に繋がることが多いのです。
−− ADHDの特徴のひとつに、創造性が挙げまれます。薬によって、創造性が失われることはないのでしょうか?
岩波:そういう心配があることはわかります。アーティスト的な仕事をしている人、例えばイラストレーターの人から、「発想が豊でなくなってしまった」と言われたことはあります。ただそれは、薬を少し止めればいいだけなんですね。そうすればすぐに戻ります。
−− そうなんですね。薬を飲んでアイデアが浮かばなくなってしまったから、薬をやめるという人もいるのでしょうか?
岩波:いますね。いったんやめて、また始める方もいます。
−− 薬を飲んだとしても、永遠に創造性が消えてしまうわけではないのですね。
岩波:一過性です。
−− 薬を飲み続けなければ、アイデアが次々に浮かんでくるという状況は変わらないということですか。
岩波:アイデアが次々に浮かんでくるということは、それはそれでプラスではあるのですが、それはつまり「頭の中が多動」という状態なのです。これは「マインド・ワンダリング」と呼ばれ、集中力が阻害された状態です。このマインド・ワンダリングが創造力につながれば良いのですが、本題と関係のないことばかりを考えてしまう状態に陥ることもあるのです。その状態を抑えなければ、いろいろな場面でコントロールが効かなくなってしまいます。
−− そうなると、職業にもよるということになりそうですね。マインド・ワンダリングがうまく芸術方面などに出せる人はいいけれど、皆がそういう仕事をしているわけではありませんから。
岩波:通常業務だと、困るわけです。やっぱり芸術家的な仕事ですよね。漫画家とかイラストレーターとか。最近、世界的な音楽家を診ています。その方は誤診されていて、最近ADHDだとわかり、ADHD用の薬を飲み始めてよくなったと言っていました。
−− ASDは特に、「自閉の文化」、もしくはより広い概念として「ニューロダイバーシティ(神経多様性)」の文脈で語られることがあります。定型発達の人との違いを、「優劣ではなく文化の違い」で捉える考え方です。この側面から考えると、文化と薬の衝突があるのではないかと思ったのですがいかがでしょうか。
岩波:そもそもASD用の薬がまだないので、そういうことは少ないですね。ASDの方に薬を使うのは、うつ病や不眠症になった場合です。ASDの症状のそのものに使われる場合は、例えばこだわりの症状に使われる場合がありますが、それは強迫症状に近い場合です。例えば、何度も確認し続けてしまうとか、嫌な記憶のフラッシュバックが繰り返される場合などです。嫌な記憶のフラッシュバックには、もちろん百発百中ではありませんが、向精神薬、特に抗うつ薬がある程度効くので使う場合があります。
●薬はどう効いているのか
−− ADHDの薬について教えてください。
岩波:基本的にはドーパミン、ノルアドレナリンの機能障害を改善します。それらの機能が低下しているのだろうと考えられているのです。ただ、確証はないんですね。
−− ドーパミンは意欲を高め幸福感を感じさせてくれる物質。ノルアドレナリンは集中力ややる気に関わる物質ですね。これらの脳内にある物質が、脳に残るようにする薬が効いていると。
岩波:関係しているのではないかと推測されています。ただ、推論なんですよ。いろいろ試してみたら、そういった薬が効いたということです。
−− 実験で結果が出たわけではないのですね。
岩波:それらしい結果が出ることもあるのですが、再現性がなかったりします。動物実験で出た結果が人間で通用するか、という話もあります。まだ確証はありません。
精神疾患に使われるような薬というのは、そういうものが多いのです。例えば、一番長い歴史があるのが「統合失調症」の薬です。昔は「分裂病」と呼ばれていました。統合失調症にはドーパミンを遮断する薬が使用されます。ドーパミンが過剰になると、興奮しすぎたり、依存症や幻覚・妄想の原因になることがあるとされているからです。ただ、統合失調症の方が「本当にドーパミンが高いのですか?」と言われると、今だにはっきりとそういう結果は出ていないのです。ドーパミン遮断薬を使ったら、統合失調症の症状が非常によくなった。だから「統合失調症ではドーパミンが亢進している」と考えられているということなんです。これは「ドーパミン仮説」といわれ、60年以上ずっと仮説のままなのです。
−− 精神疾患に関する薬というのは、そのように「効くから使っている」ということが多いのですか?