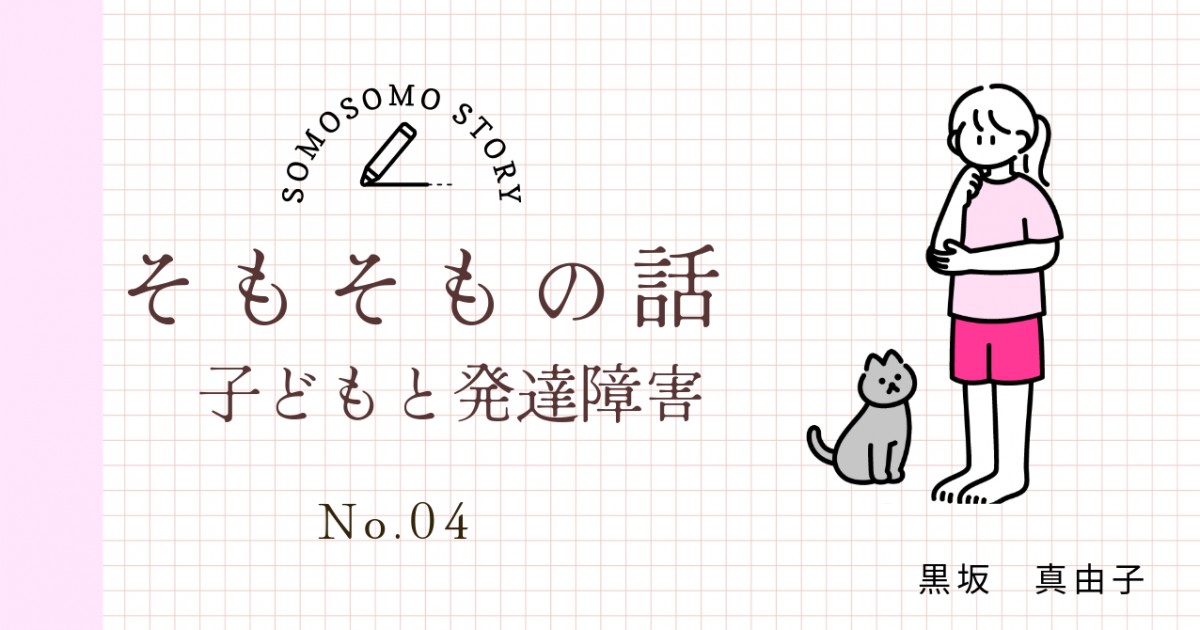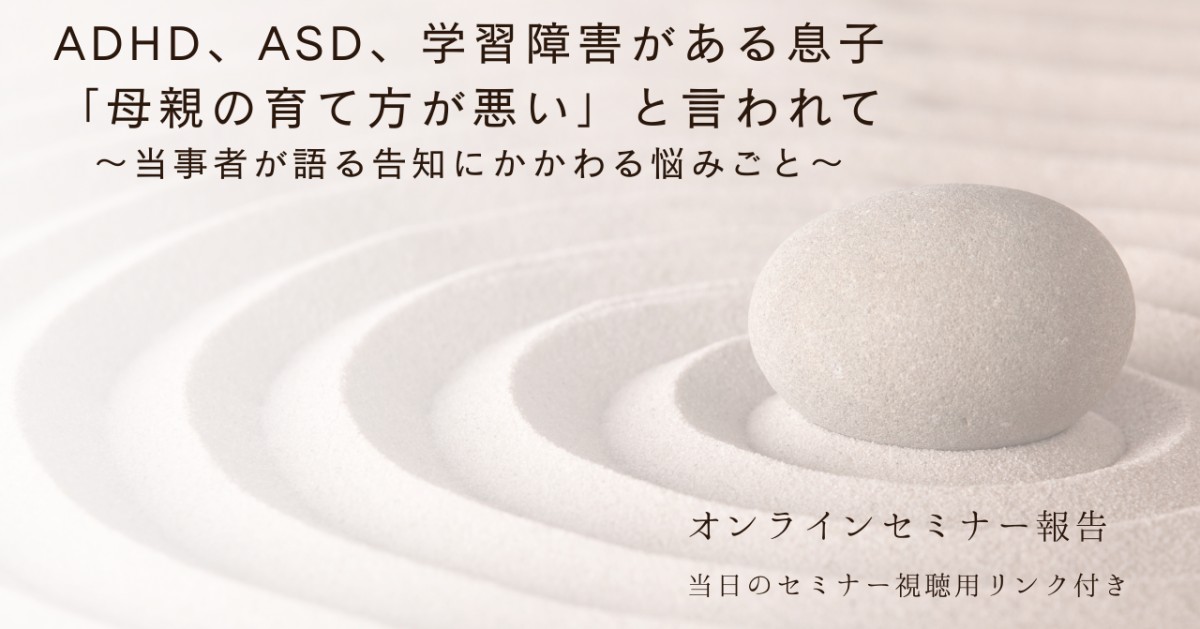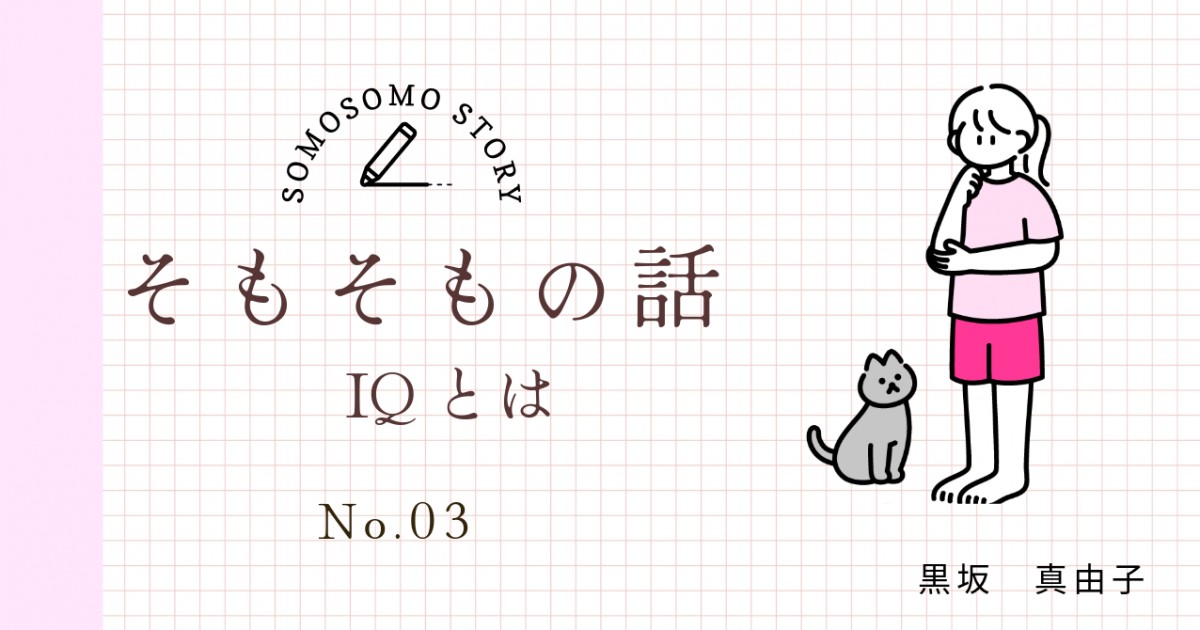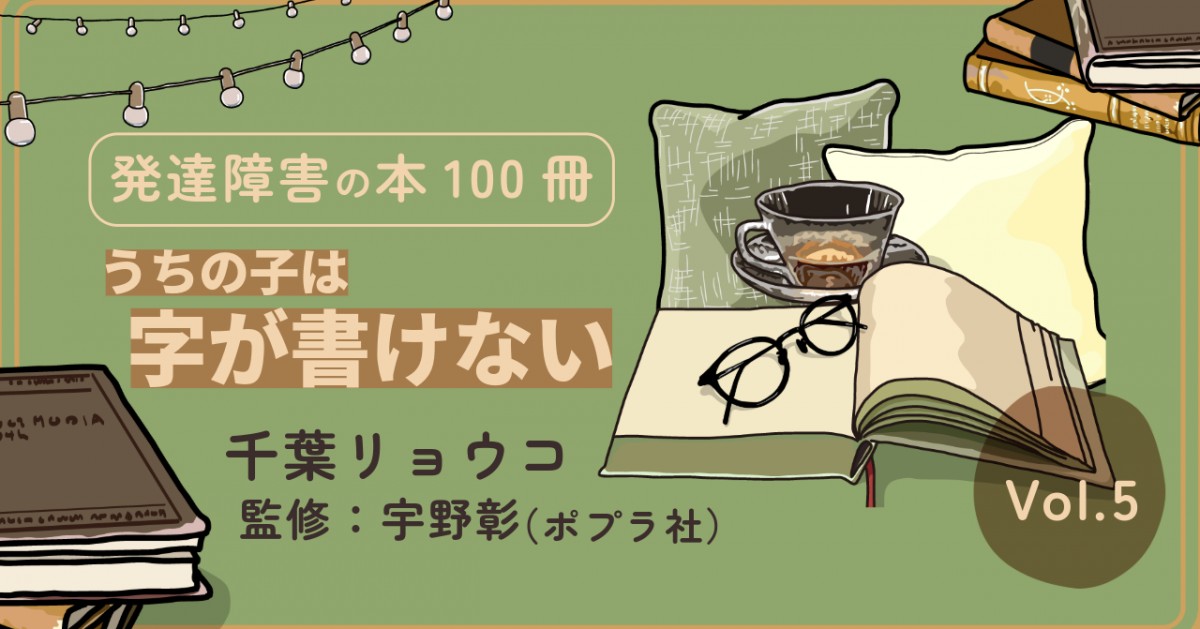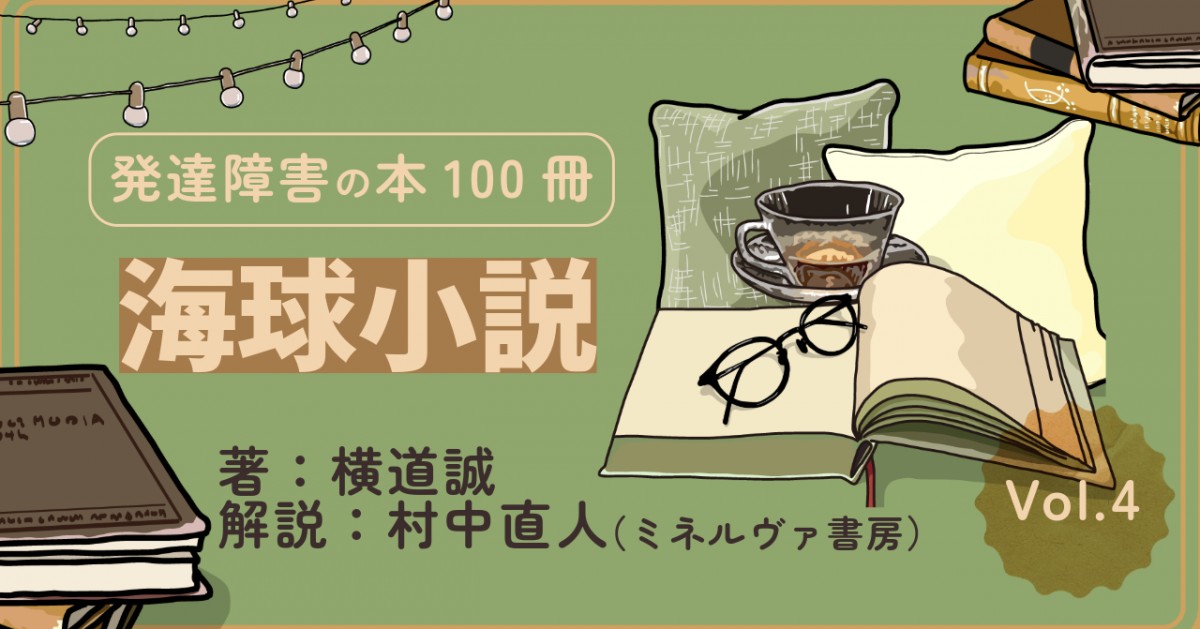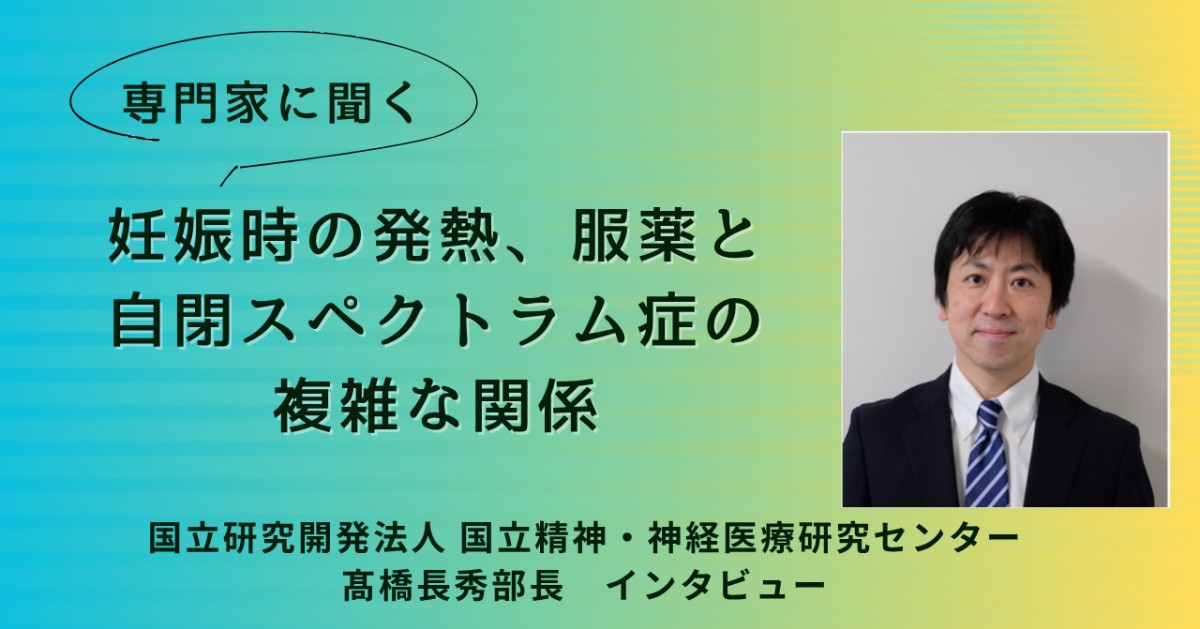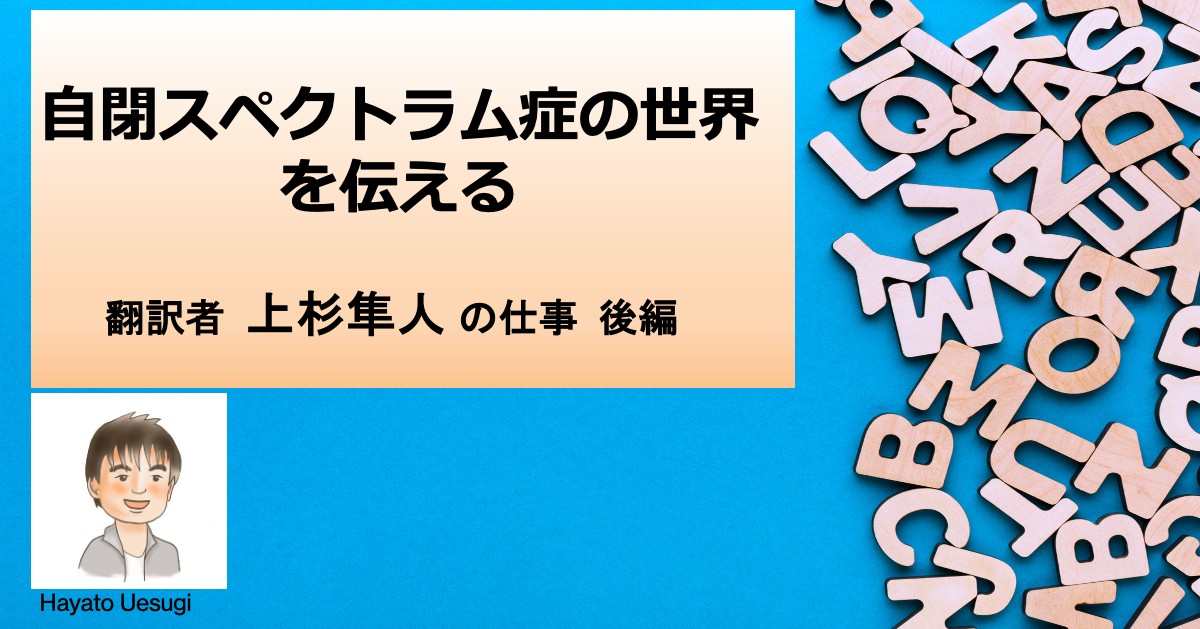[発達障害の本 100冊]
『発達障害はなぜ誤診されるのか』
岩波明 (新潮選書)(2021年2月刊行)
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。
発達障害について発信を続けていくために、応援をよろしくお願いいたします。
本の紹介というと、どうしても新刊にかたよってしまいます。そこでこのコーナーでは、新刊・既刊に関わらず、これまで私が読んだ発達障害関連の本の中から、オススメの本を紹介していきます。また、インタビューに登場してくださった著者の本もご紹介します。インタビューと合わせてお読みいただくと、より理解が深まるはずです。
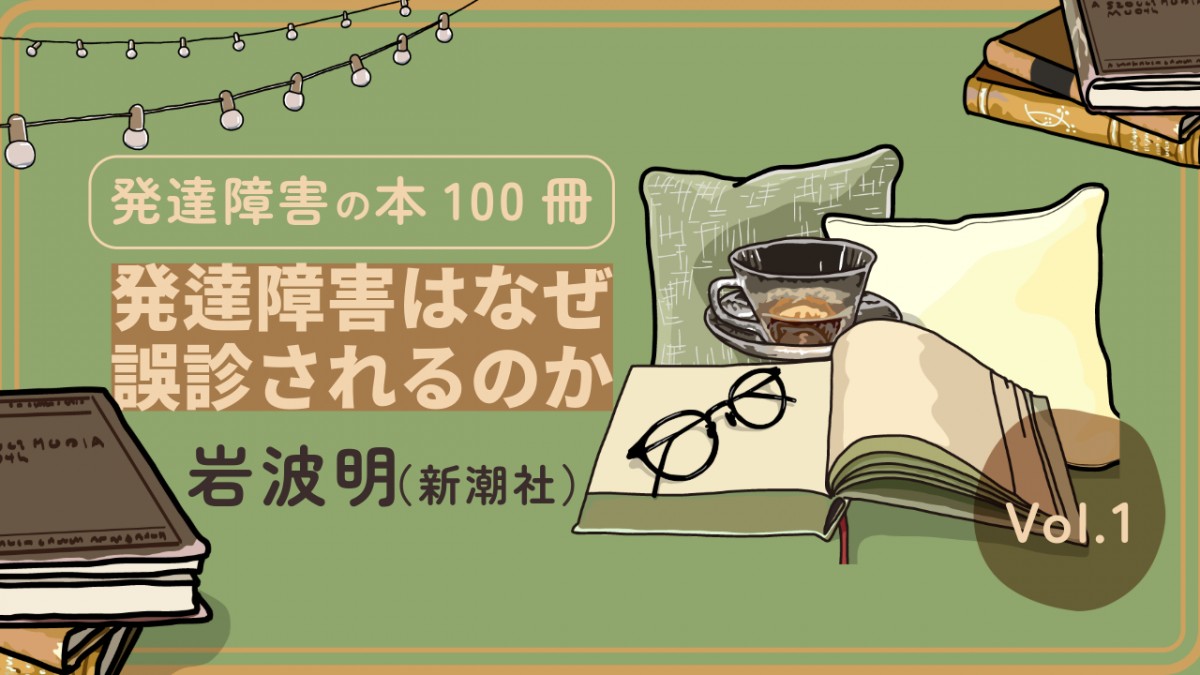
岩波明(いわなみ あきら)
1959(昭和34)年、神奈川県生まれ。東京大学医学部医学科卒。精神科医、医学博士。発達障害の臨床、精神疾患の認知機能の研究などに従事。東京都立松沢病院、東大病院精神科などを経て、2012年より昭和大学医学部精神医学講座主任教授、2015年より昭和大学附属烏山病院長を兼務。2024年より昭和大学特任教授。著書に『発達障害』(文春新書)、『医者も親も気づかない女子の発達障害』(青春新書)、『誤解だらけの発達障害』(宝島社新書)など多数。
●誤診は珍しくない
その診断は間違いかもしれない−−。
その理由を解き明かしてくれるのが本書です。著者の岩波明氏は、「大人の発達障害」を世の中に知らしめた第一人者。これだけ「発達障害」という言葉が広まったのは、2017年に出版された岩波氏の著書『発達障害』(文春新書)が果たした役割も大きかったと思います。
ただ、「発達障害」に関して、誤診率が高いことは、あまり知られていません。臨床の現場で、大人の発達障害を診断している著者は、日常的に誤診に遭遇します。なぜなら、いくつもの病院を回った末に、著者のもとへと辿り着く患者が少なくないからです。本書は、その豊富な臨床経験から、誤診に至る背景や原因を、実際のケースとともにわかりやすく示した一冊です。
●誤診の背景に、何があるのか?
発達障害の誤診の背景を、岩波氏はいくつか類型化しています。
最初に挙げられるのが、「医師の知識不足」です。
大人の発達障害というのは、精神科医にとっても比較的新しい分野です。そのため、現在現役で診療をしている精神科医の多くが、成人の発達障害に関する教育や研修を受けたことがないといいます。「成人期の発達障害」が、医学教育に含まれるようになったのは、比較的最近のこと。そのため、精神科医自身が、学んでこなかった分野であるために、診断をすることができないというケースがあるわけです。
「他の精神疾患との併存」も、発達障害が誤診される原因となります。
発達障害で生じる二次的な症状が、「うつ病や不安障害などから生じる症状と似ている」ため、ベースにある発達障害が見逃されてしまうことは、珍しくないといいます。よくある誤診の一つが、「長年うつ病と診断されていたが、ADHD(注意欠如多動症)がベースにあり、うつ病はその併存症だった」というものです。
また、ADHDとASD(自閉スペクトラム症)の症状が似ていることも、誤診につながる要素です。著者は、「実際の臨床現場では、ASDとADHDを明確に区別できないことは少なくない。筆者自身も、しばしば判断に迷うことがある」と述べています。
例えば「相手に構わず一方的に話を続ける傾向」という問題において。ADHDの場合は「衝動性」が原因なのに対し、ASDにおいては「自分の興味、関心ある話題」に集中してしまうことが原因となります。行動の背後にあるメカニズムは違っても、周囲が目にする行動は同じなので、見分けがつきにくくなってしまうというのです。
さらに、「ASDの過剰診断」という問題があると著者はいいます。
2000年代に、「天才」の代名詞のように、もしくは少年犯罪との関連において、メディアでさかんに使われた「アスペルガー症候群」と診断されることは、まれではなかったといいます。
2025年現在の「DSM-5-TR」(米国精神医学会作成の「精神疾患診断・統計マニュアル第5版」の最新版)では、「アスペルガー症候群」は、ASDに含まれる下位分類となっているため、メディアにおいて使われることはずいぶん減ってきている印象がありますが、言葉が一気に広まったことは、少なからず診断の現場に影響を与えてしまったのかもしれません。
●発達障害周りの精神疾患の整理にも
本書を読むと、発達障害周りの精神疾患にどのようなものがあるのかを、知ることができます。言葉だけ知っていて、どのような疾患だかわからなかった「双極性障害」「統合失調症」「パーソナリティ障害」などについて、章を分けて解説しているため、発達障害との違いを整理することができました。
実は、「発達障害ではない」疾患を理解することは、発達障害とはなにかを理解する助けになると私は思います。発達障害というのは、なかなか理解しにくいものです。「◯◯ではない」と除外していくことで、浮かび上がってくることがあると感じます。
本書はリアルなケースとともに解説されているため、とても読みやすく、発達障害について調べ始めたばかり、という方にもおすすめできます。本書を読むと、誤診に長い間気づかれず、苦しんできた方が少なくないことがわかります。そのような状態を避けるためにも、受診する前に読んでおきたい一冊です。
・岩波明氏のインタビュー「発達障害は、なぜ誤診されるのか?」は、こちら
すでに登録済みの方は こちら