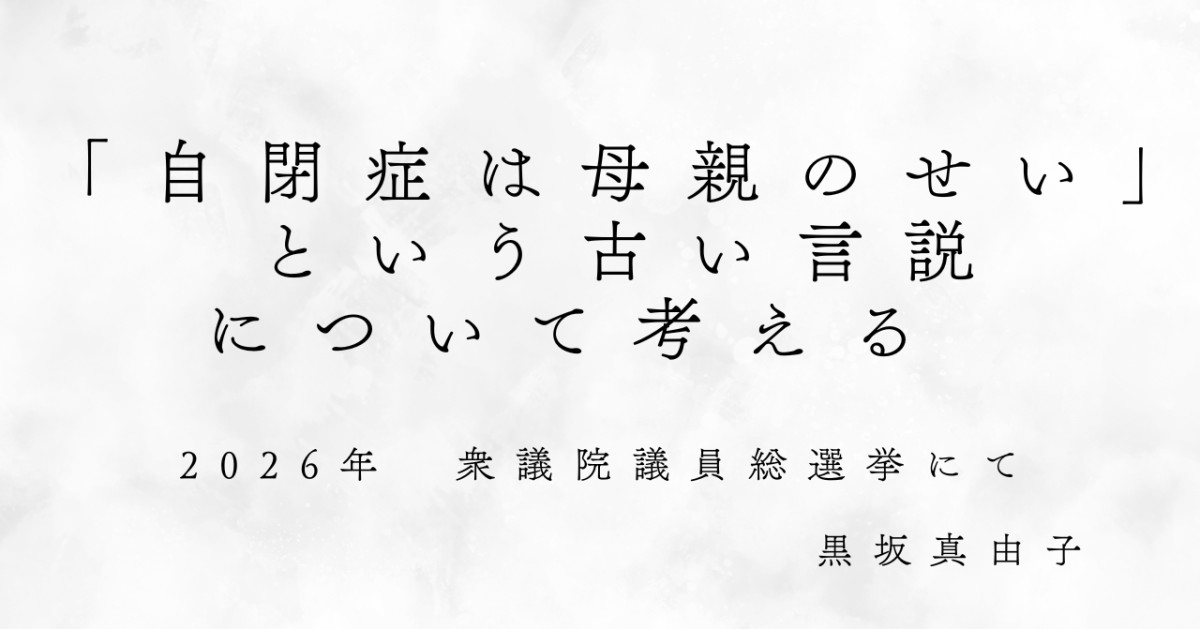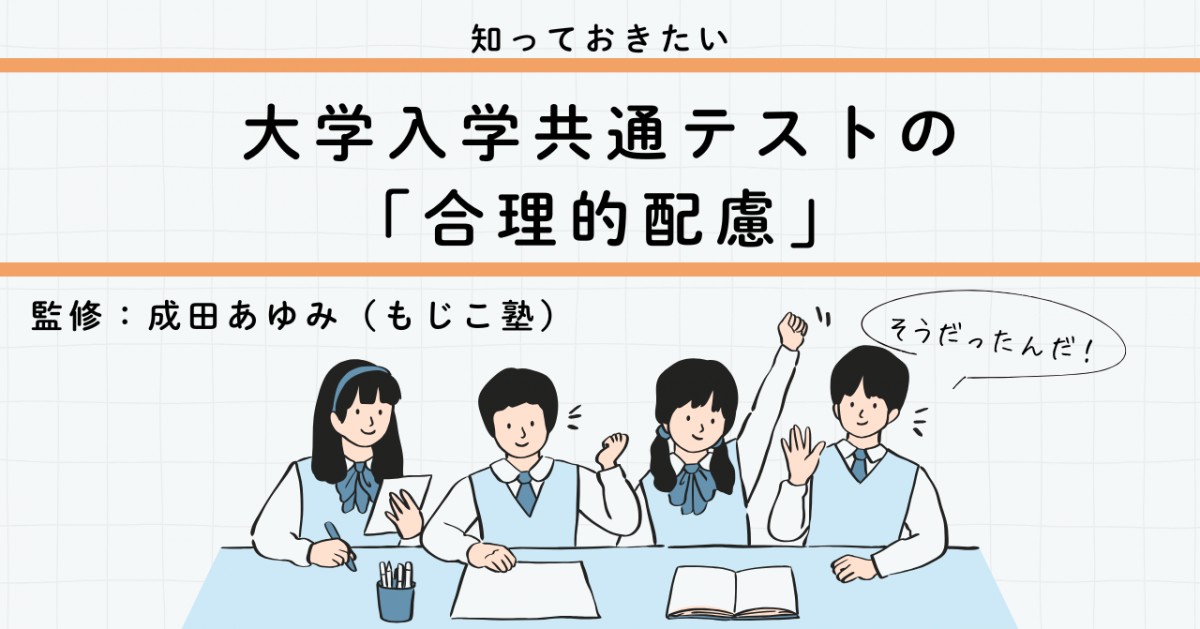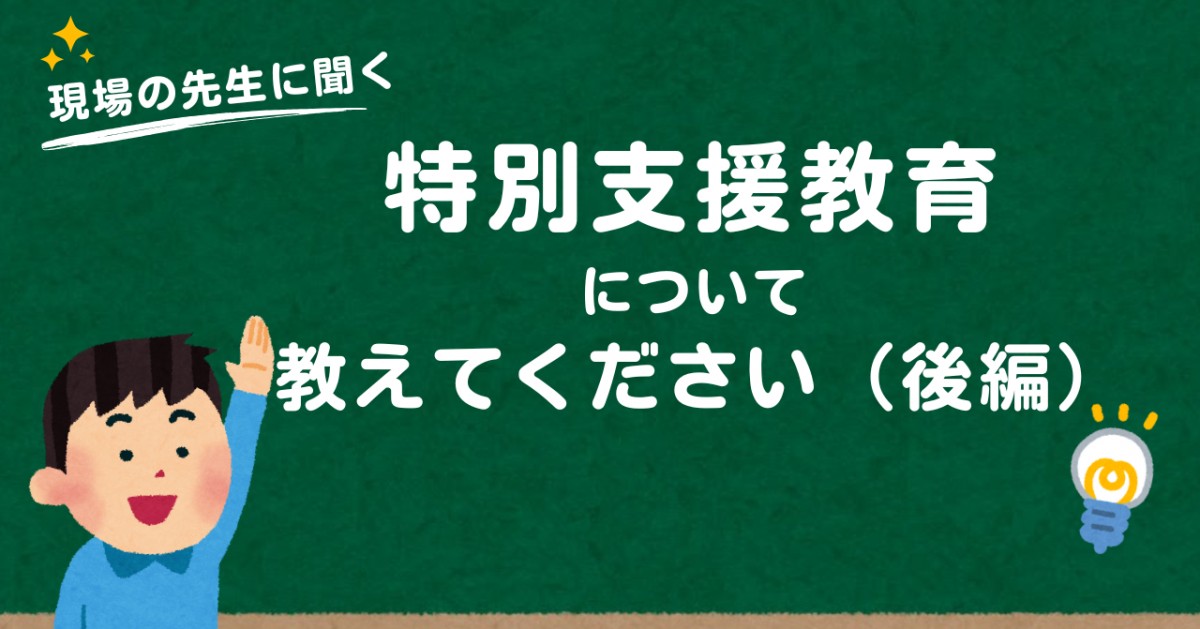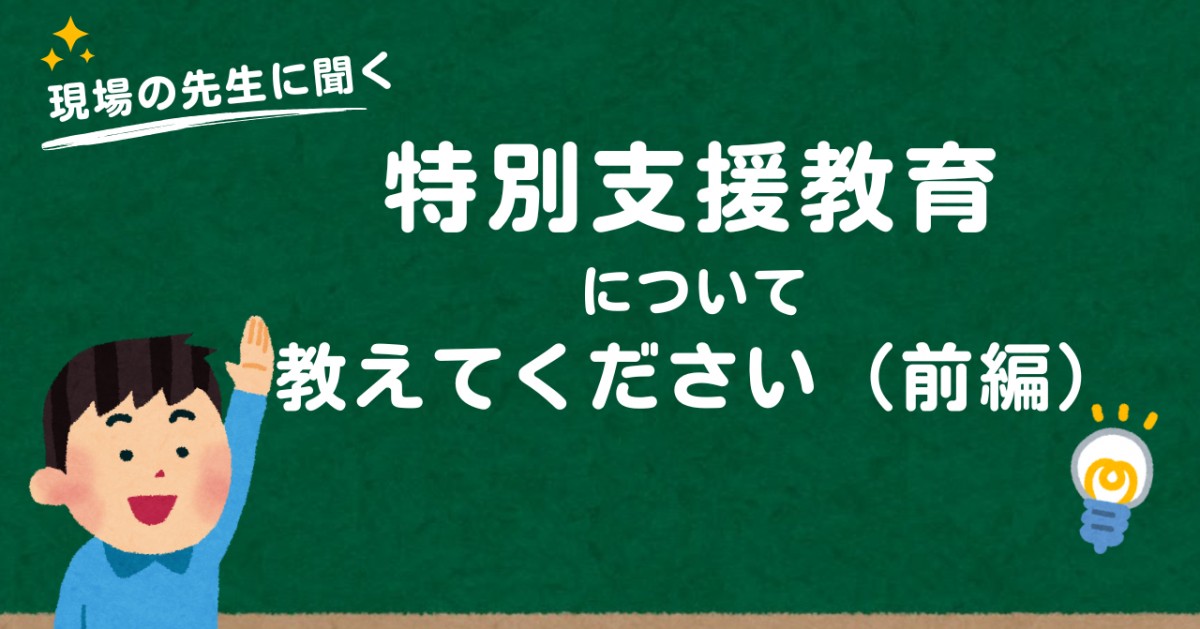「発達障害とは何か?」
黒坂真由子 講演書き起こし(前編)
「アーカイブ」では、発達障害関連の情報を発信しています。専門家からの情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験を記事にしています。
サポートメンバーの登録により、発達障害についての継続的な発信が可能になります。メンバーとしてのご登録をお願いいたします。メンバーシップは、無料、有料から選べます。概要について、詳しくはこちらをご覧ください。

●はじめに
講演のご依頼をいただきまして、本当にありがとうございます。正直、こんなにたくさんの方が集まってくださると思わなかったので、「発達障害に対して、興味を持ってくださっている方がこれだけいるんだな」と驚いているところです。1時間ぐらいお話しさせていただきます。私自身はライターなので、医学的なことや、診療に関することにお答えすることはできないのですが、取材を通して専門家や当事者の方に教えていただいたことをお伝えしたいと思います。よろしくお願い致します。
私には、発達障害、特に学習障害のある息子がおります。子どものことを知りたくて、発達障害について取材を始めたのがおよそ8年ほど前になります。当時は発達障害という言葉もそんなに広がっていなかったですし、私自身、子どもに何が起こっているのかわからなかったんですね。
息子が小学校1年生の漢字練習のときのことです。目の前にお手本があり、ただ写すだけなのに、それができない。「えっ、写すだけじゃん。ちゃんと見て」とか、「ちゃんとやって」と言って、そこでケンカになって、息子が泣いて、ということがありました。「なんかおかしいな……」と。そんなふうに、何も知らないところからのスタートでした。
●右利きの世界
「右利き左利き」の話をちょっと先にしたいと思います
アイスブレイクみたいな感じで、いやだったら手を挙げなくていいのですが、左利きの方、いらっしゃいますか? ちょっと少ない。両利きとか。おおー、いらっしゃる。左利きと同じくらいらっしゃいますね。左利きはだいた10%ぐらいといわれているのですが、国とか地域によって全然割合は違うそうです。 0%とかのところもあって、ちょっとおかしくないですか? おかしいですよね。本当はそんな差があるはずないと思うんですけど。ただ、日本でも「増えている」と思います。なぜなら、左利きを矯正されることが、今、少なくなっているからです。
発達障害の人も、すごく特性や個性が強い人と、まあそうでもない人も含めると、なんとなく左利きの人と同じぐらいいるんじゃないかと言われています。10人に1人となると、家族にいても親戚とかにいても、職場にいても全然おかしくないというか、いないことはないと思います。なので「左利きの人くらいいるんだなぁ」と思っていただければいいと思います。
例えば自分のお子さんやお孫さん、パートナーとか会社の人が発達障害であったとしても、左利きの人ぐらいの割合でいるわけだから、当たり前に発達障害の人がいるんだということです。それほど特別なことではないのです。
発達障害が左利きの人とイメージがすごく似てるなあと思うのは、左利きは昔は矯正されていたからです。私も左利きで矯正されました。字は右で書くのですが、包丁とかは左です。避けられることもありました。ある結婚式場で、給仕のバイトをしてたんですね。その時に「右手でやってくれ」と言われました。たまたまその日のチーフが、そういうお考えをお持ちの人でした。ちょっと皆さんも反対の手でお盆をもつことを想像してみてください。私の場合だと、右でお盆を持って、左でサーブすることはできるんですけど、反対はけっこう厳しい。右利きのみなさん、右手でお盆を持つの、厳しくないですか?
そして「左利きは縁起が悪い」みたいなことを言われました。その時は学生で素直だったので、とにかく言われた通りにしたんですけど、お盆を持って一歩踏み出したとたんに、ガシャンって全部落としちゃったんです。そうしたら「じゃあ君はもう左でいいよ」って言われました。
でもそれって、私の給仕する能力が、著しく足りなかったんでしょうか? 私のせいですか? 多分違うと思うんですよね。利き手じゃない方を使うように強制されたから、うまくできなかっただけなんです。他のバイトの日は、左手を使ってちゃんとできていたので。右手を矯正されるだけで、たちまち生きにくくなってしまうということがありました。
社会は基本、今も右利き用にできています。自動販売機のお金を入れるところも右だし、改札のピッとする場所も右にあります。今、スマートウォッチに定期を入れている人いますよね。右利きの人は左手に時計をはめるから、体をひねってタッチして、すごくやりにくそうですよね。左利きは常に、そんな感じです。
ただちょっと有利なこともあって。テニスとかバドミントンとかは有利です。例えば私の娘は競技カルタをしているのですが、左利きが相手だとやりにくいみたいです。いつも右利きの人相手に練習をしているからです。そんなふうに、左利きが有利なこともあります。だからなおさないでいいのであれば、できれば左利きの良さを生かして生活できたらいいですよね。何かですごく有利になる可能性もあるからです。
そんなことが、発達障害にもいえると思います。
だから発達障害を、「脳の左利き」みたいなふうに考えるといいのかもしれません。自分とはちょっとやり方が違うし、なんかうまくいってないようにも見えるけど、それは自分とはやり方とか違うからだと。考え方が違うからだと。
●「発達障害」とはなにか
これは日経ビジネスのオンライン版で2年ぐらい取材をして、その記事をまとめた本なのですが(『発達障害大全 −「脳の個性」について知りたいことすべて』)、ここに「脳の個性」と入れました。ただ、「個性」というには、今の段階では厳しいと感じることもあります。字が書きにくいとか、コミュニケーションを取るのが苦手とか、今の社会で行きにくい。「個性」という言葉で片付けるには、多分すごく辛いと思われる方もいると思います。なので、カッコ付きで「個性」という言い方をしています。
この本では、13人の方にインタビューをしているのですが、一番最初に「発達障害とは何か?」という質問を投げかけました。なぜかというと、私がそれを知りたかったからです。 発達障害と言われても、どういうものなのか見えないので、わからなかったんです。そうしたら専門家の方も「いや、それに答えるのが一番難しいんだよね」とおっしゃられて。なぜかというと、発達障害には診断基準はあるのですが、結局、発達障害と診断されるかどうかは、「本人が困難や障害を感じているかどうか」という「主観」によるからです。自分がどう思うかが重視されます。
診断基準の1つはここにあるのですけど(DSM-5-TR(*))。 お医者さんなどは、このような診断基準を参考にしています。ただ、たとえここに書かれている診断基準のすべての条件に当てはまったとしても、本人が困難を感じていなければ発達障害とは診断されません。
それがなかなかわかりにくいところです。
例えばですけど、漫画家のAさんと市役所で働くBさんがいたとします。AさんもBさんも落ち着きがなく、忘れ物が多い。でも、アイデアがすぐに浮かんで、けっこうパッと口に出したりしちゃう。AさんとBさんには、全く同じ症状があるとします。Aさんは漫画家なので、自宅で1人で働いています。だから落ち着きがなくても、何か忘れたとしても、「ああ、ここにあった」と、そんなに困ることはないわけです。ただ、Bさんは市役所でみんなと働くときに、思ったことをすぐ口にしてしまったり、今日の会議で必要なものをどこかに置いてきてしまったりすると、一緒に働いていくのが難しいと思われてしまう。本人もつらくなってくる。
Aさんは別に困ってないので、病院に行くことはありません。一方Bさんは、非常に働きにくい上に、周りの人との関係が悪くなってしまうなどの困りごとが生じてきます。本人は一生懸命やってるのに、「忘れ物ばかりして不注意だ」「真面目にやっていない」「ちゃんとしていない」などと言われて、評価が下がってしまう。そうして苦しくなって病院に行くと、診断が下りるということになります。
そうすると、このAさんとBさん、同じ症状なのに、Aさんは発達障害ではなく、Bさんは発達障害ということになります。
これが病気との大きな違いです。
つまり、本人が苦しいかどうか。ですから発達障害という言葉が広まったことで、例えば職場で「あの人、発達障害だよね」という話が出ることがあるかもしれませんが、でも本人がそう思ってなければ、発達障害ではありません。そもそも周りの人が判断することは、できないのです。AさんとBさんのように本当に同じ症状があっても、本人が困ることがなければ診断は下りないということです。
これは病気や怪我とのすごく大きな違いです。だから余計分かりにくいんですね。
「病気ではない」ということですが、例えばコロナもそうですけど、ウイルスが検出されたら、コロナだとなります。発達障害には、そういう客観的な診断がないわけです。糖尿病は、自覚症状がないといわれます。自覚症状がないから、「いや、糖尿病じゃありません」と言っても、検査をしてある数値が出れば「糖尿病ですね」となります。ここには自覚症状の有無は入ってこないわけです。
そうなってくると要は、「自分がこの社会の中で、生きやすいかどうか」というところに関わってくるということです。
だから、左利きと一緒ですよね。社会が右利き用にできていて、みんなが「左利きをやめてください」と言うと、非常に生きにくくなります。左利きが0%の社会というのは、きっとそういう場所なのだと思います。そうではなく、「いろんな人がいるよね」「まあ、一緒にやっていきましょう」みたいな社会になってくると、発達障害と診断されるために病院に行く人もいなくなり、結果として発達障害の人は減るわけです。
*)DSM-5-TR:アメリカ精神医学会が作成する公式の精神疾患診断・統計マニュアルの第5版の最新版。精神障害診断のガイドラインとして用いる診断的分類表。DSMはDiagnostic and Statistical Manual of Mental Disordersの略称。
●言葉の整理
いろいろな言葉が出てくるので、わかりにくくなってくるかもしれませんので、まず3つの名前だけお話をしておきます。
実は発達障害というのは、総称なんですね。 1つの障害とか1つの病気ではありません。総称っていうのを例えると、「色」みたいなものです。「色」という色はないですよね。青とか赤とか黄色とかがあるように、発達障害も、「発達障害」という病気ではないんですね。色に赤、青、黄色とたくさんの種類があるように、発達障害にもいろいろな種類があります。
話題に取り上げられるのがこの3つです。
・注意欠如多動症(ADHD)Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
・自閉スペクトラム症(ASD)Autism Spectrum Disorder
・限局性学習症(学習障害、LD、SLD) Specific Learning Disorder
ADHD(注意欠如多動症)という言葉を聞いたことがある方、いらっしゃいますか? 多いですね。自閉スペクトラム症、ASDという言葉を聞いたことがある方? ありますね。あと限局性学習症、学習障害というのがもう1つ。学習障害を知ってる方、ちょっと減りますよね。やはりあまり知られてないんですね。
この他にも、昔で言うと不器用みたいなことに対しても、名前が付いていたりします(発達性協調運動症、DCD(*))。ですから今、不器用だからとか、運動ができないとかで、学校で責められることがないのは、このような苦手なことの1つとされているからです。今日は、ADHD、ASD、学習障害の3つを主にお話しします。
*)発達性協調運動症:協調運動が苦手な障害。「不器用」「運動が苦手」といわれることが多い。DCD(Developmental Coordination Disorder)。
●発達障害を色に例えると
さきほど、発達障害は「色」のような総称だ、というお話をしましたが、発達障害の中で、ADHDやASDや学習障害が、それぞれの色にあたると考えてもらえばいいと思います。 だから、重なる場合もある。 ADHDとASDが重なる場合もある。学習障害が重なる場合もある。先生によってはもう大体重なるという方もいますし、まだまだ分かってない部分が多いです。
ただ「脳の個性」と考えると、重なっていても普通かな、という気もします。色々な得意、不得意が人それぞれ違うからです。色と同じで、けっこう濃淡があります。ですから、例えばASDと学習障害が重なっていたとしても、どちらの個性が強く出るかによって、対応の方法がけっこう変わってきたりします。
ADHDは、いわゆる多動・不注意だとか衝動性の問題といわれていて、けっこう目立ちやすい。例えば小学校で走り回っちゃう男の子とかが、ADHDじゃないかといわれたりします。ただ、実際小学生男子は、元気なのが普通なので、違うことも多いです。ですから、この本に掲載した文部科学省の統計でも、小学生男子のADHDのリスクがものすごく高く出ているのですが、だんだん成長とともにその数は減っていきます。この理由の一つは、医師の診断ベースではなく、学校の先生が「ADHDのようだ」と判断した人数が計上されていることがあります。元気な小学生の男の子は、ADHDだと思われてしまうという傾向があるのだと思います。
ASD、自閉スペクトラム症は、コミュニケーションの苦手さとこだわりの問題。得意なことや好きなことがあって、それにすごく集中してしまうところがあります。最近言われているのは、コミュニケーションを練習し、得意になる方がけっこういらっしゃるということです。ですからそういう方に、例えばお医者さんが「コミュニケーションは苦手ですか?」と聞くと、「いや、私は得意です。 僕は得意です」と返ってくるのだけれど、「疲れませんか?」と聞くと「すごく疲れます」と返ってくる。そういう方は、パターン化してコミュニケーションを覚えるなど、ものすごい努力をしてコミュニケーションに参加しているわけです。ですからその辺りも、ちょっと見ていかないといけないといわれています。ものすごく努力をしている可能性があるということです。
学習障害は、読む、書く、計算する、推論するなどに苦手がある状態です。ある特定の分野が、著しく苦手ということです。学習障害について説明する場合、知能との関連についても話すのですが、学習障害は「知能的には問題はないけれど、書けない」のように、何か特定のことについて、それだけができない状態です。
今日はこの3つをなんとなく頭に入れていただければなと思います。
●知能との関係
知能との関係について、もう少しお話しします。