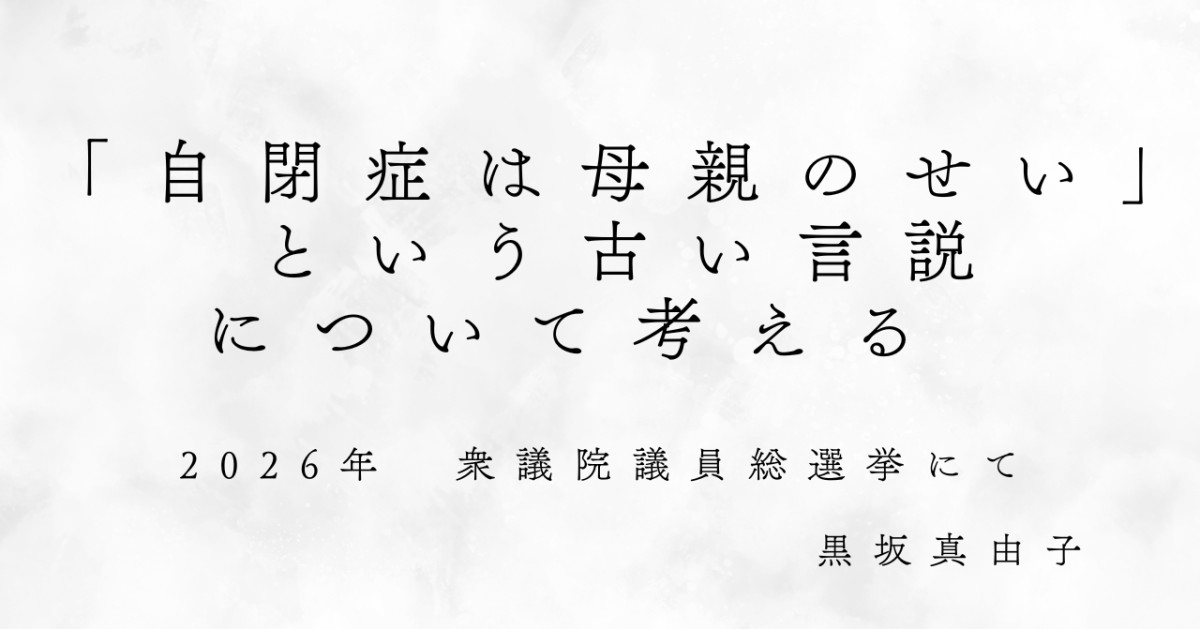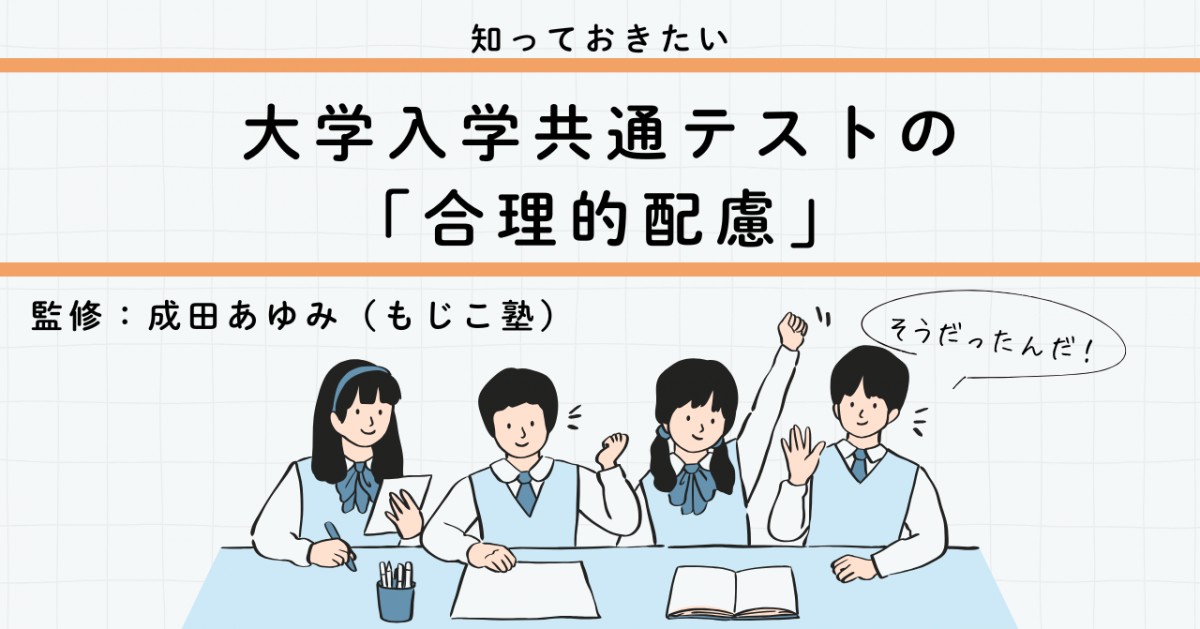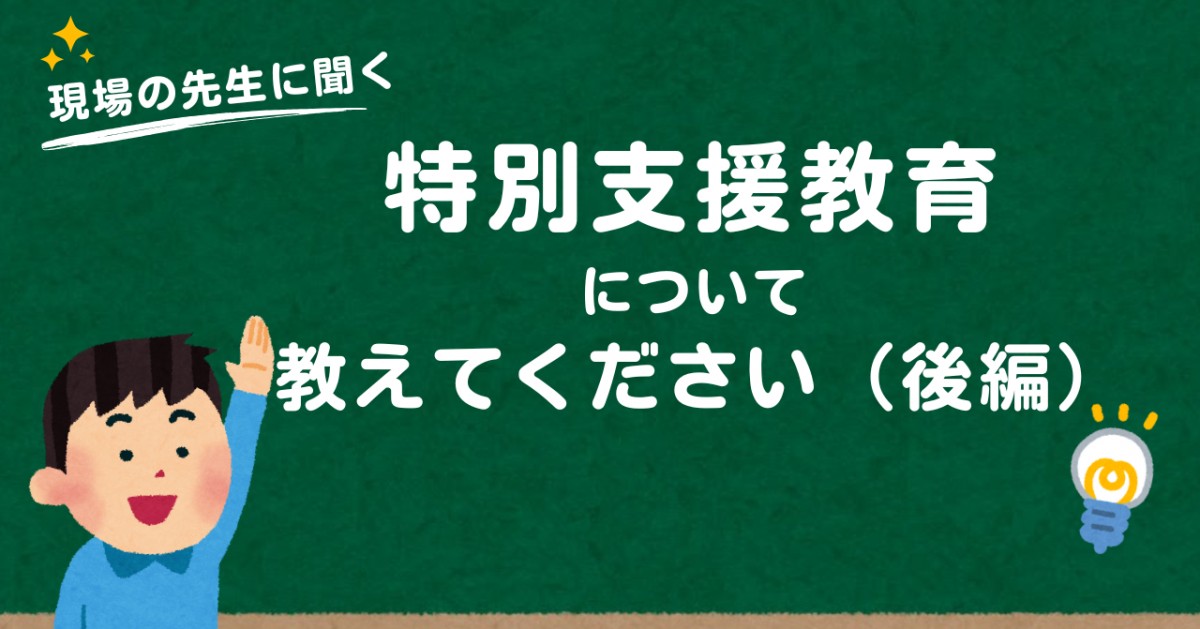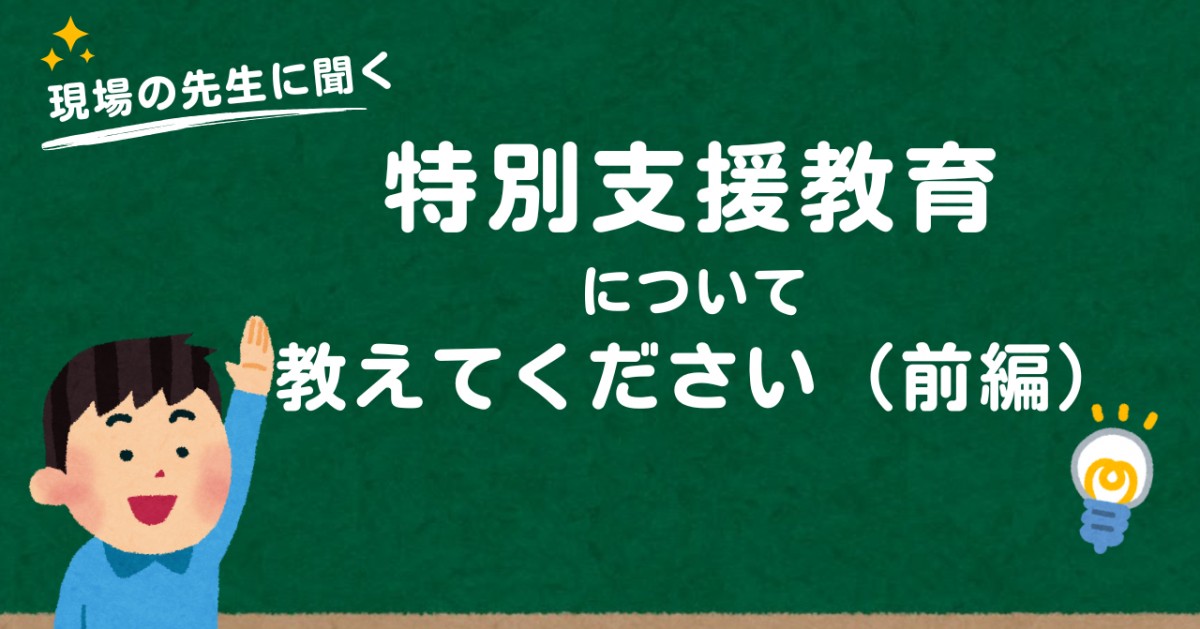自閉スペクトラム症の世界を伝える 翻訳者 上杉隼人 の仕事(前編)
「アーカイブ」では、発達障害関連の情報を発信しています。専門家からの情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験を記事にしています。
サポートメンバーの登録により、発達障害についての継続的な発信が可能になります。メンバーとしてのご登録をお願いいたします。メンバーシップは、無料、有料から選べます。概要について、詳しくはこちらをご覧ください。
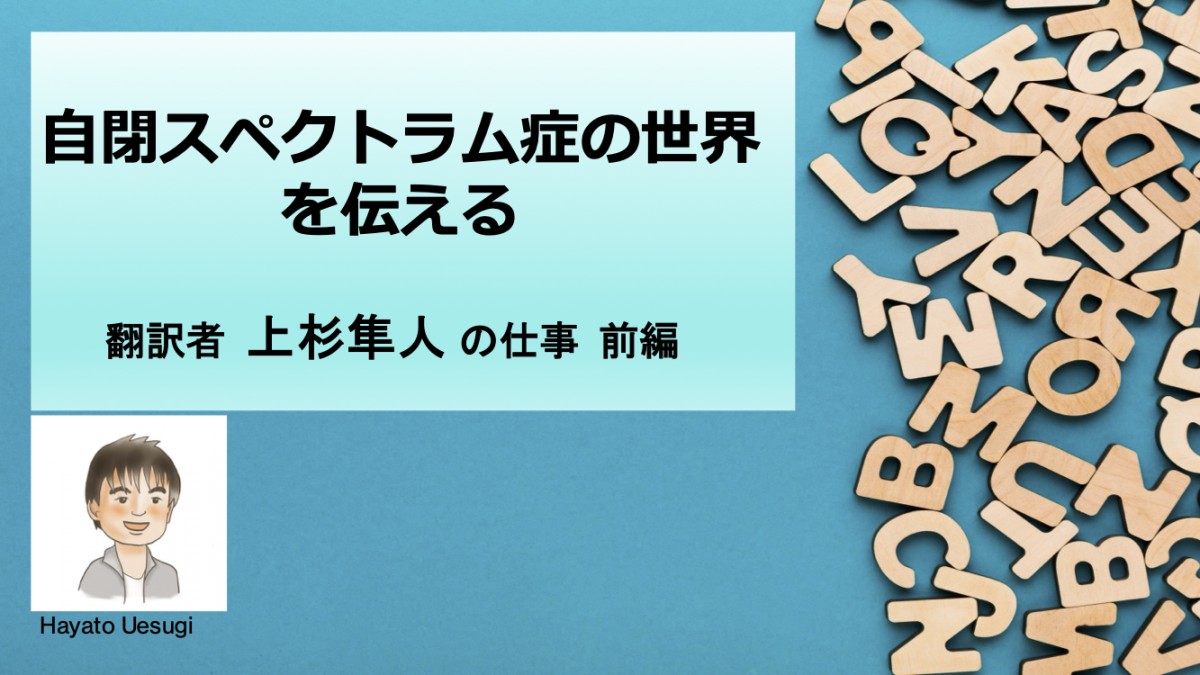
●プロフィール
上杉隼人 Hayato Uesugi
翻訳者(英日、日英)、編集者、英文ライター、通訳、英語・翻訳講師。早稲田大学教育学部英語英文学科卒業、同専攻科(現在の大学院の前身)修了。訳書にマーク・トウェーン『ハックルベリー・フィンの冒険』(上下、講談社青い鳥文庫)のほか、ヴィクトリア・ロイド=バーロウ『鳥の心臓の夏』(朝日新聞出版)、ジョリー・フレミング『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方』(文藝春秋)、フランク・ロイド・ライト『浮世絵のみかた』、ダグラス・ウォーク『マーベル・コミックのすべて』(作品社)、ムスタファ・スレイマン『THE COMING WAVE AIを封じ込めよ DeepMind創業者の警告』(日本経済新聞社/日経BP)、「スター・ウォーズ」シリーズ、『アベンジャーズ エンドゲーム』『アベンジャーズ インフィニティ・ウォー』(いずれも講談社)、マイク・バーフィールド『ようこそ!おしゃべり科学博物館』(すばる舎)、ミネルヴァ・シーゲル『ディズニーヴィランズ タロット』(河出書房新社)、など多数(日英翻訳を入れて100冊以上)。
●「持ち込み」が難しい翻訳の世界
−− 翻訳家として、普段どのような本を担当されているのでしょうか?
上杉隼人氏(以下、上杉):これまで100冊以上担当してきましたが、まだまだ翻訳したい本はたくさんあります。もちろんベストセラー本を訳してみたいですし、担当したい小説もあります。ただそういった本は、僕に限らずやりたい人は多いですよね。ですから自分は、部数的には厳しくても、十分な印税にならなくても、いい本を出したい、と思っています。
−− 『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方』や『鳥の心臓の夏』など、自閉スペクトラム症(以下、自閉症)関連の本を手掛けています。
上杉:『「普通」ってなんなのかな』も『鳥の心臓の夏』も、出版社の編集者さんから声がかかったものです。これは本当にありがたかった。なぜなら僕自身、自閉症関連の海外の本は常にチェックしていて、出版社の編集者さんに「この本はどうですか?」と提案してきたからです。でも、なかなか実現しないんですね。「それはいい本ですよね。でも、こんな本がありますから、先にこちらを……」という話にいつもなってしまって。それでスパイダーマンなど、気がつくとマーベル本の翻訳の仕事を受けることになったりしているんです。
−− 上杉さんは、マーベル本の翻訳者としても有名です。この8月にはダグラス・ウォーク氏の『マーベル・コミックのすべて』(作品社)という、ずいぶん厚い本を翻訳されています。
上杉:そうなんです。そうなってしまって。ですから一度も持ち込みに成功したことがないんですよ。
−− 100冊以上担当していて、一度もですか?
上杉:一度もないです。ただ『「普通」ってなんなのかな』だけは、本当に運が良くって。この本、実はある出版社に持ち込んだものなのです。
−− 自閉症の青年が、この世界をどう見ているかを語ってくれる話です。私も大好きな本で、すでにこちらの記事でも紹介しています。著者のジョリー・フレミングさんと上杉さんとのインタビューも拝見しました。ジョリーさんは、ホームスクーリングで学んだのちに高校へ進学。大学卒業後は、2つの奨学金を得て、2019年9月にはイギリスの名門オックスフォード大学で修士号を修めています。その後、母校のサウスカロライナ大学にて、地理学と海洋科学の学士号を取得し、現在は研究者、教育家として活動されています。
上杉:編集者もこの本を気に入ってくれて、「やってみましょう」ということになりました。それですぐに、版権の確認をしてもらったのです。すると、もう他の出版社に版権がおさえられていたのです。それが文藝春秋(文春)でした。
僕は文春に知り合いがいたのでかけあってみたところ、「じゃあ、レジュメとサンプル訳をつくってみてください。それで判断しますから」と言われて。その頃すでに70冊くらいは訳していたのですが、トライアルからのスタートでした。
−− それだけ実績があっても、トライアルからなのですね。
上杉:下訳の人を使っている偉い翻訳家の先生だったら、誰かにレジュメとサンプル訳を作ってもらうのかもしれませんが、僕は全部自分で訳していますから常にトライアルからなんです。この本はどうしても翻訳したかった本なので、すごく緊張したのを覚えています。かなり気合を入れてレジュメとサンプル訳を作り、その知り合いの編集者に提出しました。
それから半年、何の連絡もなくて。ほとんどあきらめつつ、思い切って編集者に連絡しました。そうしたら、「ああ、ごめんなさい。翻訳担当に出し忘れていました」と。
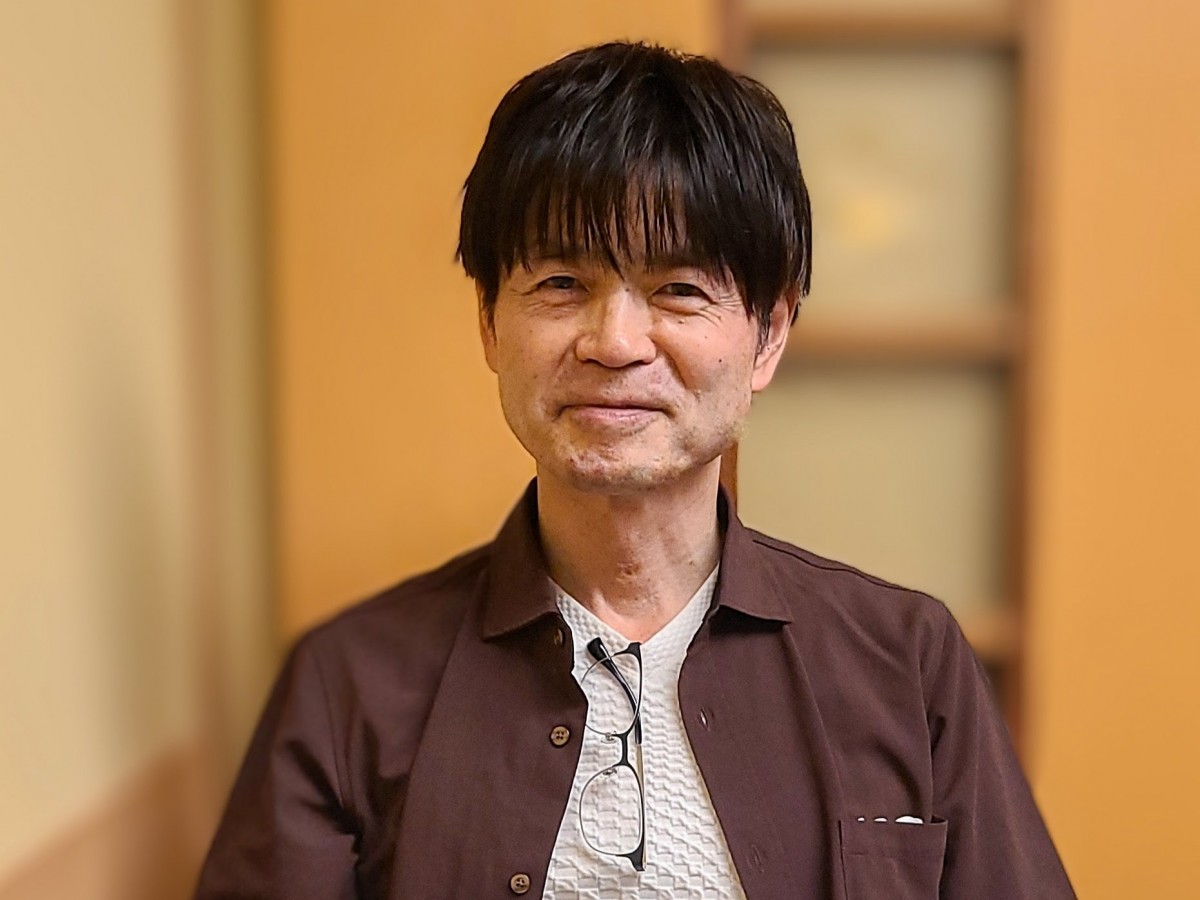
上杉隼人氏(本人提供)
−− 翻訳担当にレジュメとサンプル訳が届いて、OKとなったのですね。ところで、どのようにこの本に出合ったのですか?
上杉:インターネットで見つけて、これは面白そうだなと思って。アメリカの場合、出版社がすごく大事なんです。インディペンデント(独立系)のとこから出ていると、ちょっとつかみようがないんです。宗教絡みのものがすごく多いというのも理由です。この本は、Simon & Schuster(サイモン&シュスター)というすごく大きな出版社から出ていたので、まずその点で安心できたということがあります。結果的に文春が版権を取っていたくらいなので、その予想は間違っていなかったということです。
ただ、版権を取った後、翻訳者が決まっていなかったことを考えると、もしかすると自閉症の問題に興味がある翻訳者が周囲にいなかったのかもしれません。脳の問題が出てくるので、訳すのもすごく難しいんです。
−− そうですね。脳関連のことを説明するのは、日本語でもかなり難しいですから。翻訳はさらに大変だと思います。
上杉:「自閉症の著者が書いたものだからわからない」と言われるのがすごく嫌だったので、自分が責任を持って訳そうと思いました。新たに注をつけたところもあります。何より、本に記された著者ジョリーの声が聴こえてこないといけない。まずは原文をしっかり読み込んで、「ジョリーはどんな風景を見ていたのか」ということを理解しようと思いました。
そしてこの翻訳に使用したのが、まさしく「音声」です。ジョリーが読んでいるわけではないのですが、オーディオブックで聴いてみると、強調したいところがよくわかるのです。最初は発音の表記を確認するために聞いていたのですが、ジョリーが本当に言いたいことがなんとなくわかってくるようになりました。「ああ、ここはそういうことだったのか」と、ハッと気づくこともありました。
−− 翻訳するために、原著を読むだけでなくオーディオブックも活用したというのは、本当に細やかな作業だと思います。
上杉:実は、「朗読者が失敗している部分」が大事なんですよ。
−− 読み間違えているところが大事なのですか?
上杉:そうなんです。「文字通り読めなかった部分」というのがあるんですね。その間違いが実は大事で、「普通はそういうふうに言う」のを、この著者は「ここではこういうふうに書いている」ことがわかるからです。
−− 著者は「あえてそう書いている」ということがわかるのですね。
上杉:そういう可能性があるということです。もちろん結果としてであって、「あえて」かどうかはわかりませんが。通常使われている表現と違っている、すごく難しい表現になっているなど、朗読の間違いから見つけられることがあるんです。
−− みんなが使っている四字熟語の、例えば後半をあえて変えたりしていることがありますけど、それに気づかずに正しい読み方でさっと読んでしまうことはあると思います。でもそこに、著者の意図やユーモアが隠れている可能性はありそうです。
上杉:ですから、翻訳にもリスニングはすごく大事なんです。
●「普通」について考える
−− 訳していて、特に面白いと思った部分はどこですか?
上杉:ジョリーの苦労がなんとなく微笑ましいんですね。その苦しみ方が、大変失礼なんだけど「あなた、いいやつだねえ」としみじみ感じられる。例えばゴミを出すときに、家のゴミを集めてから一気に出すのではなく、ゴミを収集箱に入れてゴミ箱を空にして、また家に戻ってゴミを集めて収集箱に入れて……、ということをするわけです。
僕はボランディアで、自閉症の人たちのサポートをしているのですが、ジョリーみたいな人がいっぱいいるんです。「やっぱりみんな一緒なんだな」とよく思います。その人達の「普通」をみていると、いわゆる「定型発達者」とされる我々は単に我々の世界で「普通」なだけなのではないかと思う。ジョリー達はこちらの世界において「普通ではない」とされてしまうだけの話だと思うのです。ジョリーが我々の世界で「普通じゃない」とされるのは、我々が「そう思っているだけ」のことなんですよ。でも、ちょっと違うけれど、実はそれがすごく微笑ましかったりして受け止められることもある。そう思えた瞬間が、すごくよかったですね。それはやはり、自閉症の人達をサポートしてきたからだと思います。
−− 自閉症の人の文化に触れて、馴染んでいた部分があるということですね。
上杉:両方の文化を見ていますから。こちらの文化にも「普通」でない人はいるし。それに自閉症の人の中にいると、「あなたはすごくピュアですごく気持ちのいい人だから、ちょっと汚れたこっちの文化に来ない方がいいんじゃないかな?」と思ってしまう瞬間が何度もありました(笑)。
−− ああ、嘘がつけなかったり、正直だったりということですよね。
上杉:そうなんですよ。その違いが見られたのがよかったですね。
●ジョリーからのメッセージ
−− 特に印象に残っているフレーズはありますか?
上杉:原著の最後の文章には衝撃を受けました。
歴史的遺産を思わせる樹木には、なれないかもしれない。でも、思い出に残る、楽しい花にはなれる。だから悲しんでいる人や、気持ちが落ち着かない人がいれば、行って助けてあげたい。忘れられてしまうかもしれないけど、何かを伝える花にはなれる。
−− 宮沢賢治みたいですね。
上杉:そうなんです。地理学と海洋地形学の研究者としての考えに、自閉症をもって生きる自分の考え方が重なってきている部分だと思います。
だって、僕らはみんな地球で生活している。このことを真剣に考えれば、地球上の全生態系の中で、みんな常に支えあわなくちゃいけない。僕ら人間は酸素も作り出せない。僕はひとりじゃ生きられない。みんなもひとりじゃ生きられない。誰もひとりじゃ生きられない。
こんなふうに、本は終わります。これを言葉にできたことは、ジョリーにとってすごくよかったことなのではないかと思うんですね。
−− 日本語版には、原著の後に上杉さんが行ったジョリーさんへのインタビュー「ジョリーは今」が「日本語版附章」としてついています。インタビュー時の言葉で、印象に残っているものはありますか?