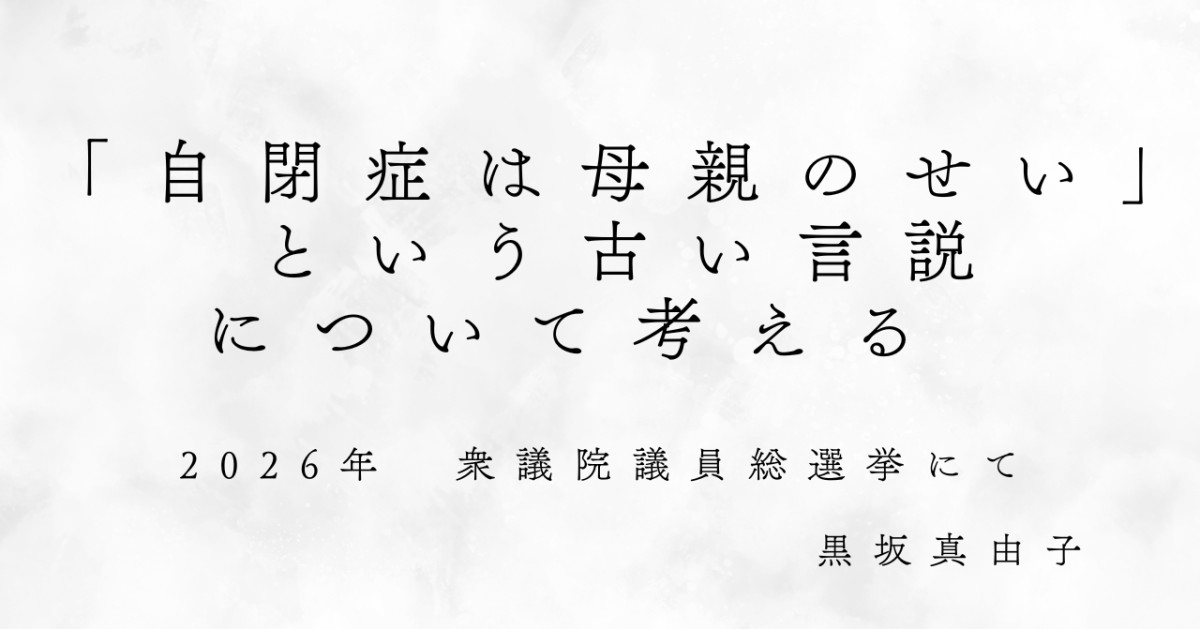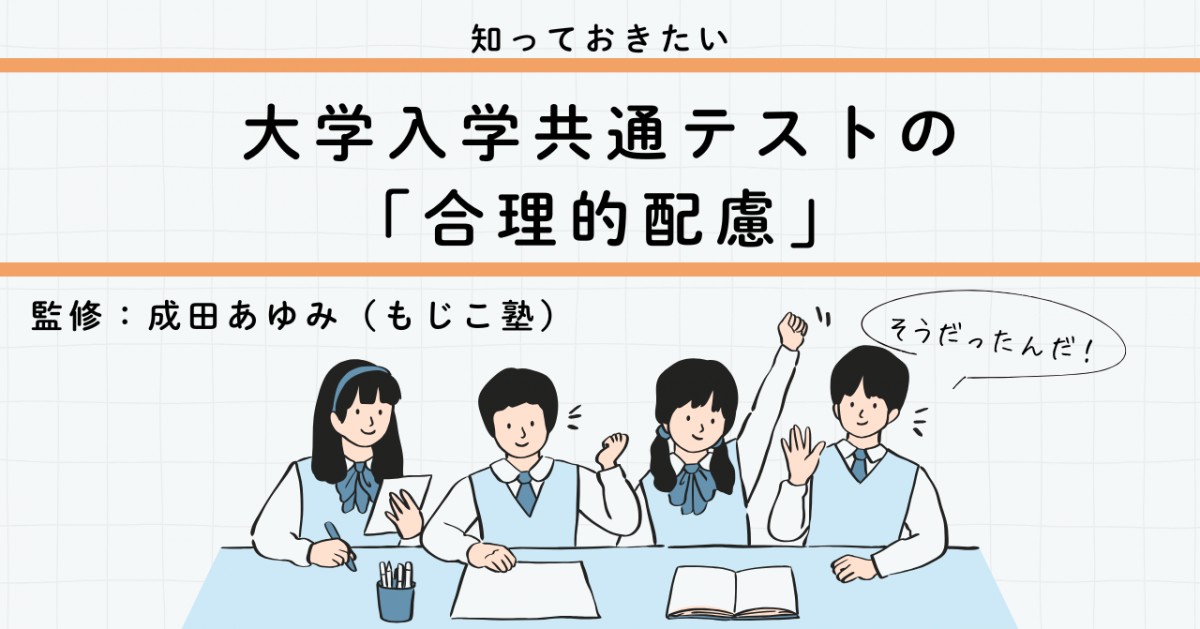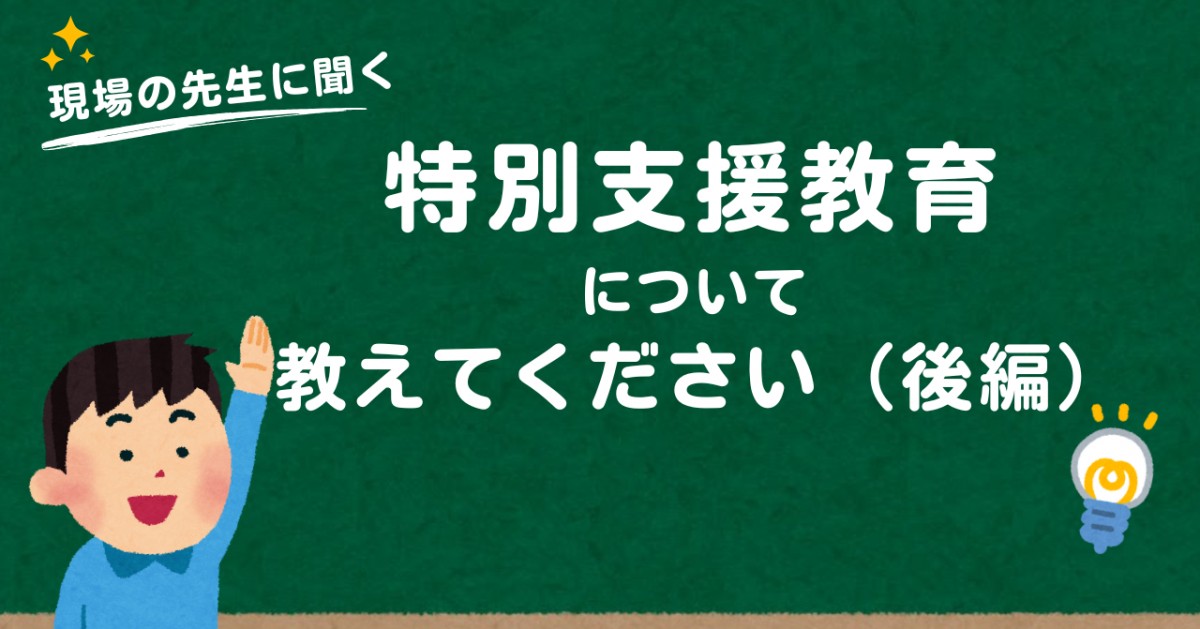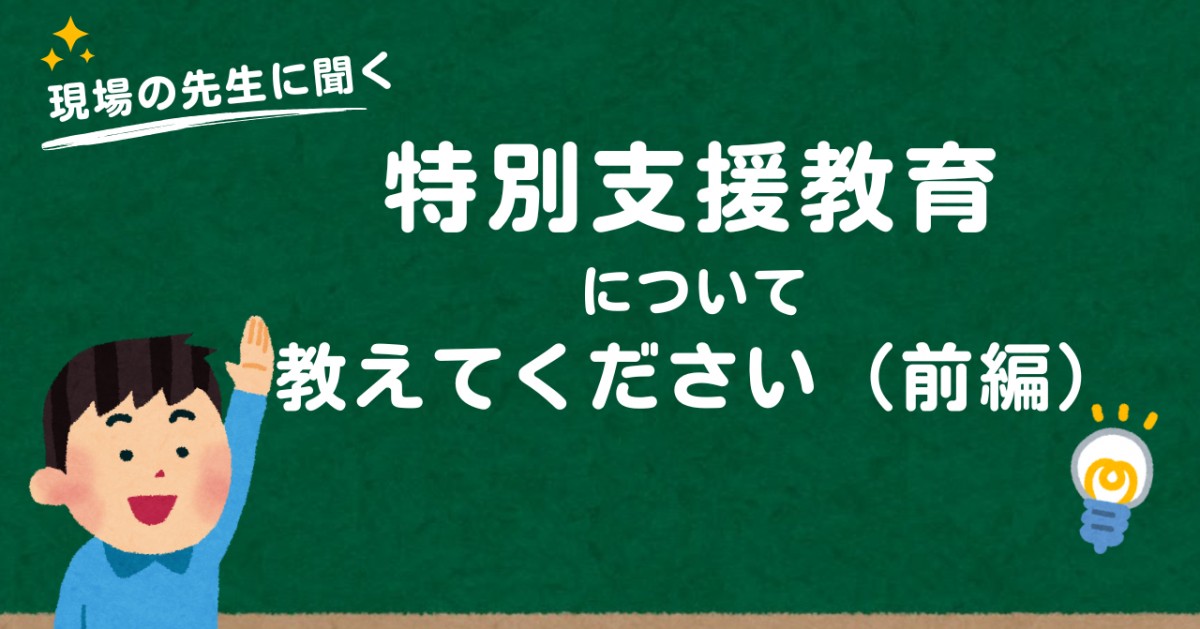「発達障害とはなにか?」
黒坂真由子 講演書き起こし(後編)
「アーカイブ」では、発達障害関連の情報を発信しています。専門家からの情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験を記事にしています。
サポートメンバーの登録により、発達障害についての継続的な発信が可能になります。メンバーとしてのご登録をお願いいたします。メンバーシップは、無料、有料から選べます。概要について、詳しくはこちらをご覧ください。

●「当たり前」に気がつく
学校だけではありませんが、私たちの社会には、たくさんの「当たり前」があります。
その「当たり前」に、苦労なく順応していける人向けに、この社会はつくられています。その「当たり前」は、もしかすると発達障害を持った人には「当たり前」じゃないかもしれません。
漫画家の沖田×華さんは、忘れ物が多く、ランドセルも忘れてしまう。なぜかというと、ランドセルを背負う動作がコートを着る動作に似ているからです。コートを着ると忘れてしまう。でもそれは、本当にわざとじゃないのです。忘れ物をしたくないから、毎日全教科をランドセルに入れている子もいました。すごく重いのに。本当に、がんばっているのです。
親御さんの工夫としては、例えば消しゴム何個も持たせるなど、あらゆるところに入れておく。なくして怒るのではなく、なくす前提で揃えておくのです。ADHDで「忘れ物が多い」ということがわかっているなら、準備ができる。筆箱を2個持たせている親御さんもいました。周りがその子の苦手を知り、特に小学生の間は、失敗してしまいそうなことに備えておくのがよいと思います。もちろん成長するにつれて、だんだんと自分でできるようにしていかなければいけませんが。
ASDの子で集団行動や、みなと同じことをするのが苦手なら、それを知っておく。子どもが休み時間に1人で本を読んでいると、みんなと一緒に遊ばないと、親は不安になったりしますよね。でも、本人がそれが落ち着くのであれば、それでいいと考える。
あと、学校でも、職場でも、「暗黙の了解」を書いて貼っておくといいと思います。外資系企業では、何でも書いてあるといいます。それはいろいろな文化を持った人が一緒に働くために、「この国の人の当たり前が、他の国の人の当たり前ではない」ということが前提になっているからです。
日本は「当たり前」で進んでいくことが多いので、それに気付くのが難しい。ですから、例えば本棚があったら「この本は教室で読んでください」と書いて貼っておく。持って帰って忘れてしまったり、ということを防ぐためです。
●早めのサポートが必要な学習障害
もし、教育関係の方がいらしたら、お伝えしたいことがあります。学習障害についてです。今、小学校はかなり大変ですよね。ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字それに加えて、英語が小学校で必修になりましたから、アルファベットの大文字、小文字を覚えなくてはなりません。しかもローマ字は、英語と読み方違いますから混乱します。
学習障害があっても、音と文字が「1:1」の対応なら、覚えやすい人はいます。ですから、ひらがなやカタカナは、大丈夫な人が多い。なぜかというと「あ」というひらがなの音は「ア」という音だけだからです。「1:1」の対応です。
でも、漢字は違います。恐ろしいほど読み方がありますし、訓読みと音読みまであります。英語圏では「発達性読み書き障害」のことをディスレクシア(*)と言いますが、読み書きが苦手な子どもは多のです。なぜかというと、つづりと発音が一致していないからです。数字の「1」を表すoneですが、そのまま読んだら「オネ」ですが、正しいのは「ワン」ですよね。こんな風に英語では、綴りと発音が違うことが多いのです。例えばイタリア語の「1」はunoですが、そのまま「ウノ」と読めます。そういう言語の方が、ディスレクシアの率は低いのです。
綴りと音が一致しないと、非常に負荷が高いんですね。それが自然にできている皆さんは気づかないかもしれませんが、ひとたびそれが苦手となると、学校の勉強はかなりきつくなります。学習障害の子は、クラスに3人ほどいるといわれてます。読み書きが苦手な子は、クラスに3人くらいる。でもほとんど見つかっていない。
もしかすると、ひらがなが読めるために見つからない、ということがあるかもしれません。でも、漢字をたくさん書くようになるときつくなってくる。そういうことがあるわけです。学習障害の子だけではなく、外国ルーツの子も日本語を習うのは難しいことがあると思うので、小学校1年生で苦手な子を見つけ出すことをしていただきたいと思います。つくば市など、すでに始めている地域もあります。ぜひ、お願いしたいです。
読み書きは勉強だけではなく、情報を取るためにも必要です。読み書きが苦手だと、集団生活にも影響が及びます。「次、何をするか」ということがパッと見てわかる子と、じっくり読まないとわからない、もしくはじっくり読むことができない子だと、集団生活に影響が出てくるはずです。ぜひ小学校1年生のときに、読み書きの苦手な子を見つけてサポートしてあげてほしいと思います。多分それは、財政的にもプラスだと思います。その後の特別支援教育のコストが減ると思います。ここはぜひお願いいたします。
*)ディスレクシア:発達性読み書き障害とほぼ同義で使われる言葉。発達性読み書き障害は診断名だが、ディスレクシアの場合、「読むことに困難がある」という症状を指すのに使われることもある。
*)特別支援教育:障害のある子どもの自立や社会参加を目指して行われる教育。特別支援学校や特別支援学級、通級による指導などで行われる。障害の状態や発達に応じて学習面・生活面の指導や支援を行う。
●みんな、すごくがんばっている
子どもはすごくがんばっています。大人もがんばっていると思います。
漫画家の沖田×華さんが、こう言ってました。
毎日できないことだらけですけど、たまに「できる日」があるんです。でも、誰にも評価してもらえない。私にとっては、「今日は何も忘れ物しなかった」というのが、すごい「奇跡の日」なんですけど、周りのみんなにとってはそれが当たり前なので。