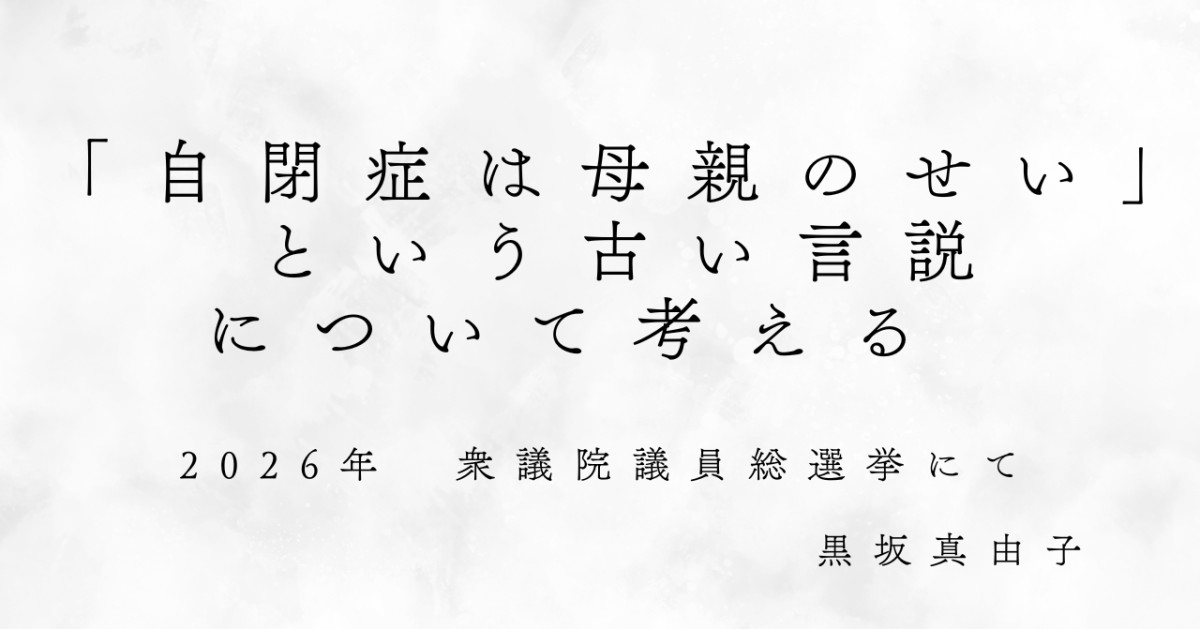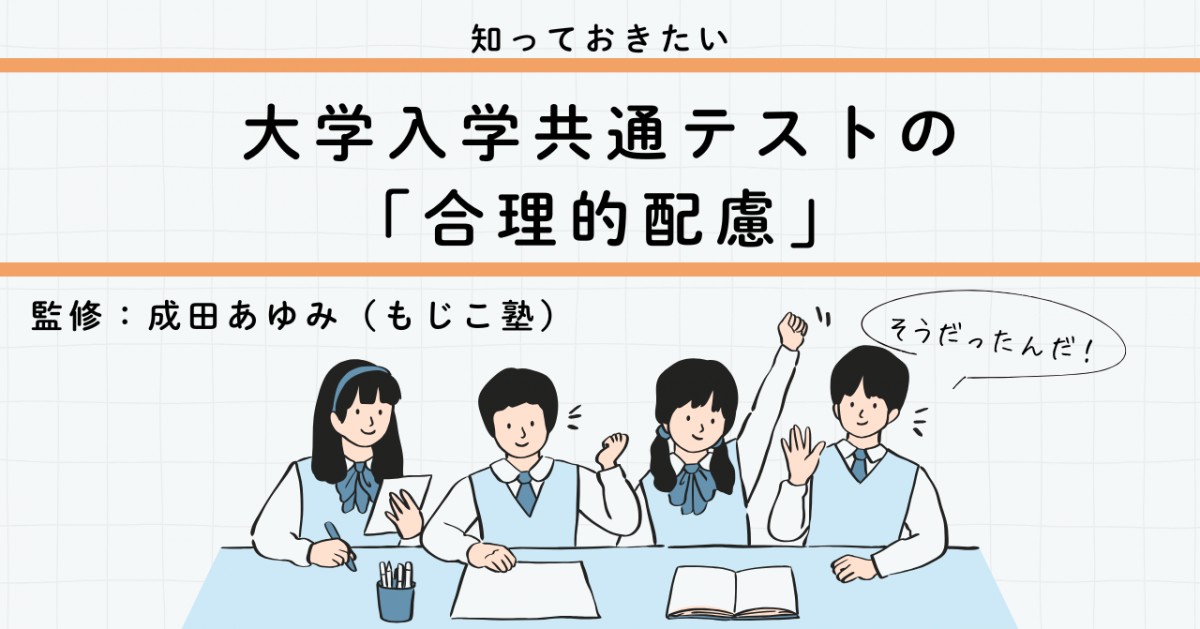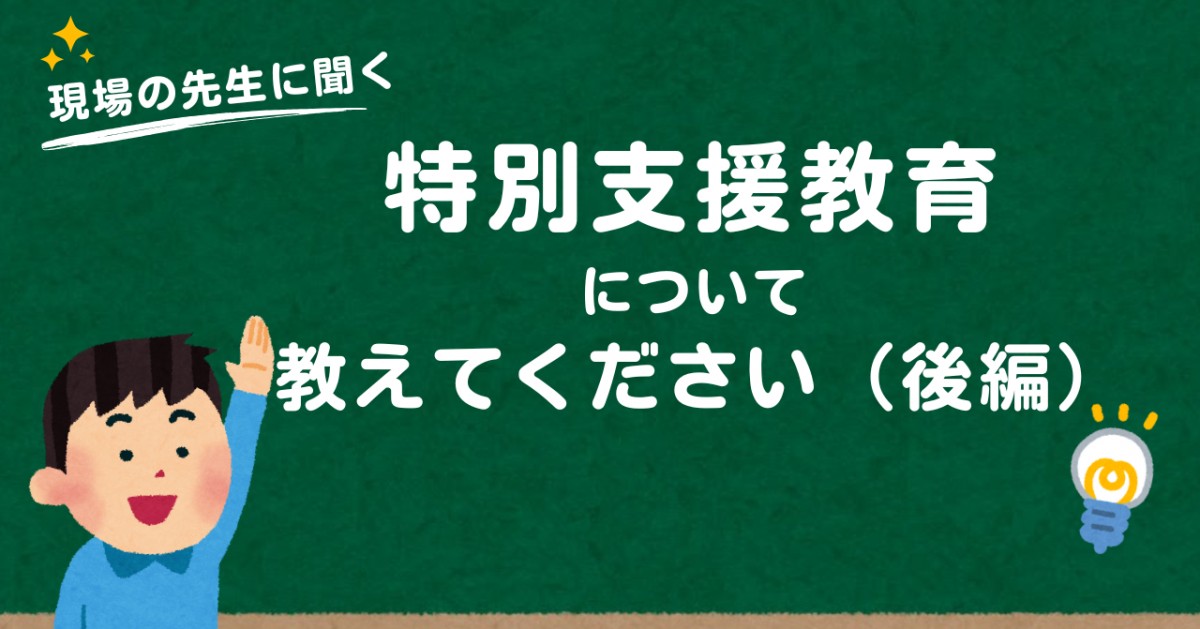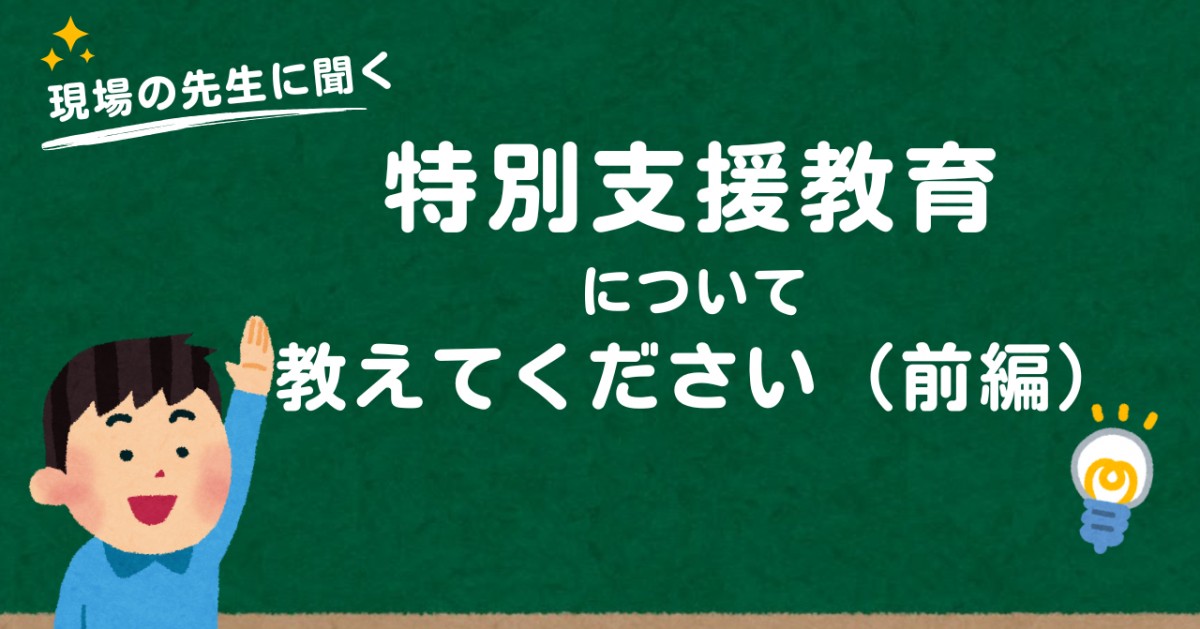詳しく知りたい「算数障害」算数障害と他の発達障害との重なり 第2回(全3回)
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を発信・蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(いつでも解約可能です)。発達障害について発信を続けていくために、ご登録での応援をお願いいたします。
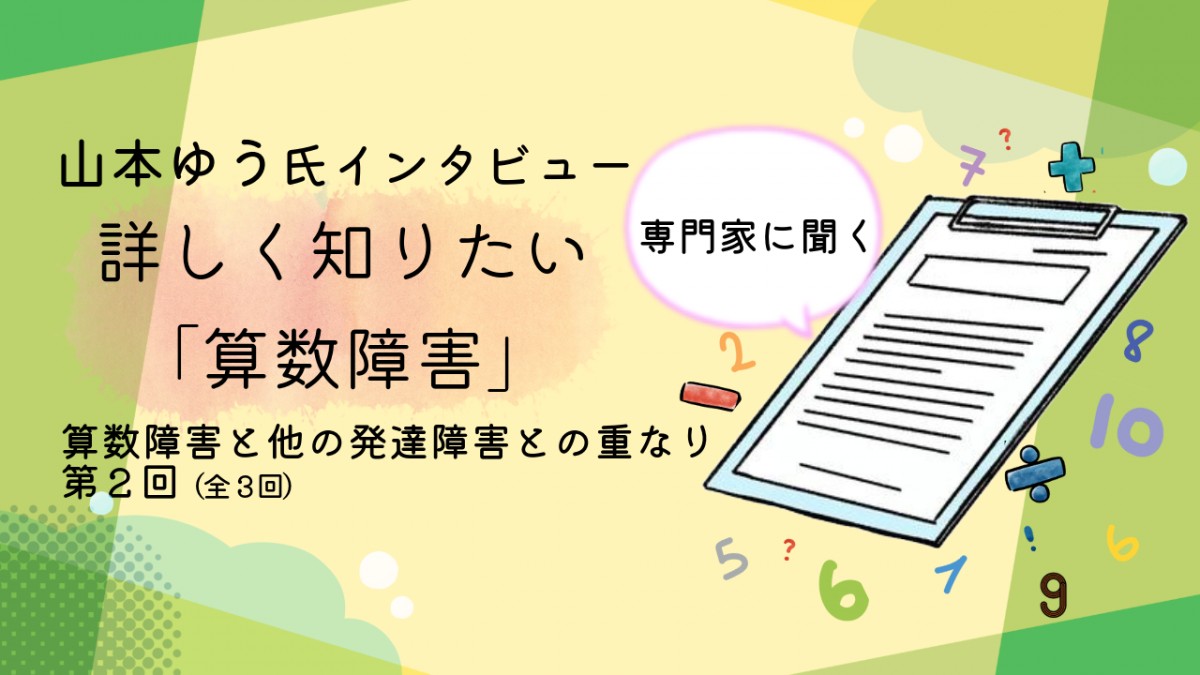
「算数障害」について考える第2回目は、他の発達障害との重なりや判定に必要なテストについて、質問をしました。(★第1回のインタビュー「算数障害とは、何か?」はこちら)
プロフィール
山本ゆう(やまもと ゆう)
松本大学教育学部専任講師。博士(障害科学)。特別支援教育士SV(スーパーバイザー)。公認心理師。小学校教員、医療機関や教育委員会での心理職を経て現職。算数障害のある子どもの臨床に携わりながらその解明および指導方法の研究を専門としている。
ADHDやASDなどとの重なりはあるか?
−− ADHD(注意欠如多動症)やASD(自閉スペクトラム症)と、重なりはあるのでしょうか?
山本ゆう先生(以下、山本):あります。違った形で、算数の問題が現れることが多いですね。ADHDでの子どもというのは、じっくり注意を向けて、集中して学習課題に取り組むことが苦手です。ですから、算数に取り組む以前に、先生の説明が頭に入ってこない、ということがあります。
ASDの子どもであれば、想像力の問題があります。例えば文章題で「鳥が5羽います。3羽飛んでいきました。今、何羽いますか?」という問題に、「5羽」と答えてしまいます。なぜなら、「鳥は飛んでいってしまっただけで、世界のどこかにその鳥は存在しているから」と言うのです。
「クッキーが5枚あります。3枚食べました。何枚残っていますか?」という問題も、同じです。食べてクッキーがなくなった、という感覚がなく、「お腹にあるから変わらない」「食べて満足度が高まり、むしろ増えた」と言うような子もいます。
−− 特性によって、算数のつまずき方が違うのですね。
山本:ですから、何かにつまずいているときに、その原因をしっかりと見極める必要があります。例えば、九九ができない場合、それは算数障害によるものなのか、ADHDによる注意の問題による習熟不足のせいなのか、それとも4(シ)と7(シチ)が聞き分けにくいなど音韻認識(*1)の問題なのかなど、さまざまな原因が考えられるからです。
発達性読み書き障害との重なりは?
−− では、発達性読み書き障害との重なりでは、算数においてどのような問題が発生するのでしょうか?
山本:まず、読字障害の問題があれば、そこをクリアしなければ子ども一人で算数の問題に入っていくことができません。算数の問題を考えるために、読んであげるということが必要になります。
−− 文章題が解けないのは、そもそも文章を読めていない、という可能性があるのですね。
山本:不注意や衝動性で文章を読めていないという問題もありますし、国語的な読解力の問題もあります。そして、文章題の場面を文章から数量をともなってイメージできていない場合は算数障害の問題になります。
もし、読み上げることで算数の問題が解けるのであれば、算数の学習に問題はありませんが、読みの指導をしていかなければなりません。
−− 算数障害と一口に言っても、どこでつまずいているのかを見ないと、ぴったりしたサポートは、できないということがわかります。
算数障害の判定に、必要なテスト
−− 算数障害の判定には、どのようなテストが必要になりますか?
山本:まずは知的な遅れがないかを見る必要があります。知的発達症(*2)や境界知能(*3)でないかの確認が必要です。IQでいえば、全体的な知的発達の水準が85以上あるかが目安となります。
この記事は無料で続きを読めます
- WISC-VとKABC-Ⅱの検査の違い
- 『算数障害スクリーニング検査 適切な学習指導は正確なアセスメントから』
すでに登録された方はこちら