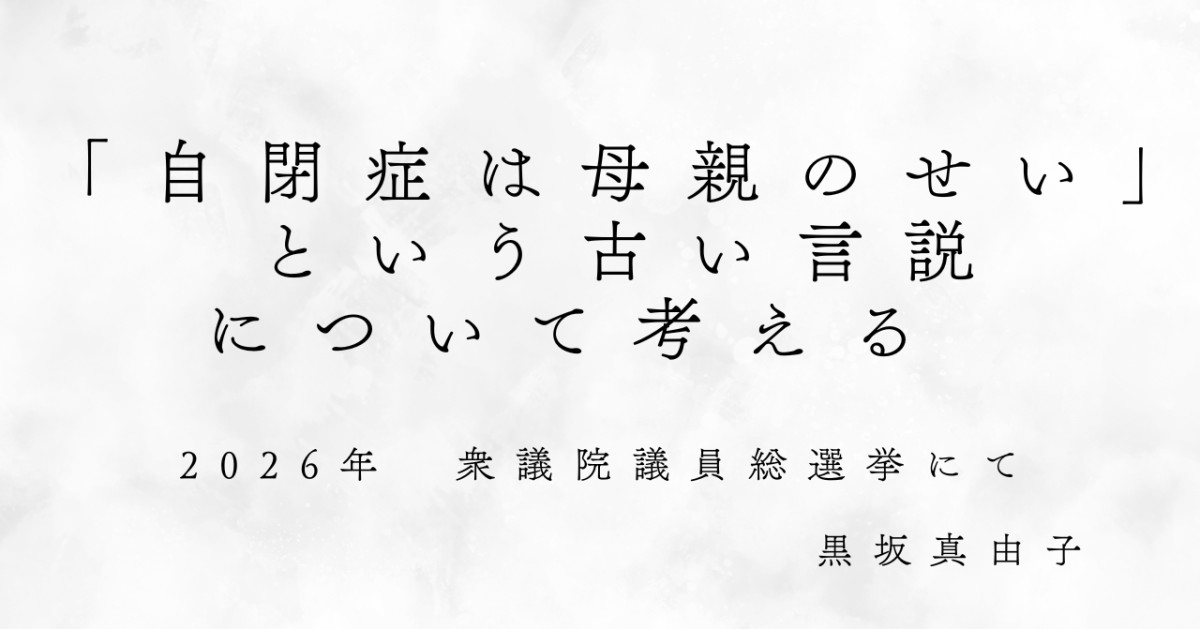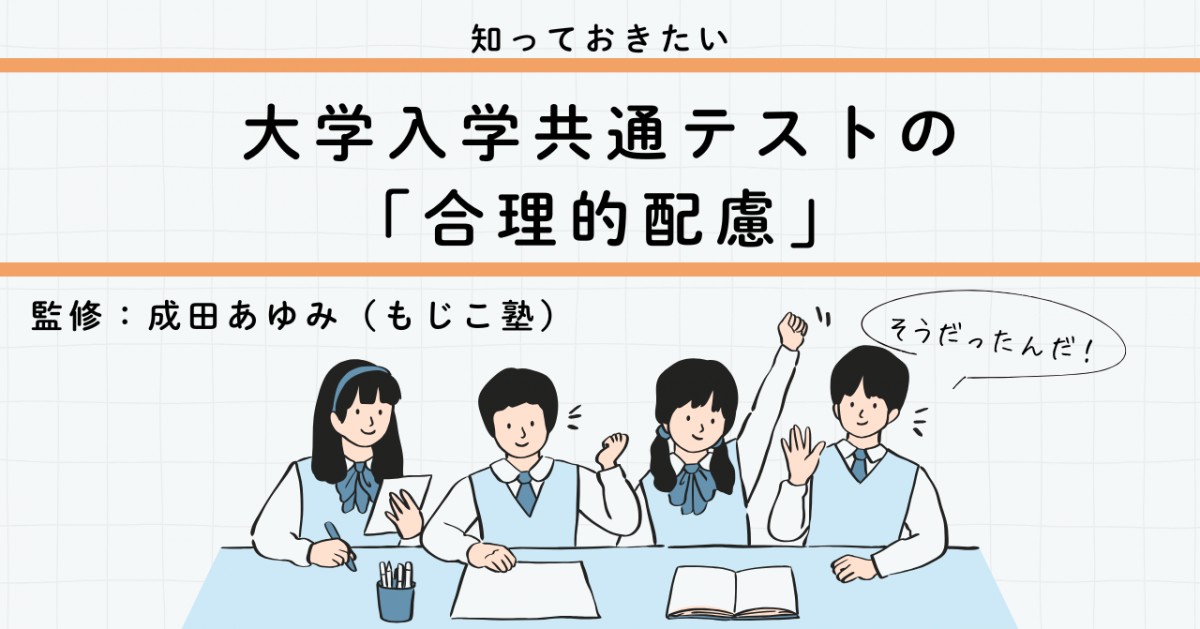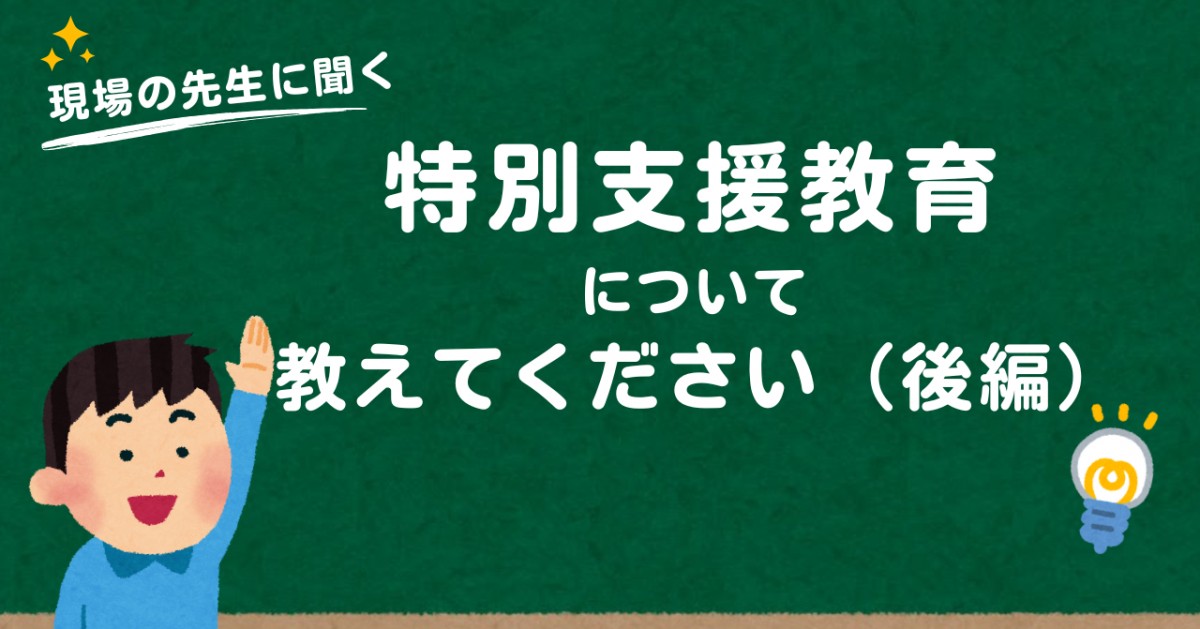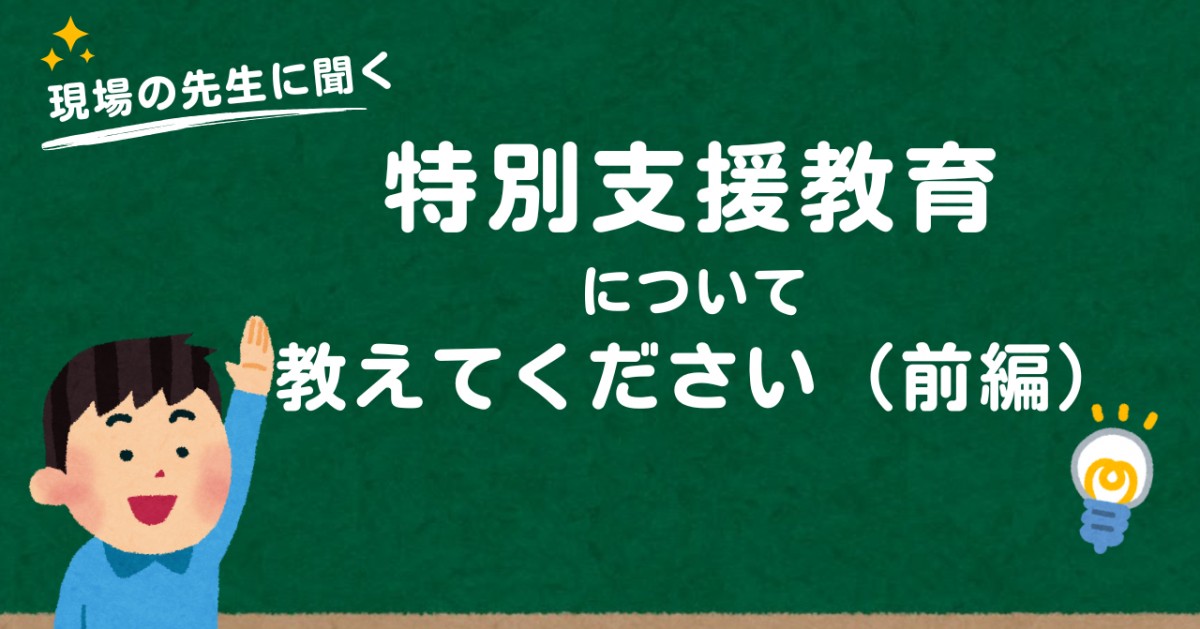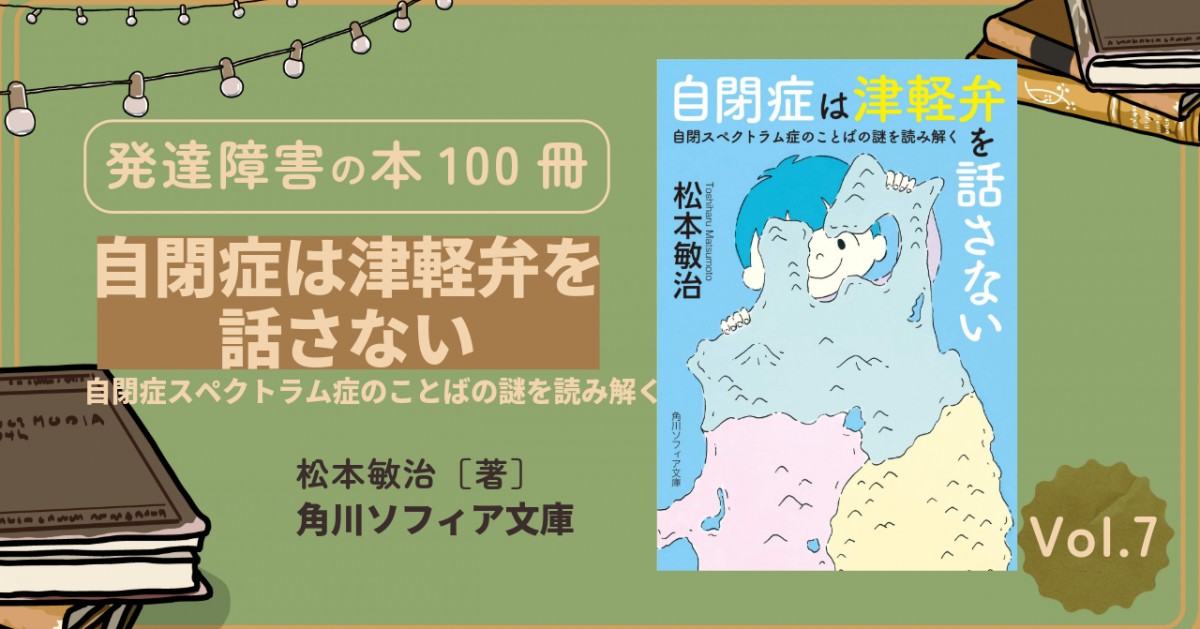詳しく知りたい「算数障害」
算数障害とは何か? 第1回(全3回)
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(いつでも解約可能です)。
発達障害について発信を続けていくために、ご登録での応援をお願いいたします。
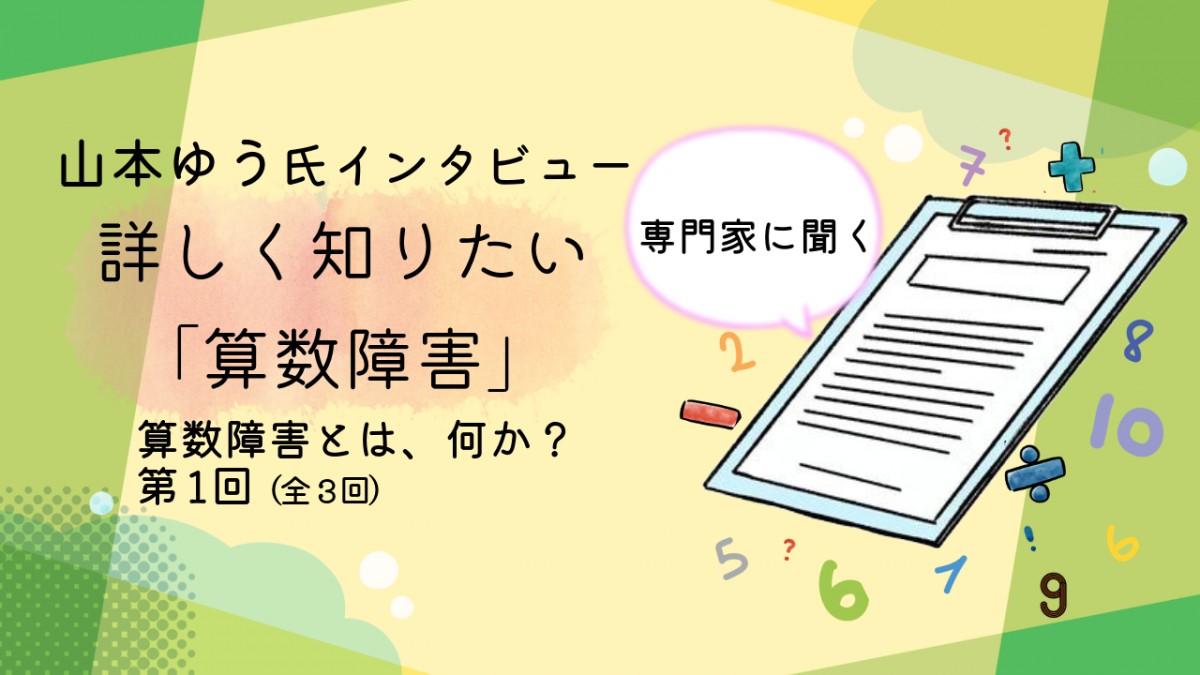
プロフィール
山本ゆう(やまもと ゆう)
松本大学教育学部専任講師。博士(障害科学)。特別支援教育士SV(スーパーバイザー)。公認心理師。小学校教員、医療機関や教育委員会での心理職を経て現職。算数障害のある子どもの臨床に携わりながらその解明および指導方法の研究を専門としている。
算数障害とは、どのような障害なのか?
−− 「算数障害」については、まだあまり知られていないと思います。どのような障害なのでしょうか?
山本ゆう氏(以下、山本):知的な発達に遅れはないのに、認知能力の特性ために、算数の学習に困難が生じるものです。
−− それはいわゆる、「学習障害」とは違うのですか?
山本:学習障害の一つのタイプですね。算数の学習につまずきが起きている学習障害と考えていただければいいと思います。
−− 学習障害に含まれるのですね。算数障害という名前ですが、これは通称みたいなものでしょうか?
山本:そうです。アメリカの診断基準、DSM-5(-TR)(*1)では、限局性学習症の中の一つのタイプとして「算数の困難を伴うもの」というようになっています。ドクターは、この疾病分類を使って診断名をつけるので、診断ではそのように記載されることになります。
国際的な疾病分類である「ICD-10やICD-11(*2)」では、「発達性学習症 算数不全を伴うもの」となっています。
−− では、算数障害という言い方は、教育的な定義になるのでしょうか?
山本:研究的な用語あるいは通称というところになります。もともとは、後天的な脳の損傷によって、計算ができなくなってしまった失算から、計算障害の研究が始まりました。その中で、後天的な脳損傷があるわけではないのに、同じように計算でつまずく子どもがいるということが発見されて、「発達性算数障害」として、研究が進んできているという経緯があります。発達性ディスカルキュリア(Developmental Dyscalculia;DD)と呼ぶ方もいます。
−− 脳についての発見というのは、事故から、ということがありますね。算数障害もそうであったということは、初めて知りました。つまり、なんらかのアクシデントがあれば、突然計算ができなくなってしまうということが、自分にもあるかもしれない、ということですね。
そのように考えると、算数障害というのは脳のある特定の部位の機能の損傷であるとか、特定の部位からの連絡機能が失われていることで生じるのでしょうか。脳の一箇所、もしくは複数箇所に、問題が起きているということですか?
山本:そこがスタートだったのですが、今はそこまで単純なことではないと考えられています。fMRIなど(*3)、脳機能の働きを特定していくための科学技術が進んだことで、算数障害の人の脳機能の研究はずいぶんと進みました。そして算数の学習は、脳のほぼ全領域を使っていることがわかってきたのです。脳のどこかの部位が損なわれると、算数のどこかの場面でつまずくという可能性が見えてきているのです。
−−なるほど。当初は「この部分が損なわれたから、計算ができなくなった」と考えられていたのが、「算数の学習は脳全体を使うから、脳のあらゆる部位の損傷で、算数障害が生じる可能性があるとわかってきた」ということですね。
山本:非常に簡単な計算ということに特定すれば、ある程度の範囲で推定されてきていますが、広い意味での算数の学習ということでいえば、大規模な脳ネットワーク間の相互作用によって解決されると考えられています。それだけ算数の学習は複雑であるということにもなります。
−− 親が算数障害をざっくりと捉えるとしたら、「なんらかの脳機能の問題」というふうに考えればいいということでしょうか?
山本:そうですね。「算数の学習に取り組むときの脳機能が上手く働かない」ということです。
算数障害の割合は?
−− 算数障害の人は、どのくらいるのでしょうか?
山本:海外の報告になりますが、5%(*4)から7%といわれています。日本では文部科学省が調査をしていて、計算や推論に困難がある子が小中学生で3.4%だとしています(*5)。3.4%から7%と考えると、40人クラスに1人〜3人くらいですね。
−− 結構多いですね。
山本:そう思われますか? 「思ったより少ない」という反応をされる方も多いんです。特に学校の先生は、「算数につまずいている子はクラスにもっとたくさんいる」というイメージを持っているからです。ですからその子たち全員が算数障害じゃないんだ、ということに驚かれることがあるのです。
−−ということとは、算数が苦手な子は多いけど、障害のある子はその中の一部ということなのですね。
山本:はい。算数に困難がある子は、大きく3つに分けられます。
・学習障害としての算数障害
・境界知能
・算数不安症
全般的な知的発達に遅れはないのに、認知能力の特性、アンバランスによって起きるのが算数障害です。一方、全体的な知的発達によって遅れが出るのが知的発達症(*6)や境界知能児(*7)となります。こういった問題がありながら、それに気づかれず、適切な支援を受けられなかったために算数の教科学習に対する心理的・身体的な問題が生じているものが算数不安症となります。
−− 算数不安症は、二次障害(*8)と考えていいですか?
山本:はい、そうなります。
−− では、「単に算数が苦手な子」は、この分類の中には入らないのですね。
山本:ただ、単に苦手なように周りからは見えているけれども、境界知能のお子さんや算数障害のお子さんがいるんですね。あとは他の発達の特徴です。ASD(自閉スペクトラム症)や、ADHD(注意欠如多動症)の特性によって、算数の学習につまずきが起きてる子もいます。また、算数の学習は複雑なので算数が苦手と思う子も多いでしょうね。
−− 息子が読み書きに苦手がある学習障害なのですが、小学生の頃は、数字の「0と6」や「4と9」の書き分けがうまくできませんでした。長い文章題も読むことで苦労するので、結果的に点数が出ない。他の特性によって、算数が苦手になることはありそうです。
山本:「0、6」の数字を見間違えたり書き間違えたりすることは、不注意の問題や、視覚認知、目と手の協応の問題などから起こる算数の困難だった、と考えられますね。しかし、6個のものを見て「0個」だと認識しているようなことになると、数量と数字が結びついていないので、算数障害の問題ということになります。
計算以前の「基礎的な問題」とは何か
−− 算数障害の中で、「計算が苦手」「数字の理解が苦手」「推論が苦手」など、人によって苦手な部分は違うのでしょうか?
山本:どこかの苦手な部分で困難に気づく、ということがスタートになります。多くは計算のつまずきで気づきます。ただし、計算につまずくというのは、計算以前のもっと基礎的な段階でのつまずきによって起こっているということがあります。算数というのは、系統的な学習ですから、最も基礎的なことでつまずくと、それ以降の学習もうまくいかないからです。
−− 「もっと基礎的」というのは、どういうことでしょうか?
山本:例えば、「2」という数は、視覚的なシンボルである数字の「2」と、聴覚的な音としての数詞の「に」と、具体物という意味で、成り立っています。この三つが結びつくということが、第一ステップです。
数字
数詞
具体物
→これら3つが結びついていると、2という数を理解しているということになる
ここにつまずくと、数字はただの意味のないシンボルになってしまいます。
−− なるほど。数字も漢字のように意味を持っているということですね。例えば、「卵」という漢字を「たまご・ラン」と読み、「たまご」という意味がある、というようなことですね。
卵:視覚シンボル(文字)
たまご・ラン:音(読み)
実在としてのたまご:具体物
そうなると「シンボルに意味がある」ということが、わからないということですか?