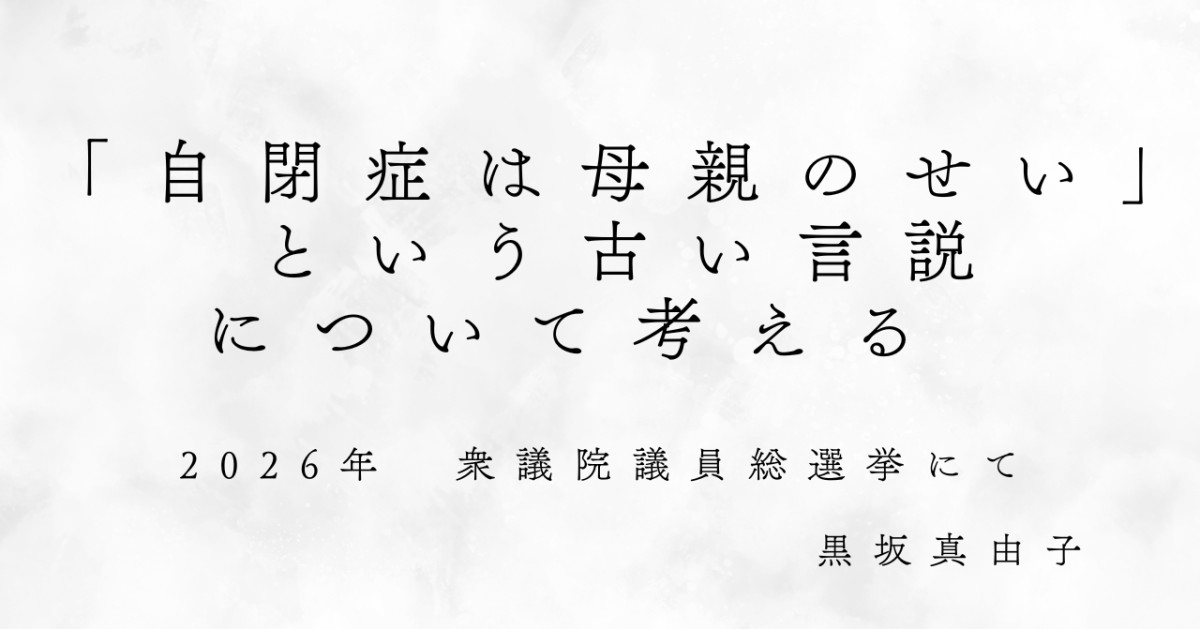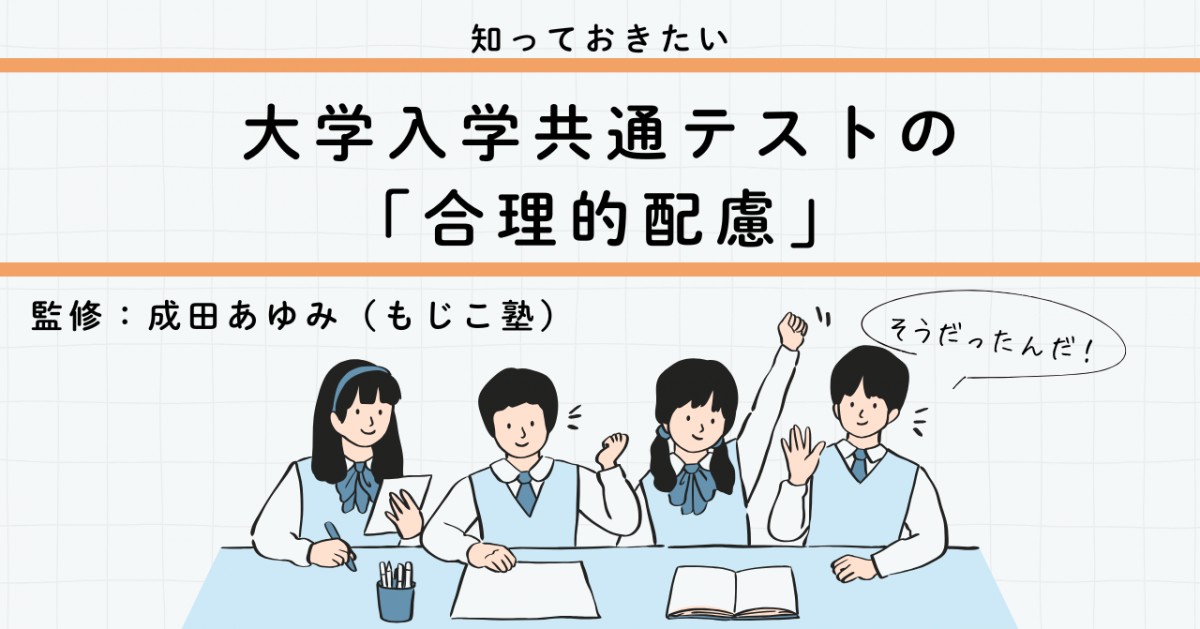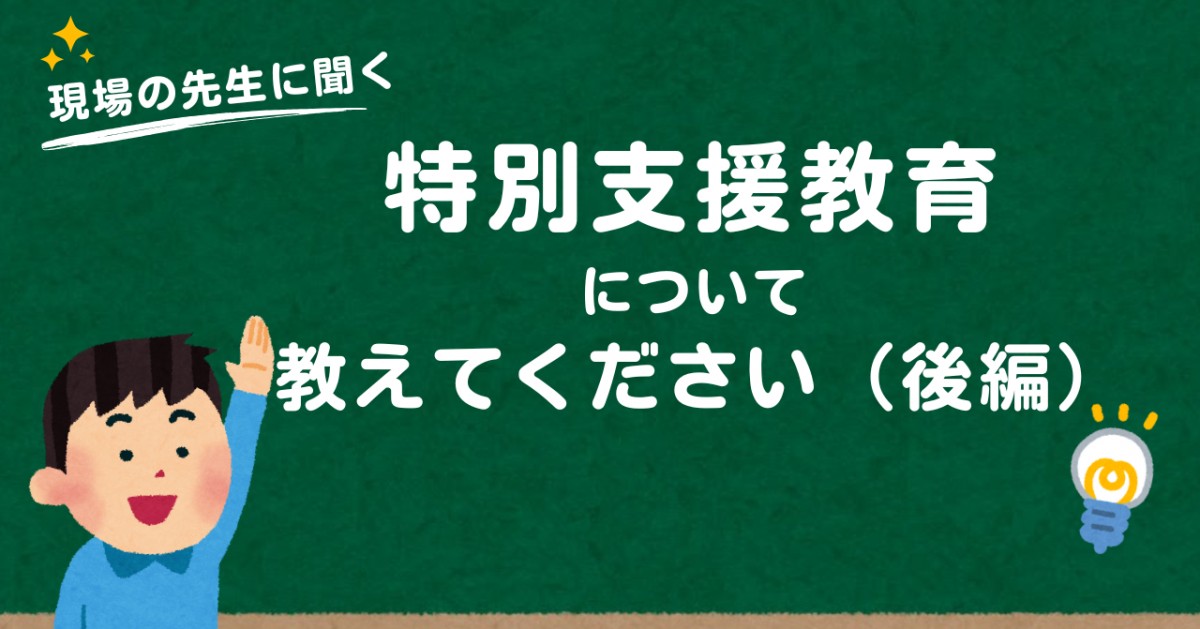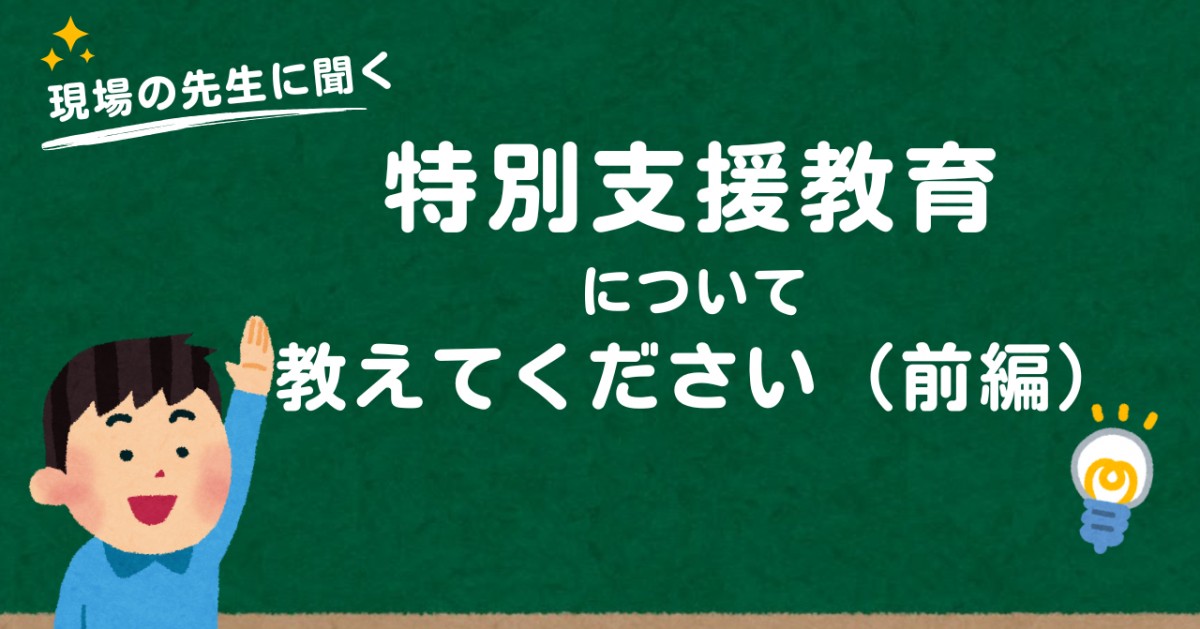「発達障害は存在しない」という言説について考える
「黒坂真由子の『発達障害』情報・体験アーカイブ」では、発達障害にまつわる情報を発信、蓄積しています。専門家から伺った深く細かい情報や現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる個人の経験をお届けします。
運営は、サポートメンバーの登録によって成り立っています。無料と有料があり、有料会員としてご登録いただくと、「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます。発達障害について発信を続けていくために、 応援よろしくお願いいたします。
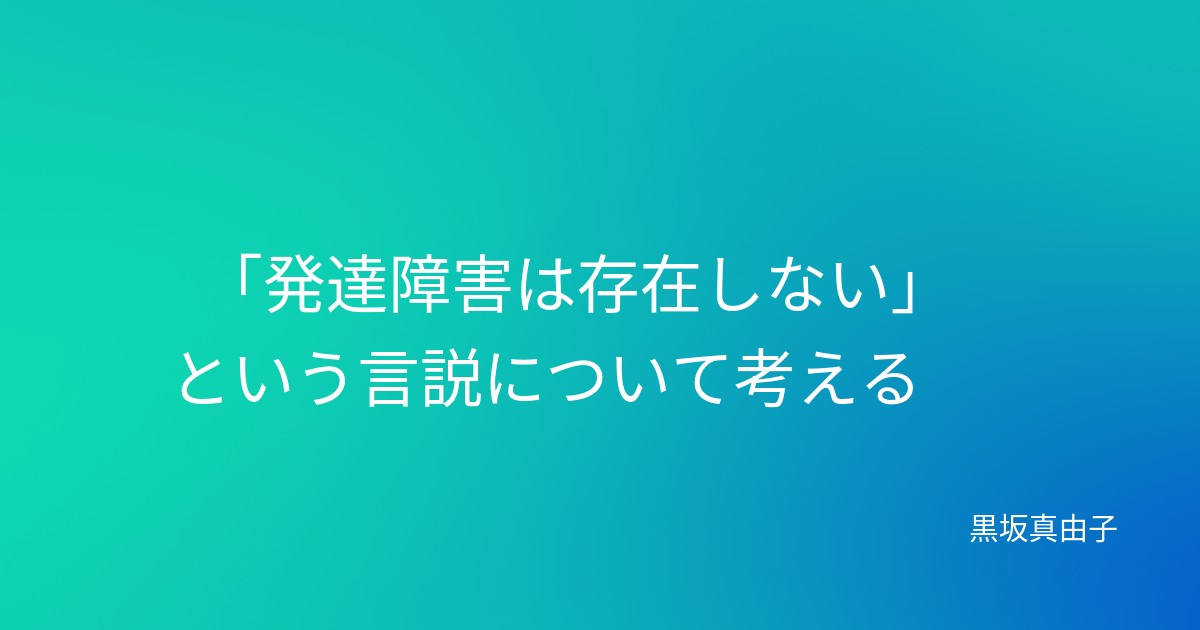
2025年7月16日、一般社団法人日本自閉症協会が次の声明をX(エックス)にポストしました。
ある政党が「そもそも発達障害など存在しない」と公言していますが、これはまったく間違っています。WHOや米国精神医学会には診断基準があり、日本には超党派の議員立法により成立した発達障害支援法があります。発達障害などないという根拠のない主張で私たち当事者や家族を苦しめないでください。
また、日本発達障害ネットワークは、下記の声明を出しています(一部抜粋)。
ある政党の出版物に「そもそも発達障害は存在しない」と いった誤った記載が現在でもあり、日本発達障害ネットワークの会員一同としては非常に遺憾に感じているところです。発達障害者支援法は 2016 年に超党派による議員立法で成立した法律であり、施行後 20 年を経て様々な形で発達障害児者とその保護者の方々に適切な支援が届くようになりました。
これら団体が示しているのは、『参政党Q&Aブック 基礎編』神谷宗幣 (編)2022年(*1)の下記の書籍の内容だとされています(アームズ魂@fukuchin6666 さんのポストから引用します)。
通常の子供たちと全く同じ教育を行えば問題ありません。そもそも、発達障害など存在しません。
*1 著作に関する編者のコメント https://x.com/jinkamiya/status/1944669593370272010
この件は、ニュースとしても取り上げられています。
日本自閉症協会「そもそも発達障害など存在しない」公言の参政党を批判(2025年7月17日)
「発達障害は存在しない」という言説があるということ自体に、不安を掻き立てられた方もいるはずです。また、こういった言説に、どう答えたらいいのかと考えてしまった方もいるかもしれません。
発達障害とは何なのか。こういった言説が広まらないためにも、何度でも確認しておきたいと思います。
答えを一言で述べるのが難しいのは事実です。さんざん悩んだ末に、私が『発達障害大全』のカバーに乗せたのは、次の言葉でした。
「脳の個性」について知りたいことすべて
一人一人の顔や性格が違うように、脳も一人一人違います。その脳の個性のために、今の日本社会で「『普通』に生きていくのが難しい」のが発達障害の人々です。発達障害と診断されるかどうかは、社会の中での「生きやすさ」が大きく関わります。同じ特性を持っていても、困難を感じずに生活できるのであれば、発達障害とは診断されません(困りごとがなければ、そもそも病院に行きません)。そのように考えると、発達障害における「障害」は、社会の側にこそあるのかもしれません。
ただ、今の社会で生きることに全くなんの困難も抱えていない人は、それほど多くないはずです。きっと似たような悩みを誰もが共有できるはずなのです。
これを機に「発達障害とは何か?」と疑問を持った方のために、過去の記事(2025年5月9日)を以下に再掲します。
そもそもの話 第1回 発達障害とは何か?
「発達障害」とは何か。これまでインタビューしてきた専門家の方々に、「答えるのがとても難しい」と言われたのは、この「発達障害の定義」でした。私が担当した『発達障害大全』(日経BP社)をもとに、「そもそも発達障害とはどのようなものなのか」について考えていきます。
●説明が難しい「発達障害」という概念
「発達障害」を説明するのは、けっこう難しいものです。私自身、「発達障害」というものの輪郭がつかめるようになるまでに、取材を始めてからずいぶんと長い時間がかかりましたし、今でも学び続けています。
「発達障害とは何か」。
これまで、たくさんの専門家や当事者の方々にお話を聞いてきましたが、「一番答えるのが難しい」と言われたのがこの「発達障害の定義」でした。なぜなら、発達障害には診断基準はあっても、結局は「本人が困難や障害を感じているか」が重視されるからです。
つまり、「主観に左右される」ということです。
例えば、AさんとBさんに、同じ症状があるとします。 Aさんは、発達障害に理解があり、制度も整っている会社で働いています。一方、Bさんの会社では、理解も制度もありません。この場合、発達障害と診断される可能性が高いのは、Bさん。
同じ特性があり、症状があっても、周囲の環境によって診断されるかどうかは変わります。そもそも、自分の環境に満足しているAさんは、「診断を受けに行く」ということがありません。
また、同じ人でも、診断が降りるかどうかは、ライフステージによって変わります。
社会に出てから「発達障害になった」という人がいますが、実はこれは正しい言い方ではありません。発達障害が突然「発症する」ことはないからです。学生時代までは、なんとか自分の特性や困難と折り合いをつけて生活していけた人が、社会に出て環境が変わったために、対応しきれなくなるということがあるのです。
海外赴任をしたことで、ラクになる、という話もききます。これはまさに、生活する場が変わったことで、生きづらさを感じなくなった例になります。このように、同じ特性があり、症状があっても、周囲の環境によって、「発達障害と診断されるかどうか」は変わるのです。
先日ある方が、「今だったら、発達障害と診断されないだろうな」と言っているのを耳にしました。過去に診断されていたとしても、生きやすい環境が整うことで発達障害の診断がおりなくなると、その人自身が感じているようでした。
●ポイントは、「本人の生きづらさ」
これは、ある数値を満たしたり、ウイルスが検出されれば診断がおりる病気とは、ずいぶんと違います。
例えば糖尿病は、自覚症状が出にくいといわれる生活習慣病ですが、こちらは血糖値などの客観的な基準を満たせば、病気と診断されます。「つらくないから、糖尿病ではない」といくら本人が主張しても、そうはなりません。本人の生きづらさとは関係のないところで、病気かどうかは決まります。
発達障害は、診断基準に加えて、「本人の生きづらさ」が重視されます。
そうなると、自分が周囲に受け入れられるかどうかが、ポイントになってきます。社会の発達障害に対する理解が深まれば、それだけ生きやすい人が増えて、実際に診断される人は減るはずです。一方、発達障害が「増えている」ならば、それは今、生きにくいと感じる人が増えているから、という可能性もあるのです。
●発達障害は、「1つの障害」ではない
「発達障害」という名前は、総称です。
例えるなら、「色」のようなもの。「色」という色がないように、「発達障害」という名前の障害はありません。また、色に、赤、青、黄色などがあるように、発達障害にも、ADHD(注意欠如多動症)、ASD(自閉スペクトラム症)、学習障害(SLD,LD)などがあります。
濃淡があることも、色と似ています。いわゆる「グレーゾーン」という言葉がありますが、これは、濃淡でいえば「淡」の方。発達障害の特性が強く出る人もいれば、特性はあるけどそれほどでもない人がいるということです。
重なることも、色と似ています。青と黄色を混ぜると緑になるように、例えばADHDとASDが重なると、それぞれだけを持つ人とは違った特性が出てくるようになります。
さまざまな色が、濃淡を含めて混ざり合うことで、他の人とは全く違う「色」になる。発達障害の人が100人いれば、100人違った様相を見せるのは、そのためです。
●言葉も定義も変わっていく
発達障害を理解するときに困るのが、用語が難しいだけでなく、定義も変わることです。
そもそも「発達障害」という言葉自体も、変わっています。医師や専門家の中には、「神経発達症」という言葉を使う人もいます。
発達障害の文章の中でよく出てくる主な症状は次のものです。
・注意欠如多動症、ADHD(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder)
・自閉スペクトラム症、ASD(Autism Spectrum Disorder)
・限局性学習症(学習障害)、LD、SLD (Specific Learning Disorder)
この他にも、発達性協調運動症、知的発達症、チック症など、発達障害に含まれる領域があります。
●社会の問題かもしれない
発達障害の人がどれくらいのいるかといえば、だいたい日本における左利きの人と同じくらいだと思います。ざっくりですが、10人にひとりくらい。左利きの状況は、けっこう発達障害と似ているところがあります。
私は左利きですが、子どもの頃、右利きに矯正されたために、字を書くのにかなり苦労しました。長い間、自分の字にコンプレックスを感じていましたし、字を書くスピードも遅かったと思います。包丁やハサミは結局矯正できなかったために、今でも左で使っています。お箸は両方で使えます(便利です)。
また、自分はかなり不器用だと思っていました。例えば、左手で押すように缶切りを使うと、缶の縁が恐ろしくギザギザになるからです。「不器用だねえ」と親からも言われましたし、自分でもそう思い込んでいました。昔の缶切りは「右利き用」だったということに気づいたのは、ずいぶん後のことです。現在のように「ぱかっ」と開けるだけの缶であれば、右利きも左利きも関係ありませんし、今では利き手に関係なく使える缶切りもあります。
同じように、バイトでも大変な思いをしました。
結婚式場で配膳のバイトをしていたのですが、ある時のマネージャーが「右手でサーブする」ことを指示してきたのです。私にとっては、左手で下からお盆を支えることにかなり無理があり(右利きの方にとっては、右手でお盆を下からささえ、左手でサーブすることになります)、持った途端に料理を全て落としてしまいました。
子どもの頃や若い頃、左利きで困ることがあったのは、右利きが当たり前の社会だったからです。だんだんと、左利き用の道具や、利き手に関わらず使える道具が出てきて、困ることは減りましたし、右を使うように強制されることもなくなりました。
つまり、社会が左利きを考慮に入れるようになったために、困ることがほとんどなくなったということになります。(もちろん、あらゆる自動販売機のコインの投入口は右側にありますし、自動改札は相変わらず不便ですが)
長々と左利きの不便さと変化について書いてきたのは、発達障害が同じような状況にあると思うからです。社会が、ある意味「脳の左利き」の人を考慮に入れていないために、いろいろなところで困難や障害が生じています。
例えば、大人の発達障害に詳しい精神科医の岩波明先生は、「社会全体で仕事の管理化が進んでいる」ことを、発達障害が顕在化した理由としてあげられています。つまり、自分のペースで仕事をすることがあらゆる場で許されなくなり、自由度が減ったために、ある決められた枠からはみ出してしまい苦しくなる人が増えているというのです。
また、養老孟司先生は、インタビューで次のようにおっしゃっていました。
僕の知り合いは、学校になじめない子、例えばADHDの子を引き取って、農業をしているんです。「畑に連れていってしまえば、多動もくそもないよ」といっていました。結局、置かれた状況次第なんですね。教室のなかだと多動が目立つけど、畑だったら全然目立たない。田舎で育って、畑にいたら誰も気にしなかったのが、「きちんとしなさい」と座らせようとするから気になる。それができないからって、別に異常なわけではないですよ。
●障害になるかどうかは生きている時代による
実際、障害になるかどうかは、生きている時代と場所によります。例えば、読み書きが苦手な学習障害。文字の読み書きができないのが当たり前の時代であれば、特に障害とされることはなかったはずです。
現在、読み書きが苦手な学習障害の人は、手書きが中心の小学校や中学校で苦労が多く、困っている子どもを早く見つけてサポートする必要があります。一方で、ICT機器を使うことでその困難を乗り越えている子どももいます。技術の進歩によって、読み書きの困難が減じられつつある例だといえるでしょう。
時代や場所によって、障害になるかどうかは変わります。そして今の状態がずっと続くわけではありません。
このように考えると、発達障害というのは、今現在の「社会の問題」として捉えることができます。左利きがずいぶんと生きやすくなったように、社会が変われば、発達障害の人ももっと生きやすくなるはずです。
そして、困っている人が生きやすい社会は、だれにとっても生きやすい社会となるはずです。
・「黒坂真由子の「発達障害」情報・体験アーカイブ」の説明、自己紹介などはこちら。
・『発達障害大全』(日経BP社)の「はじめに」を読んでみようかな、と思う方はこちら。
*リンクは別ウインドウが開きます。
最後までお読みいただきありがとうございます。ぜひ会員としての応援をよろしくお願いいたします。
無料会員として
有料会員として
すでに登録済みの方は こちら