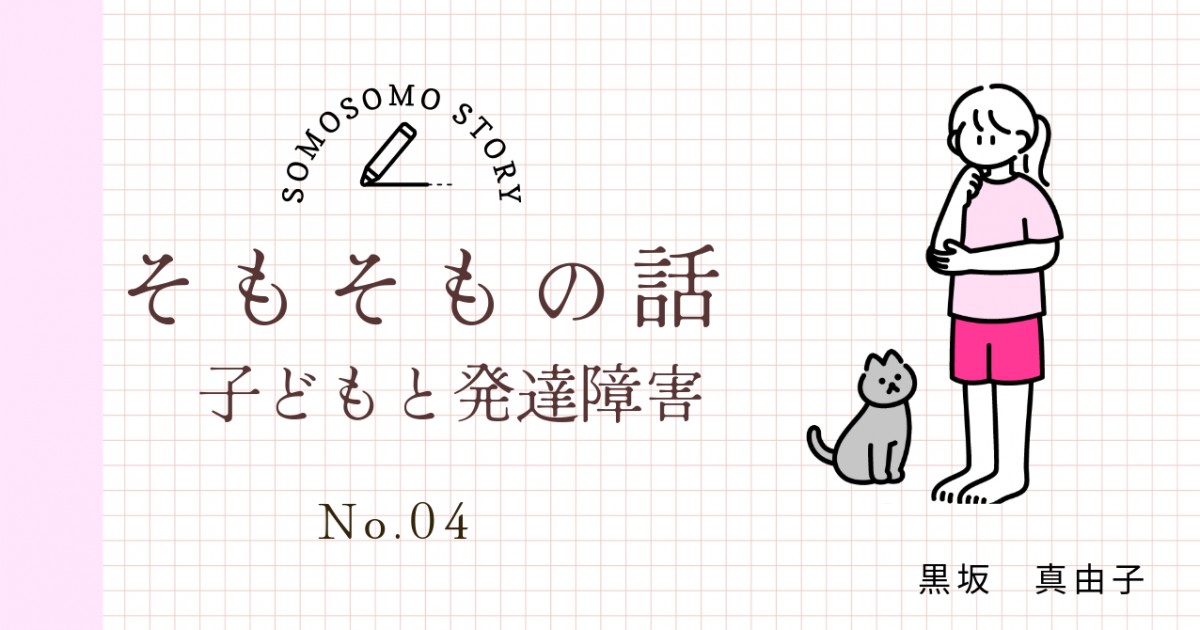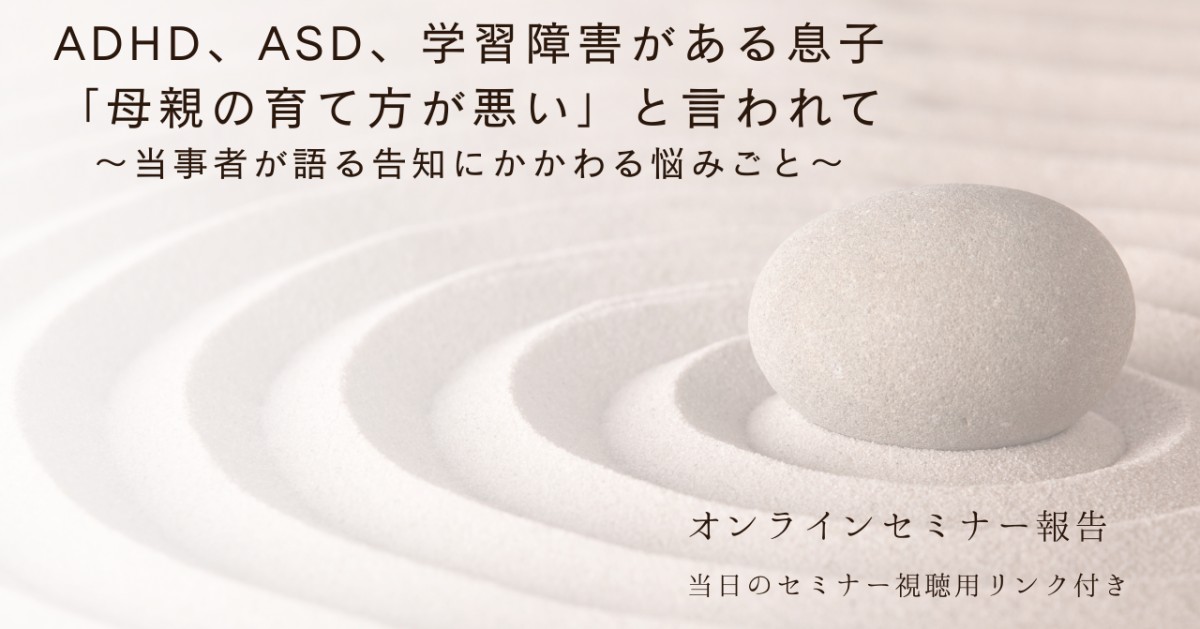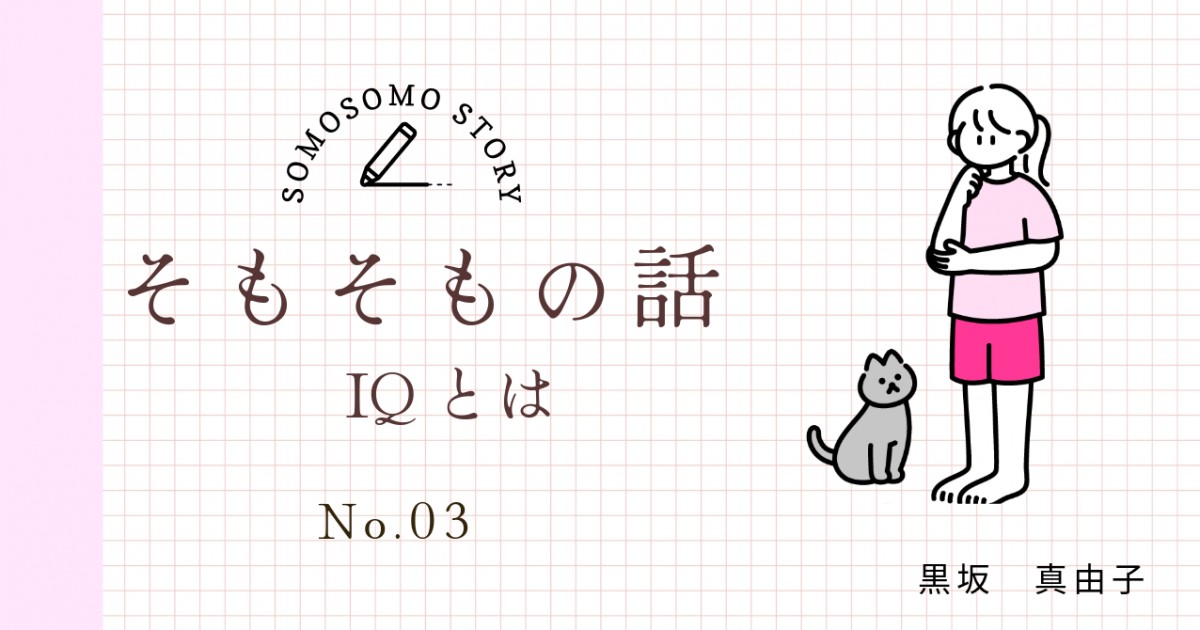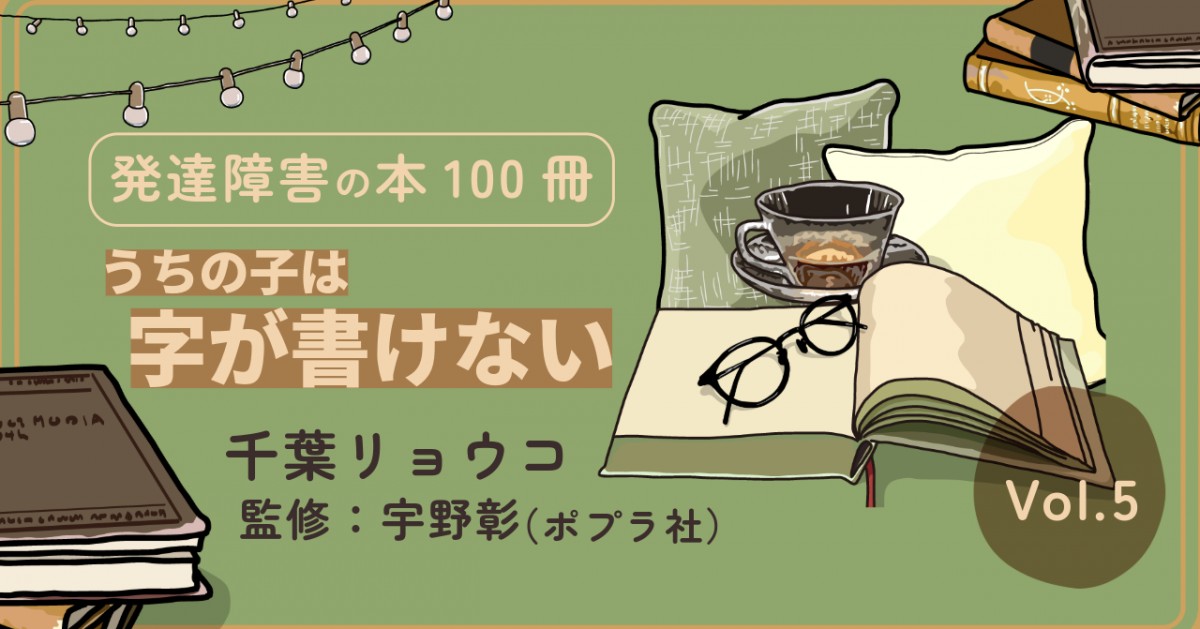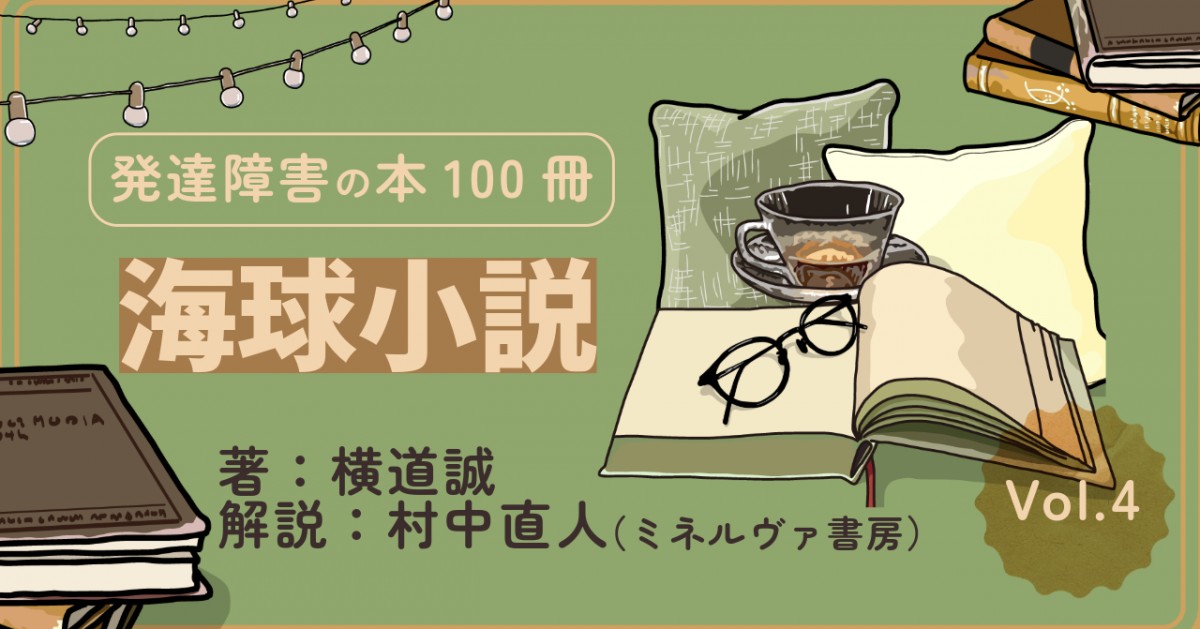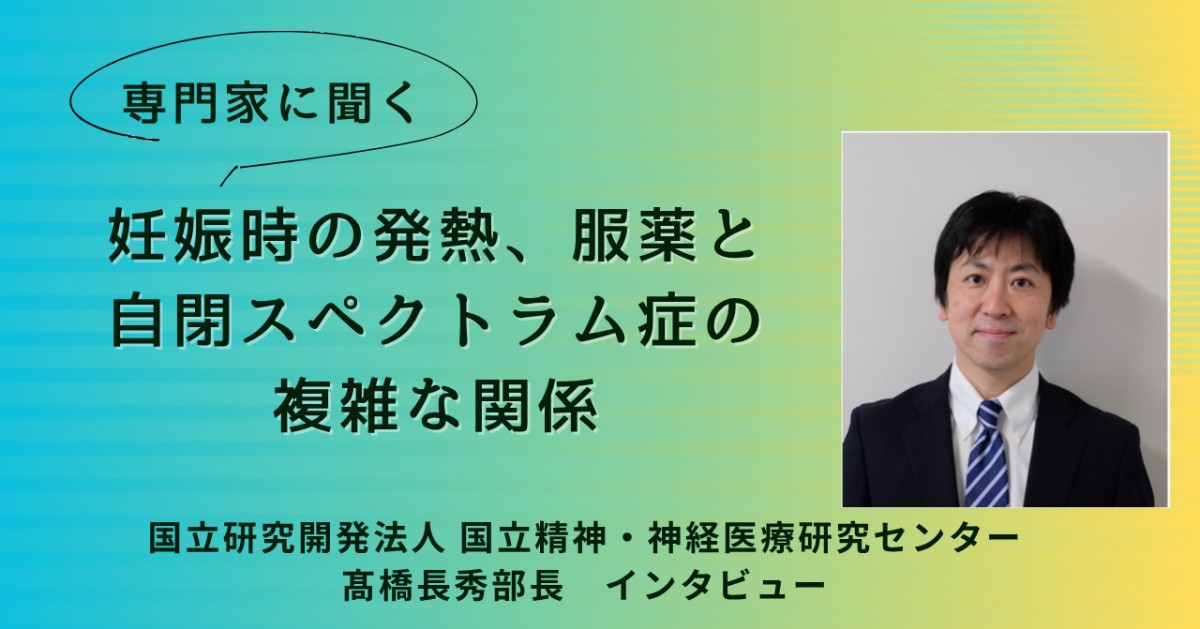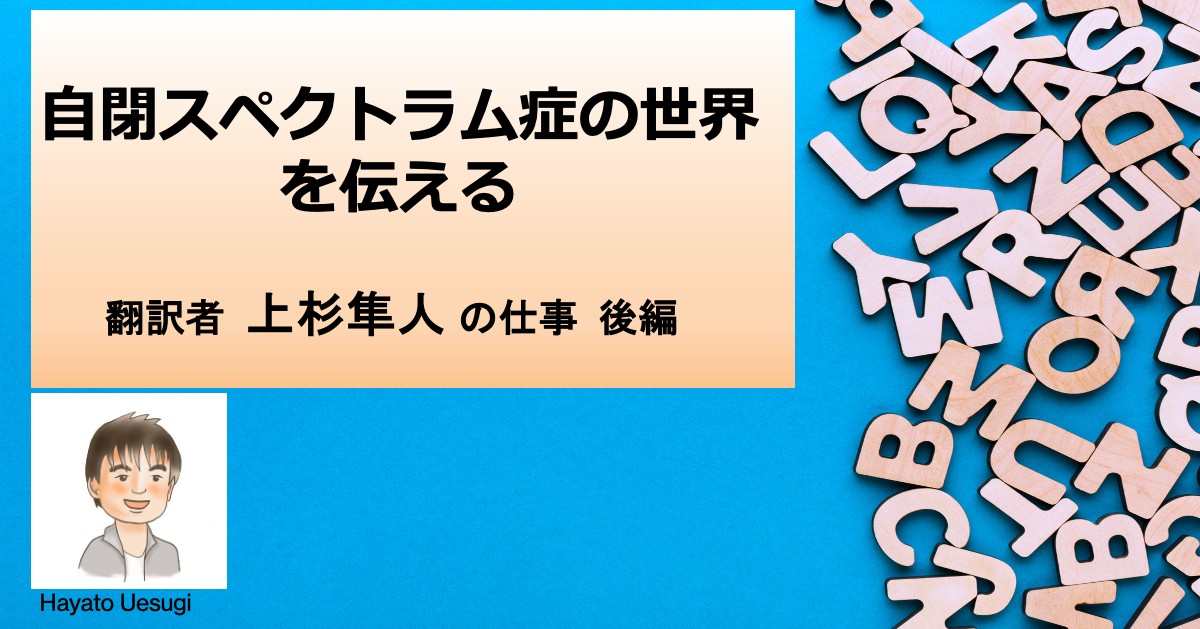[専門家に聞く:岩波明氏インタビュー]
発達障害は、なぜ誤診されるのか?
誤診は3割以上。さらに多い可能性も
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。
発達障害について発信を続けていくために、応援をよろしくお願いいたします。
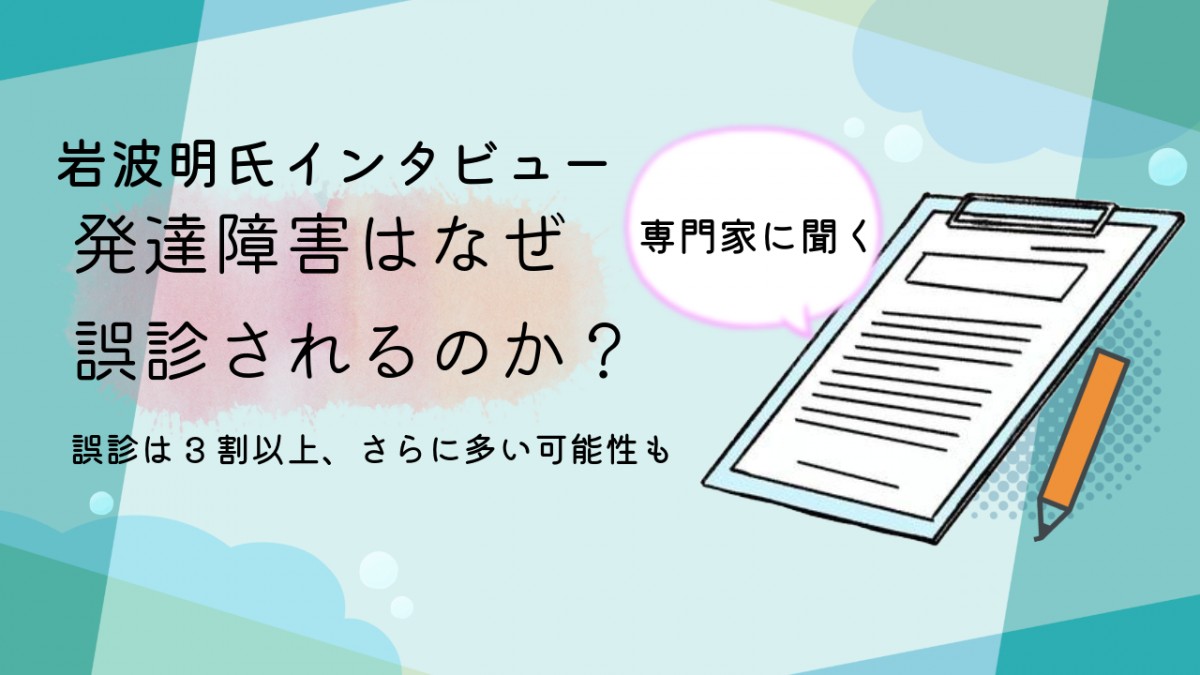
プロフィール
岩波明(いわなみ あきら)
1959(昭和34)年、神奈川県生まれ。東京大学医学部医学科卒。精神科医、医学博士。発達障害の臨床、精神疾患の認知機能の研究などに従事。東京都立松沢病院、東大病院精神科などを経て、2012年より昭和大学医学部精神医学講座主任教授、2015年より昭和大学附属烏山病院長を兼務。2024年より昭和大学特任教授。著書に『発達障害』(文春新書)、『医者も親も気づかない女子の発達障害』(青春新書)、『誤解だらけの発達障害』(宝島社新書)など多数。
●誤診の割合はどれくらい?
−− これまでの臨床のご経験から、誤診のおおよその割合を教えてください。
岩波明氏(以下、岩波):はっきりしたデータはありませんが、3〜4割はありそうです。もしかすると、もっと多いかもしれません。
−− どのように誤診されて、先生のところにたどりつくのでしょうか?
岩波:大きく二つのパターンがあります。一つはASD(自閉スペクトラム症 *1)の過剰診断によってADHD(注意欠如多動症 *2)を見逃してるパターン。これはかなり多いです。もう一つはうつ病や双極性障害と診断されているけれど、本質的にはADHDであるというパターンです。双極性障害は、これまで躁うつ病とよばれた疾患です。
−− 3〜4割の患者さんが、そのように誤診されていた、ということですね。
岩波:特に、ASDの過剰診断によるADHDの見逃しは多いのですが、それはこの病院(昭和大学附属烏山病院)にADHDの専門外来があるからかもしれません。
−− 日本初のADHD専門外来ということで、たどり着いた患者さんがいるかもしれません。なぜ、ADHDはそんなにも見逃されているのでしょうか?