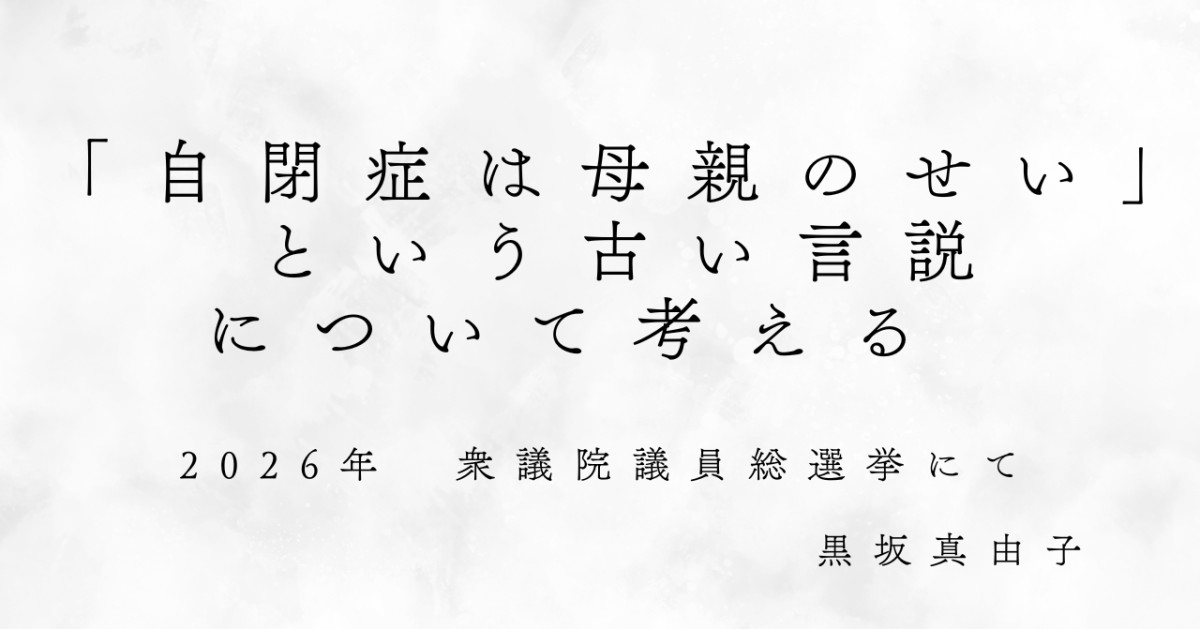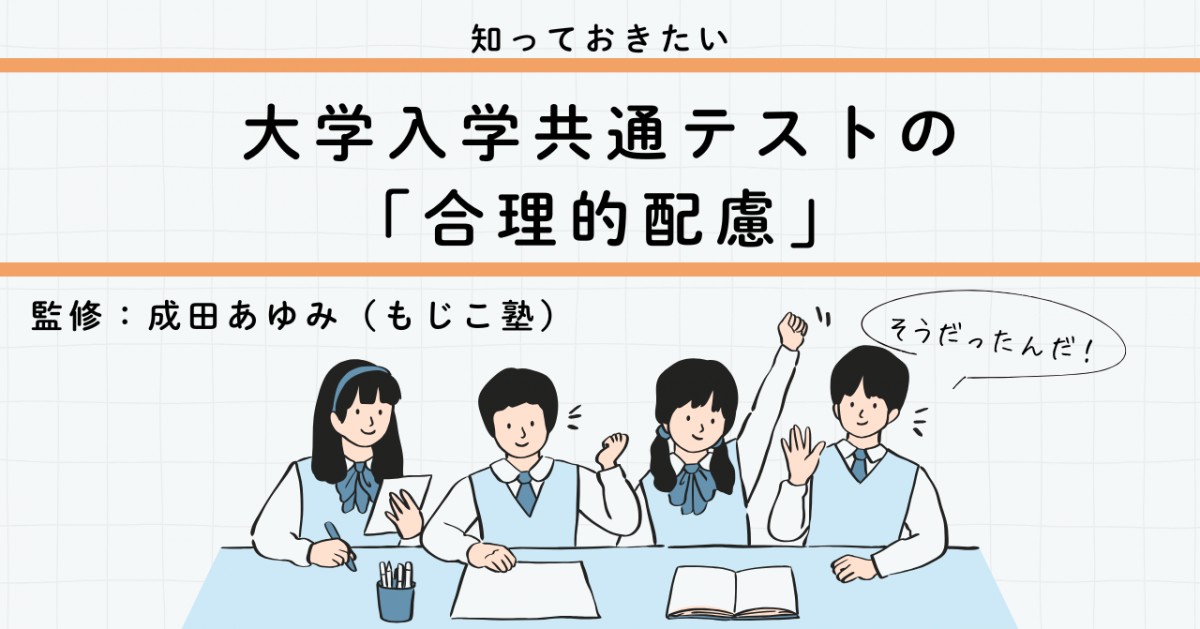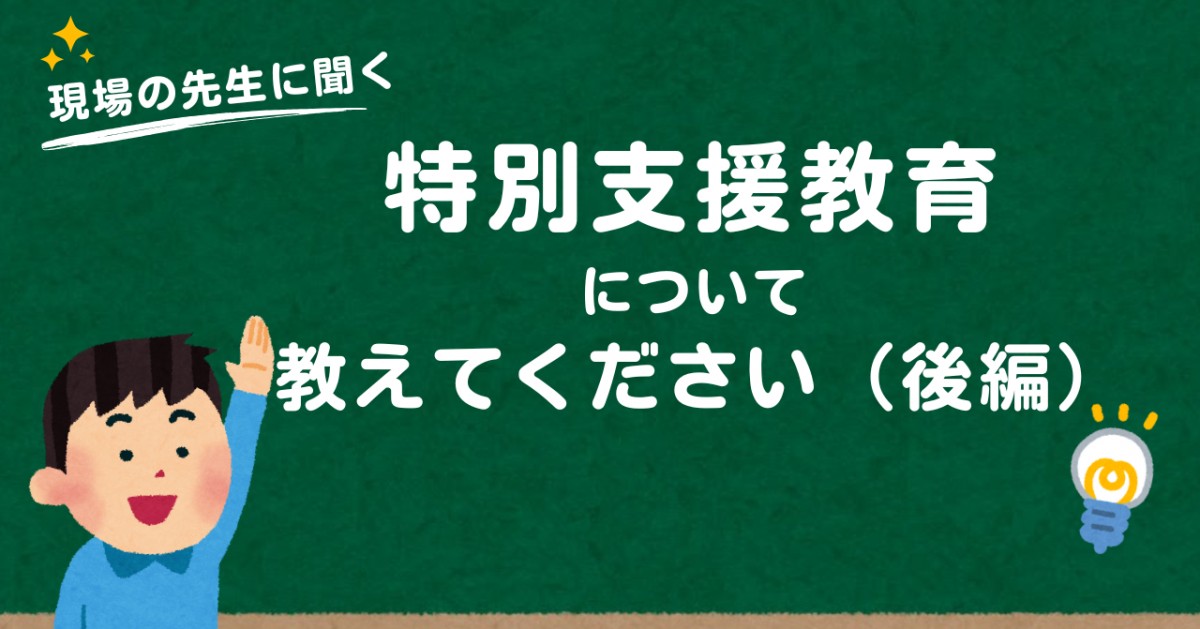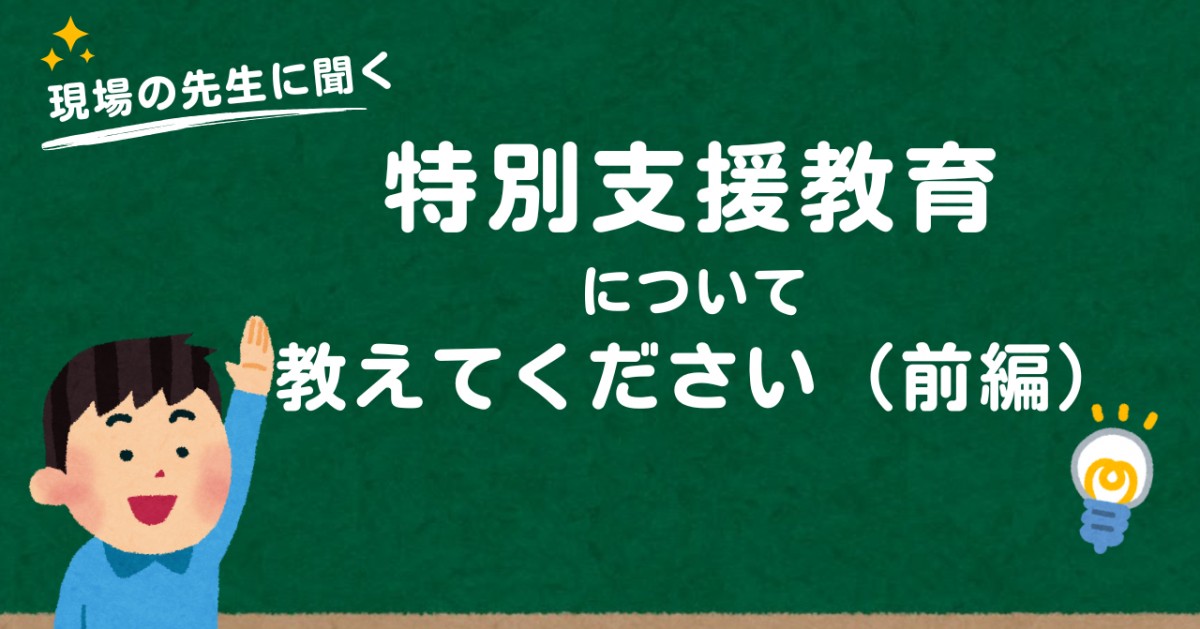日本成人期発達障害臨床医学会 レポート
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家からの深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。
発達障害について発信を続けていくために、応援よろしくお願いいたします。
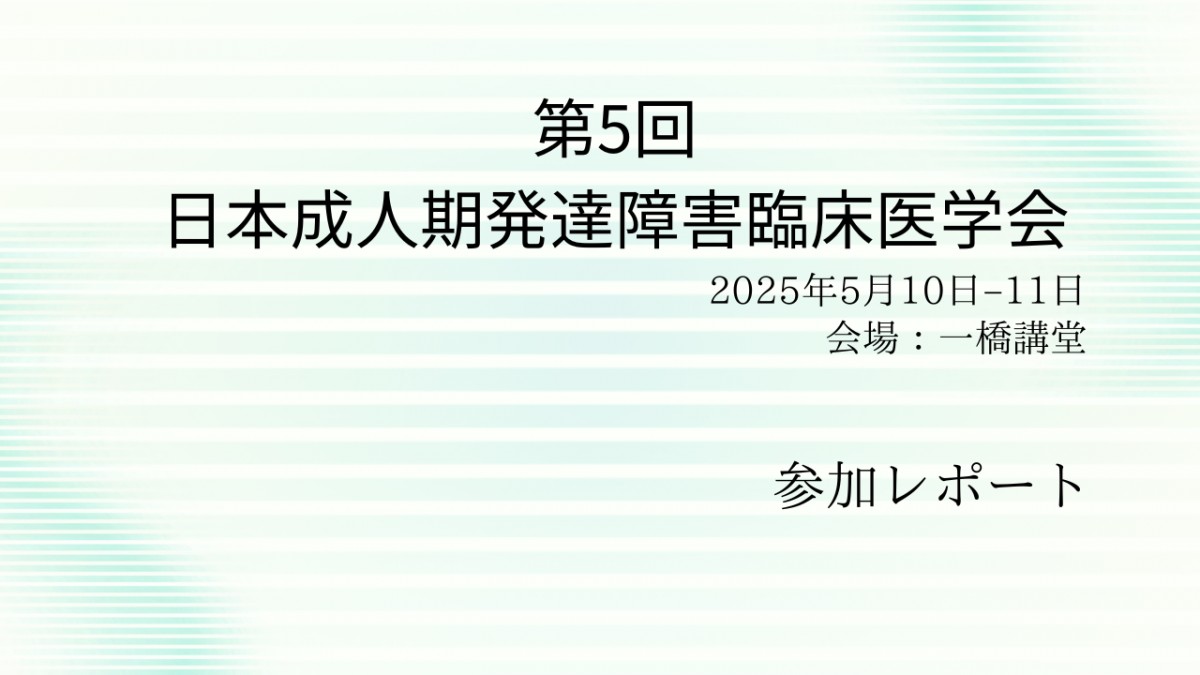
2025年5月10日、11日の2日間、東京都の一橋講堂において「日本成人期発達障害臨床医学会」が開かれました。この学会は、成人期の発達障害の臨床、研究、教育などを推進する目的で、2019年にスタートしました。(学会のHPはこちら。外部サイトへ移ります)
なぜ、あえて「成人期」なのかといえば、「発達障害といえば児童」という時代が長く続いたからだといいます。実は、成人期の発達障害については、長い間顧みられてこなかったというのです。大人の発達障害が当たり前に語られるようになったのは、このような学会や、発達障害の治療や教育、サポートに関わる方々の活動によるものなのだと、会に参加して感じました。とはいえ、学会では大人の発達障害に限らず、発達障害に関する話題が全般的に取り上げられていました。
今回の大会のテーマは「発達障害 診療・支援の最前線」。
実は、「学会」と名のつくものに参加したのは、初めてです。そもそも臨床医(病院などで診療を行う医師)の学会に、自分が参加できるなどとは思っていなかったのですが、この学会の企画・運営をされている昭和医科大学の岩波明先生にお招きいただき、この学会が一般参加が可能ということを知りました。
2日間参加しての感想は、「最新の情報や現状の課題に一気に触れられ、ありがたい…!」というもの。子どもと大人をつなぐ研究、栄養と発達障害をめぐる現在地、犯罪と裁判、そして地域社会の問題など、数々のリアルな症例・事例にあふれていました。現場で働いている医師や臨床心理士、社会福祉士、キャリアコンサルタントだからこそ伝えられる内容でした。取材したいことが一気に増えた2日間となりました。
今回はこの中から、私も司会者の1人として参加させていただいた「就労支援事業の現状と課題」についてご報告します。また、専門家4名を招いてのパネルディスカッション、「10代の自殺」についてもレポートします。
●「就労支援事業の現状と課題 ~人口減での障害者雇用~」
ハートクリニック横浜・院長の柏淳氏、黒坂が司会を担当。まず、株式会社Kaienの代表取締役、鈴木慶太氏が登壇。鈴木氏は長男の診断をきっかけに、発達障害に特化した就労支援企業Kaienを企業した元NHKアナウンサーです。Kaienでは、「就労移行支援」「就労定着支援」だけでなく、専門プログラム「ガクプロ」で学生の支援にも力を入れています。現在40ほどの拠点で、15年間で2000人以上の就職者を輩出しています。
鈴木氏は、就労支援を行う上での支援の構造を、3つ挙げています。まず「本人のアセスメント」。 2つ目が体験・実践を通じ「本人に納得してもらう」こと。3つ目が「仕事を探すこと・紹介する」こと。この中で特に大変なのは、2つ目だといいます。体験・実践を通じて「本人に納得してもらう」という部分です。なぜなら、他者目線が弱い発達障害の方は、アセスメントを通じてその人に合う道を示したとしても、その道に進んでくれるわけではないからです。むしろ本人の苦手なところ、コンプレックスを持っているところに進もうとしてしまうことがあるといいます。
実際、こういった話はよく聞きます。あえて苦手な職を選んでしまうのは、「苦手なこと」への憧れや、「普通でありたい」という強い思いがあるのかもしれません。
Kaienでは、自社の中で数百の仕事が体験できること、就職先を独自で数百社開拓していることから、高い就職率と短時間での就職を可能にしているといいます。
ただ一般には、まだまだ障害がある方の就職は厳しいのが現状です。そのような中、国は「障害者就労支援士」という新たな国家資格を検討している、と鈴木氏。初めて聞いたこの言葉を調べてみると、「障害者の就労を支援する人に向けた新しい資格」であり、将来的には国家資格にすることが検討されているとありました。国が本格的に、就労支援をする人材の育成に乗り出したという意味で、期待をしたいところです(*1)。
鈴木氏は、地方は都市より厳しい状態にあると指摘します。法定雇用率の上昇(現在の2.5%から、2026年7月には2.7%に引き上げ)のために、都市の大企業での採用は増えているものの、大企業のない地方ではそのような効果が期待できないからです。地方では特に、工賃主体の「就労継続支援B型」への依存が顕著だということでした。
次に登壇したのがVALT JAPAN 株式会社代表取締役CEOの小野貴也氏です。小野氏は全国の「就労継続支援事業所」のネットワーク化を進めています。ここに、「就労継続支援B型」への依存から、脱却するヒントがあるように思えます。
小野氏によれば、A型・B型と呼ばれる「就労継続支援事業所」は、国内に約2万か所ほどあり、それは「大手コンビニエンスストア」とほぼ同じ数。それらの事業所のほとんどが、民間企業からうまく仕事を受注できず、しかも仕事の内容は軽作業にかたよっているとしています。さらに、事業所の営業不振から撤退が相次いでいるという問題も。
このような現状を変えるべく、VALT JAPANが行っているのは、「デジタルの力を使って、全国の事業所と一般企業を結びつけること」です。どのような障害をもつ人が、どのような仕事ができるのかをデータ化し、民間企業の仕事を「切り出し」て、マッチングを行います。それぞれの事業所ではなく、かわりにVALT JAPANが仕事を受注し、全国に散在する小さな事業所に配分するという方法です。
つまりVALT JAPANが事業所の代わりに営業をし、仕事をとってきてくれるということです。そして、各々の事業者に所属する方、それぞれに合う仕事を紹介してくれる。確かにこの方法であれば、地方にある小さな事業所であっても、利用者の能力に合った適切な仕事が見つかるかもしれません。
小野氏によると、精神障害や発達障害のある方は、PCを使ったデータ入力や、AIを使用した仕事を得意とする方が多いといいます。例えば「AIが仕分けした会計データをチェックする」というある会社からの業務は、最初の1ヶ月、13万8000円の発注から始まったものが、2年後には年間1億円まで拡大。しかもこれは「発注」であり、その会社の法定雇用率にはカウントされないのだといいます。それでも大型の発注が継続しているのは、そもそも日本国内に「デジタル人材」が足りないから。「特に発達障害のある方々にとって、大きなチャンスが、今、来ているんです」と、小野氏は言葉に力を込めます。
私が驚いたのは、「全国の就労支援事業所でデジタル領域に対応しているところは、たったの4.1%しかない」ということでした。移動をしなくても、パソコンがあればできる仕事も、その幅も増えている現在、事業所での仕事が軽作業に偏っているのはもったないことです。もっと、自宅や事業所でパソコンをつかった仕事ができるようになれば、仕事が選べるようになるのではないかと思います。
小野氏は「AIによって、高度なAI人材でなくても活躍できるようになってきている」とし、エンジニア領域、データベース領域、デザイン領域、動画制作などのクリエイティブ領域、そして先に話題となった会計領域を挙げます。VALT JAPANでは新たな試みとして、デジタル人材育成に力を入れているといいます。すでに丸の内に、三菱地所とともにA型事業所「デジタルイノベーションセンター」を開設しています。この新たな試みについては、今後詳しく取材をしたいと思います。