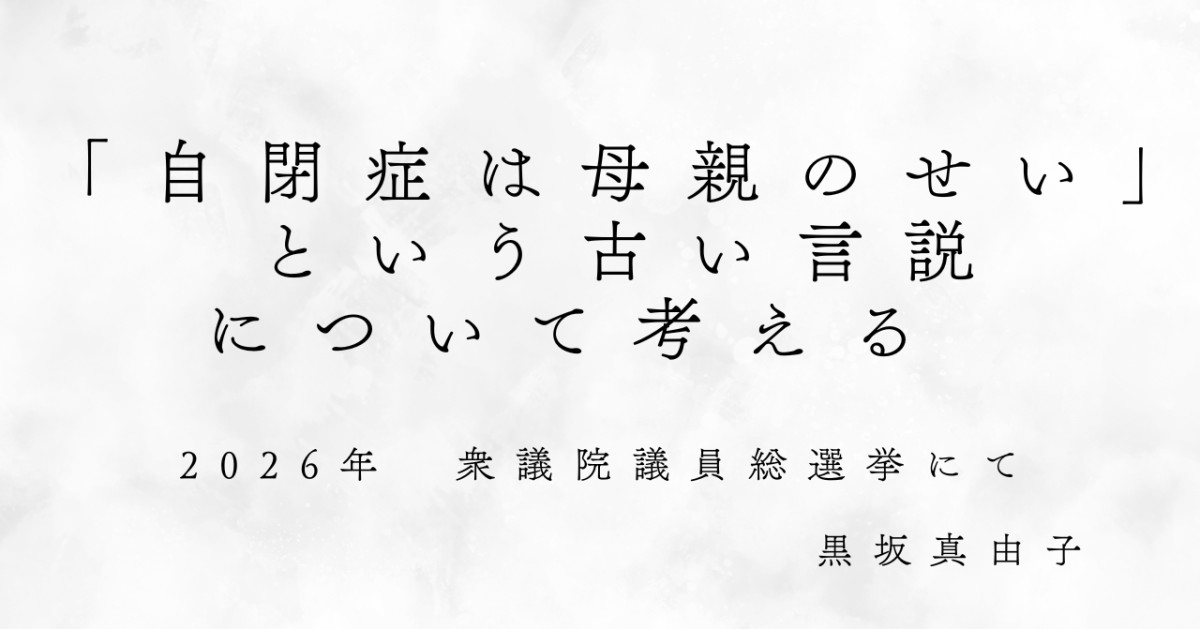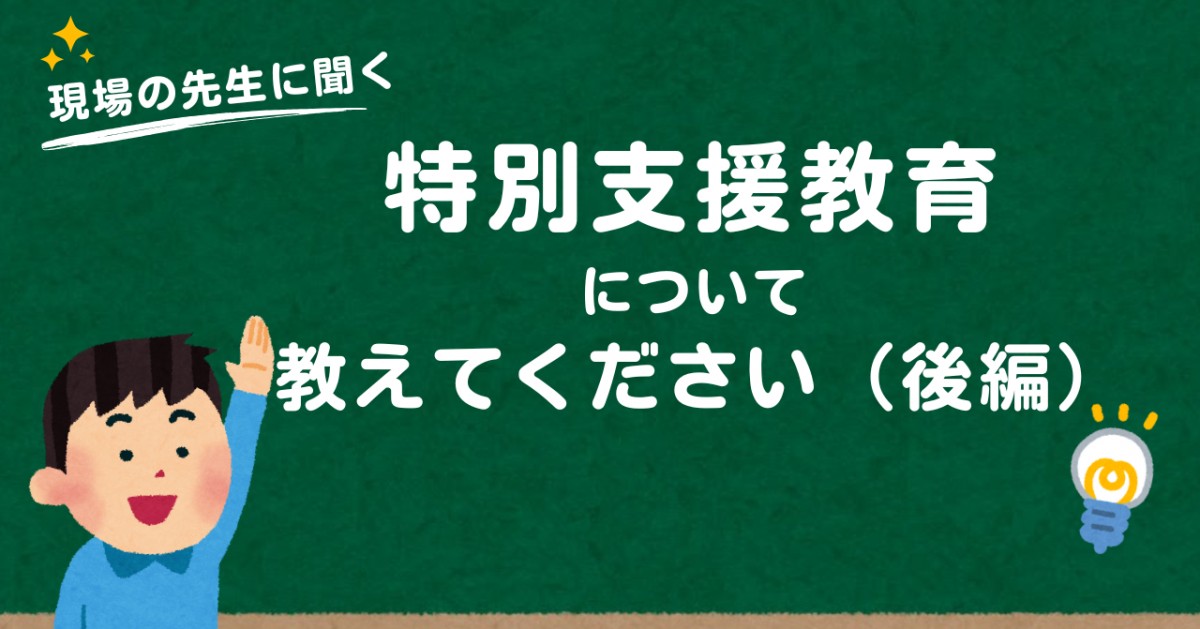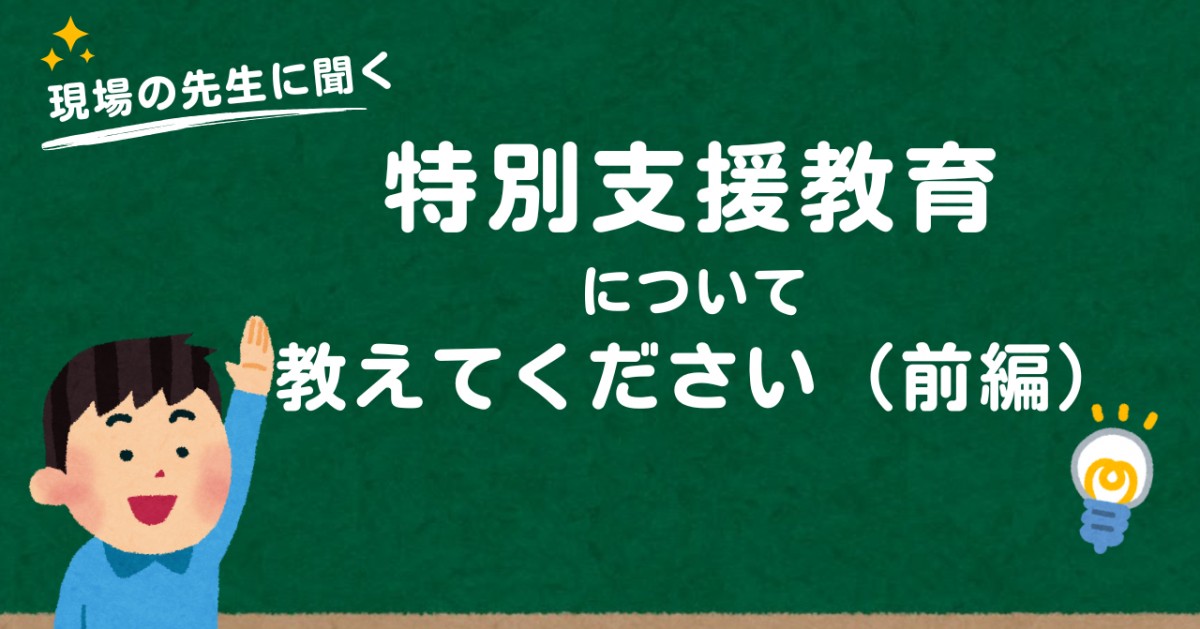『鳥の心臓の夏』
ヴィクトリア・ロイド=バーロウ(著) 上杉隼人(訳) 朝日新聞出版 (2025 年3月刊行)
「アーカイブ」では、発達障害関連の情報を発信しています。専門家からの情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験も記事にしています。なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわるリアルな情報をお届けします。
サポートメンバーの登録により、発達障害についての継続的な発信が可能になります。メンバーとしてのご登録をお願いいたします。メンバーシップは、無料、有料から選べます。概要について、詳しくはこちらをご覧ください。
*お知らせ:覚えやすさ、検索のしやすさを考え、2026年からタイトルを「黒坂真由子の発達障害レポート」に変更します。今後とも応援よろしくお願いいたします!

帯には『自閉症の僕が跳びはねる理由』の著者、東田直樹さんの言葉。「自閉症者のもどかしさをここまで情緒的に綴る文章は僕には書けない」がこの本を表現しています。カバーに広がる水は、自閉スペクトラム症の世界観に重なります。
●二つの世界を生きる
自分とは違う世界で生きる子どもを育てる。
主人公のサンデーは、そんな毎日を生きています。サンデーの生活は、さまざまな習慣や制約に満ちています。食事は白い食べ物しか摂らないし、人から触れられるのも苦手。色がついたものを食べると喉と体が焼けるように痛くなるし、触れられるとかゆくなってしまいます。
人とのコミュニケーションは、『淑女の礼儀作法 社会活動のガイド』という本によって学び、例えば初めての人と話をするときには、その本の該当箇所を思い出し、その通りに振る舞うように努力するのです。
でも、娘のドリーは違います。色がついたものでも平気で食べられるし、人との関わりあいはとても自然です。愛する娘のために「普通でいよう」とする日々が、サンデーの毎日なのです。
著者のヴィクトリア・ロイド=バーロウは、自身も自閉スペクトラム症で、その世界を自らの手で表現しています。ヴィクトリアはイギリスのケント大学でクリエイティブ・ライティングの博士号を取得。本作がデビュー作です。この本は2023年のブッカー賞の候補作にもなりました。
ブッカー賞は世界的な権威のあるイギリスの文学賞です。自閉スペクトラム症の著者が候補となったのは初めてのことであり、自閉スペクトラム症の人々の生きている世界を広く知らしめることになったという点でも、この本が担った役割は小さくないはずです。
本書は、1980年代のイングランドの湖水地方が舞台。まだ、自閉スペクトラム症への理解も進んでいなかったと思われる時代です。この物語は母であるサンデーの一人称の視点で語られますが、そこにある世界の感じ方は、著者のヴィクトリアが生きる世界と重なるものです。
外からではなく中から、自閉スペクトラム症の人が見ている世界を見ることができるのが、この本の大きな魅力です。自分が当たり前に生きている世界と、サンデーやヴィクトリアが生きる世界の違いを、物語を通じて体感できるのが本書の素晴らしさです。
●「やっぱり感謝されたらいいなあ」という願い
サンデーは、自分の世界と娘のドリーとの世界の違いを理解し、娘の世界に合わせて生きようとしています。それは愛情ゆえで、苦痛なことではないと思いつつも、娘にわかってもらいたいという思いを抱えています。
お母さんはあたしとは違うんだとドリーに思われないように、常に正常であると装おうとした。あの子の前ではわたしにとっては自然なことをできる限り抑えた。
あの子のために白いもの以外の食べ物を口に入れる時は、あの猫のように体をこわばらせてしまったし、私がしていることに対して言葉にはされなくてもいいし、もちろん騒ぎ立てられる必要なんてないけど、やっぱり感謝されたらいいなあ、と願わずにいられなかった。
「やっぱり感謝されたらいいなあ」という願い。白いものだけを食べるのは、サンデーの普通。自分の普通をあきらめて、赤や緑や茶色の物を口にするのは、娘のため。自ら進んでそうしているとはいえ、その努力をわかってもらいたいと願ってしまうのです。
このようなことは、私たちの現実でも起こっていると思います。自分の当たり前が、周りの人の当たり前だと思って生きていますが、でも本当にそうなのかと、少しでも考えてみる必要があるのだと思います。
発達障害をもつ人は多くの場合、周りの「普通」に合わせようと日々努力をしています。しかし周りが、その努力や頑張りに気づくことはほとんどありません。私自身、子どもの「予定変更が苦手」に気づくまでに、けっこう時間がかかったと思います。「せっかく時間ができたから外食しようと言っているのに、なんで嫌がるの?」などと思い、口にもしていました。
そんなふうに、自分の当たり前を人に押し付けていることにさえ気が付かないのですから、相手が自分に合わせてくれているなどとは、つゆほども気づいていなかったはずです。
サンデーは、自身の子ども時代を振り返りながら、物語を進めていきます。サンデーがどのような子ども時代を過ごしたのか。サンデー自身、自分の痛みについて多くは語りませんが、決して穏やかな子ども時代でなかったことは、回想の端々から伝わってきます。
学校のブレザーを着たわたしの背中を両親が恥ずかしそうに肘でつついている。わたしは頭の中で完璧な文章を作り出したのに、それを外に出すことができなかったのだ。泳ぎがすごく達者な人が、水中に閉じ込められてしまったかのようだ。
この「水の中にいる感覚」は、自閉スペクトラム症の当事者で研究者である横道誠氏も述べています。発達障害と診断されてから著したタイトルは『みんな水の中』。インタビューをしたときにも、「いつも水の中にいると感じている」と述べていました。
物語が効いてくるのは、この「水の中」を追体験できることだと思います。
自閉スペクトラム症であるサンデーに入り込み、サンデーの視点から世界を眺めること。ゆらゆらとしたこの世界を眺めること。そのゆらぎのある世界は、本書に散りばめられた比喩の数々で表現されているのかもしれません。
比喩の多さとその訳出の困難さは、翻訳者上杉隼人氏がインタビューで言及しています。
サンデーの日常を大きく変えることになる隣人のヴィータが目の前に現れたときの描写も、現実から少し離れた場所から眺めているかのようです。
高いところから落ちたのか、あるいは意識のない状態で誰かにそこに放り出されたのか、いずれにしろ女の人は仰向けに横たわり、腕と脚を不自然なほど広げていた。(中略)
その年の初夏の日々は記憶に残るほど明るかったし、靄がかかったような陽の光はこれから暖かさをもたらすと思わせたが、実際はそうはならなかった。今思えば、その年の初夏の日々は、次の年に訪れる酷暑の予告編だったかもしれない。靄がかかったようなこの町を、灼熱の暑さが突然爆発して腕を広げ、うすら笑いを浮かべながら行ったり来たりする予告編だった。
ヴィータは腕を水平に広げて、手のひらを上に向けて、まるで贈り物を受け取ろうとしているかのようだった。美しくまとめられた髪と、インクで染めたような濃い色合いのきちんとした服にまず警戒した。そんなきっちりした外見が、意図せずに崩壊や暴力的なものを映し出していると思えたのだ。
ヴィータの出現によって、娘のドリーのために築き上げた生活が変化していくことで、物語は大きく動き始めます。
急いで読むにはもったいない淡い光を放つ物語。のんびりと読み進めてください。
ヴィクトリア・ロイド=バーロウ(著) Viktoria Lloyd-Barlow
イギリスの作家。ケント大学でクリエイティブ・ライティングの博士号を取得。2023年発表のデビュー作である本作が同年のブッカー賞のロングリスト入りを果たし、自閉スペクトラム症の作家として初のブッカー賞候補となる。現在は創作活動を続けながら、自閉スペクトラム症と文学の関係について積極的に発言している(ハーパード大学でも講演)。夫と子どもたちとケントの海岸地域で暮らしている。
上杉隼人(訳) Hayato Uesugi
編集者、翻訳者(英日、日英)、英文ライター、通訳。早稲田大学教育学部英語英文学科卒業、同専攻科修了。訳にマーク・トウェーン「ハックルベリー・フィンの冒険」(講談社青い鳥文庫)、ムスタファ・スレイマン『THE COMING WAVE AIを封じ込めよ DeepMind創業者の警告』(日経BP/日本経済新聞出版)など多数。自閉スペクトラム症関連の本の訳に、ジョリー・フレミング『「普通」ってなんなのかな 自閉症の僕が案内するこの世界の歩き方」(文藝春秋)がある。
*気に入っていただけたら、シェアしてくださると嬉しいです。いつもお読みくださり、ありがとうございます!
すでに登録済みの方は こちら