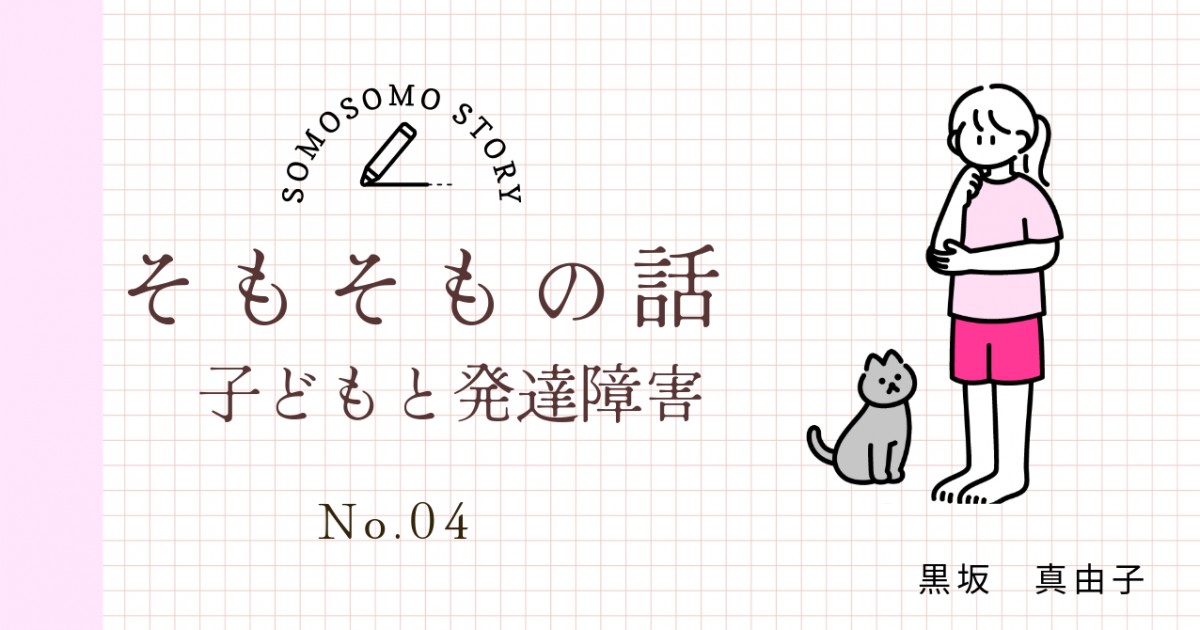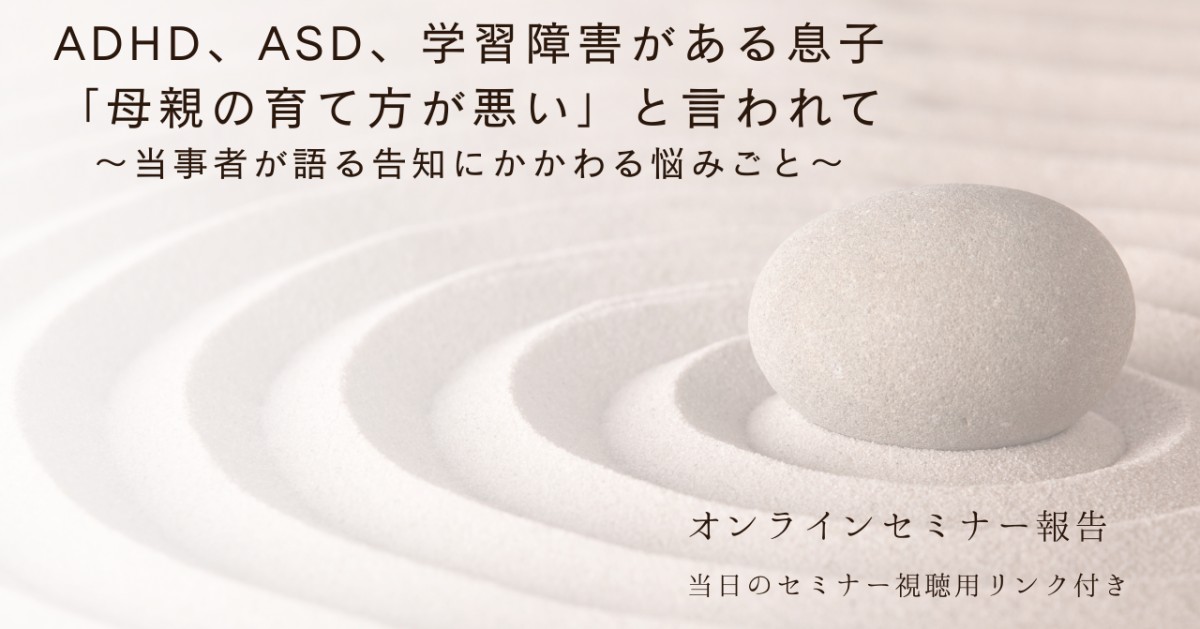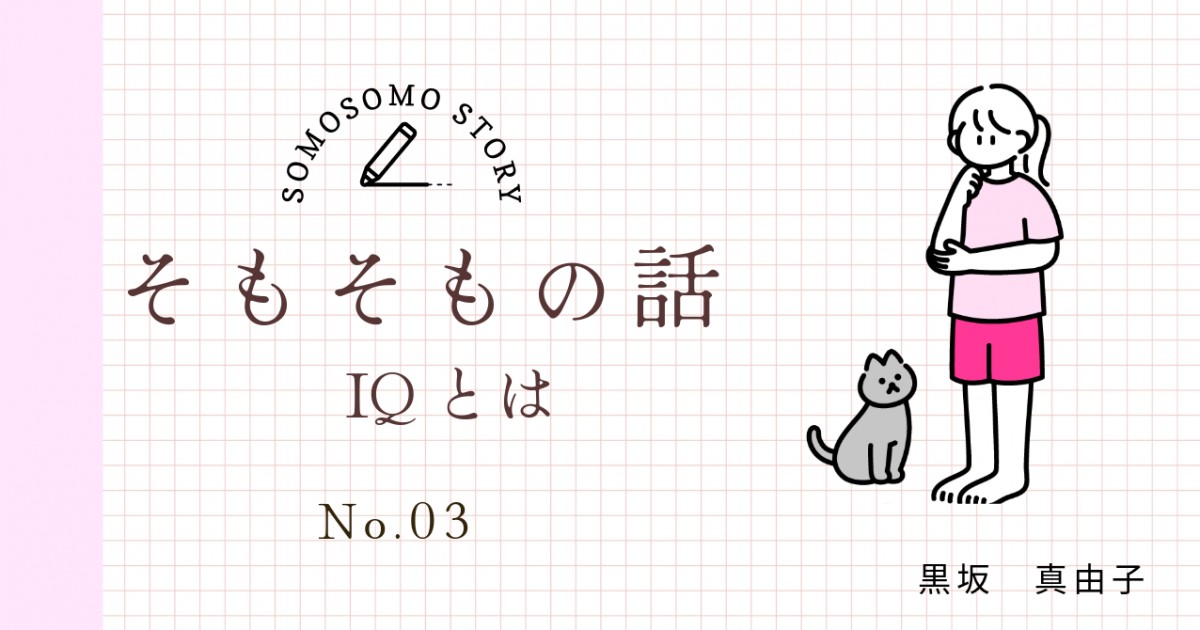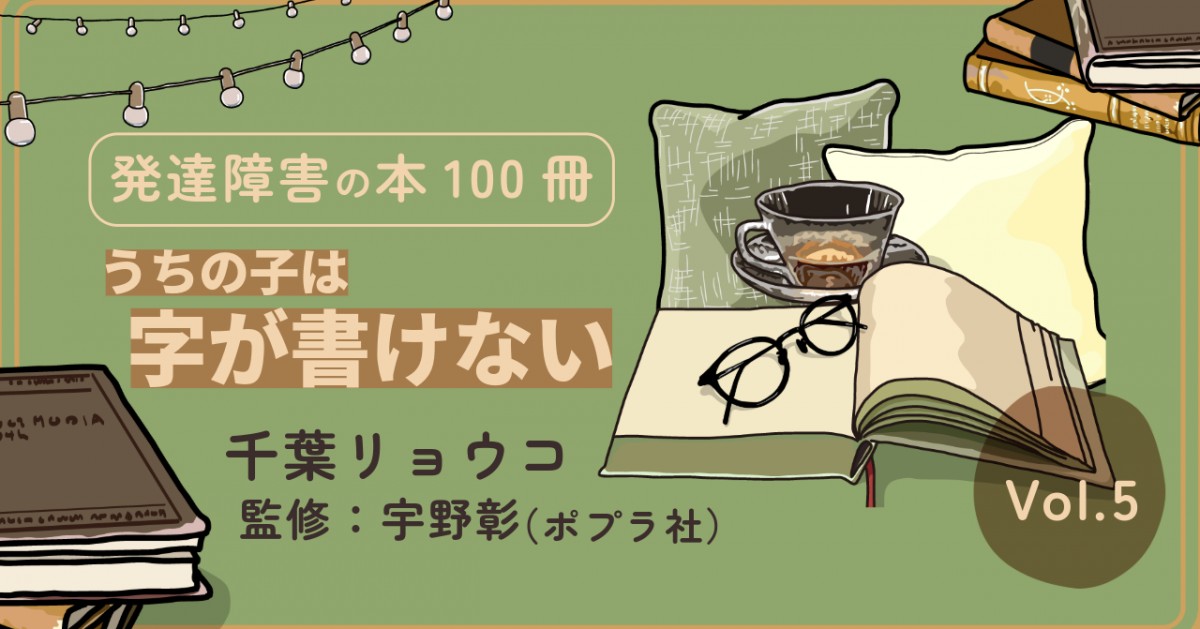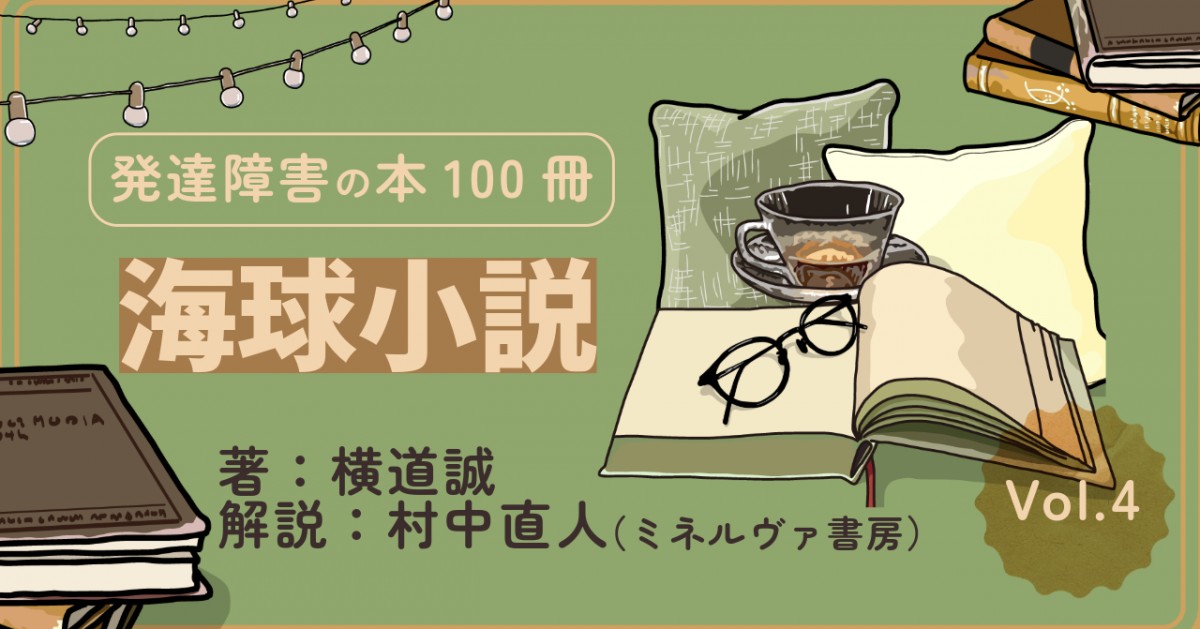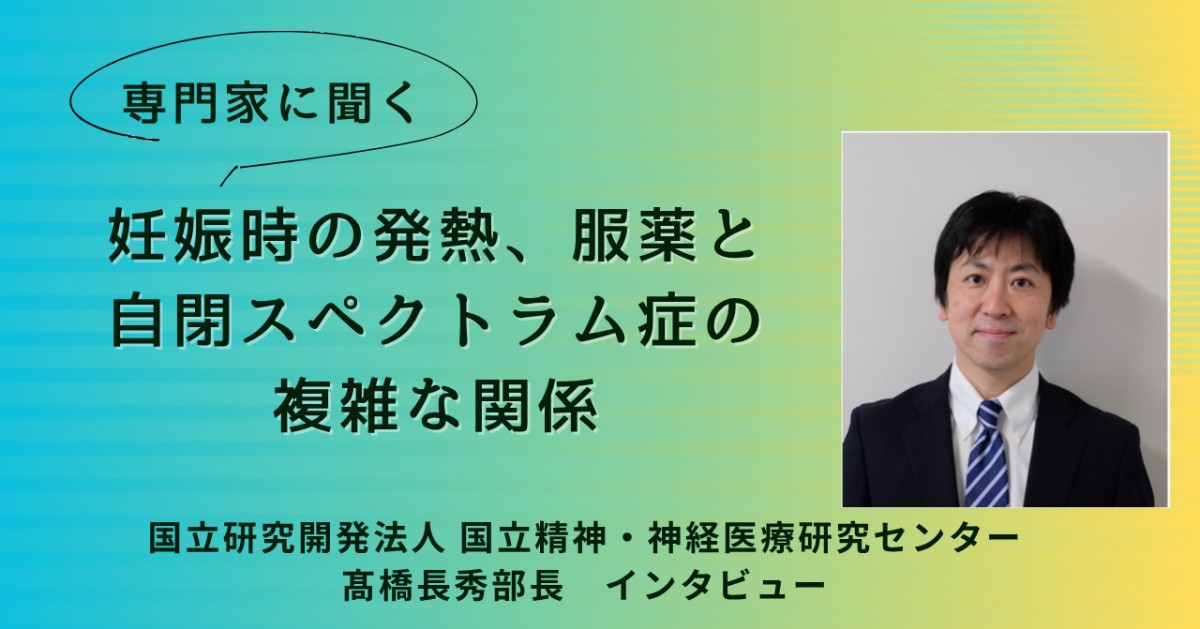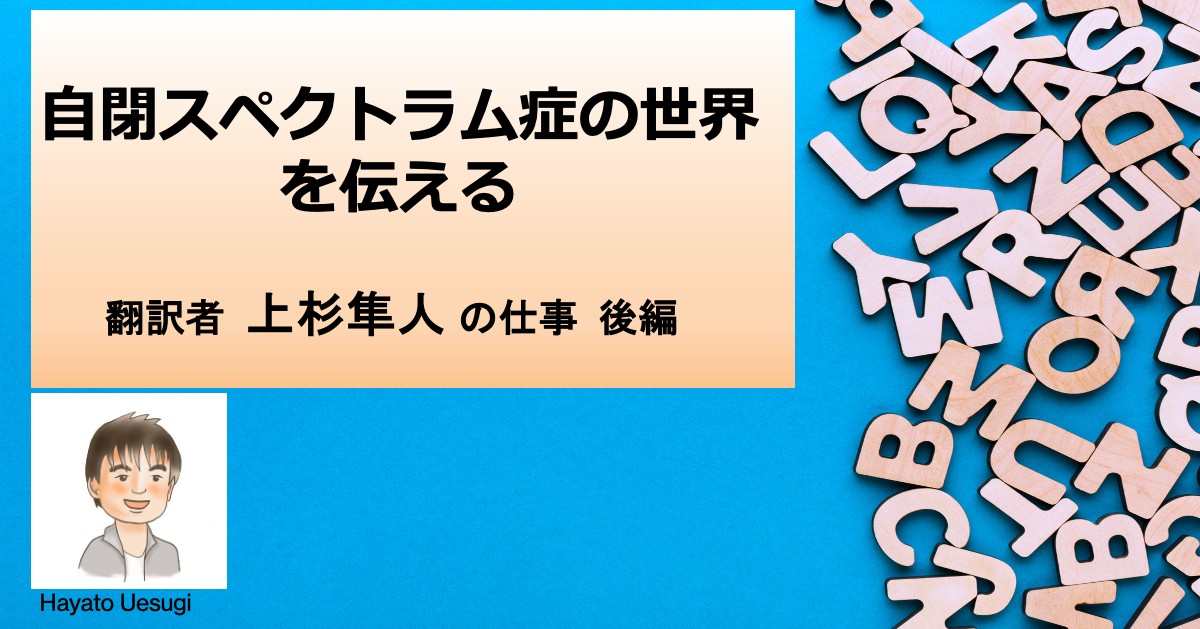詳しく知りたい「算数障害」 子どもの算数障害に気づくには? 第3回(全3回)
「アーカイブ」では、発達障害当事者や当事者家族、その周りの人々へ向けた情報を蓄積していきます。専門家から伺った深く細かい情報、現場のリアルな情報だけでなく、当事者や当事者家族の体験を記事にすることで、なかなかアクセスできない、子育てや学校、受験、仕事などにまつわる、個人の経験をお届けします。
専門家の記事を、誰でも無料で購読できます。有料会員としてご登録いただくと、個人の体験を含めた「アーカイブ」にあるすべての記事を読むことができます(750円からお好きな金額で登録でき、いつでも解約可能です)。発達障害について発信を続けていくために、ご登録での応援をお願いいたします。
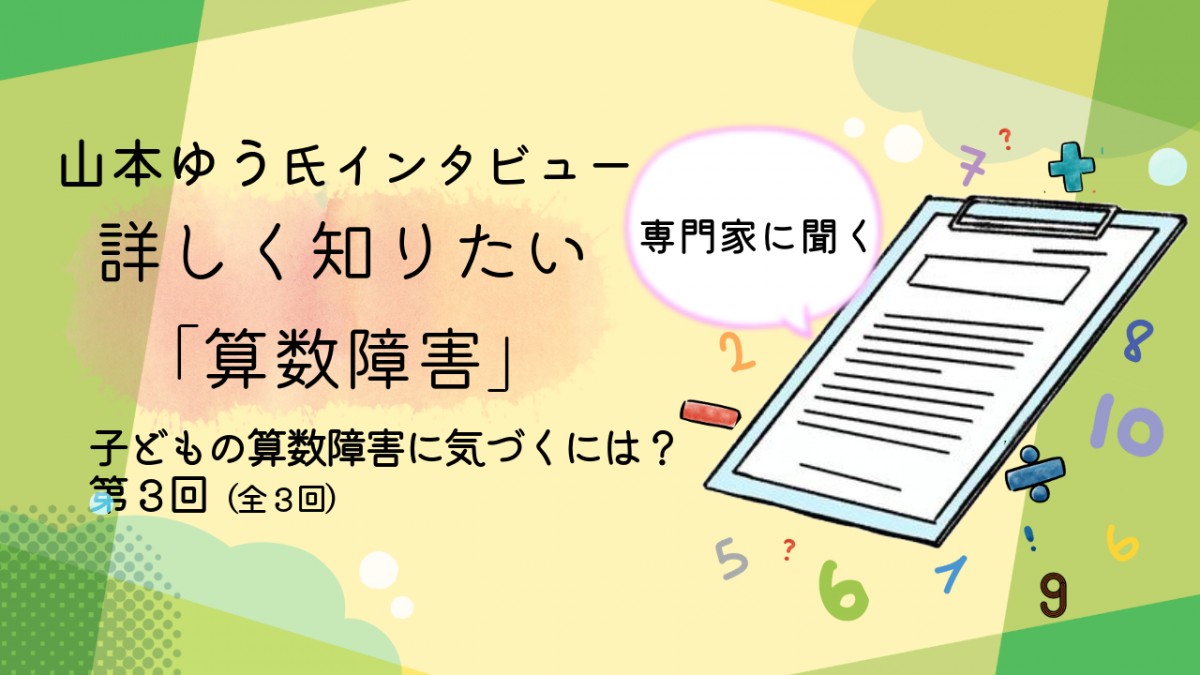
プロフィール
山本ゆう
松本大学教育学部専任講師。博士(障害科学)。特別支援教育士SV(スーパーバイザー)。公認心理師。小学校教員、医療機関や教育委員会での心理職を経て現職。算数障害のある子どもの臨床に携わりながらその解明および指導方法の研究を専門としている。
子どもの算数障害に気づくことができるのは、何歳くらい?
−− 子どもの算数障害に気づくことができるのは、何歳くらいからですか? 気づいた親は、子どものどのような様子を見て気づけたのでしょうか。
山本ゆう氏(以下、山本):「どれだけやってもできない」というのが、最初の気づきになると思います。毎日2時間、つきっきりで算数の勉強をしているのにできないとか、次の日になると完全に忘れているとか。2年生、3年生になっても、足し算に指を使っているなども、目安になります。そういう状況があれば、算数障害を検討する必要があります。または、知的な遅れについて考える必要があるかもしれません。
−− 算数障害がない子なら、例えば4年生まで指を使って計算するということはないということですね。
山本:知的な遅れがない場合にはないと思います。あるいは、学習環境が成立していなかったり、練習量が圧倒的に足りないということがなければですが。
−− 親が子どもの算数障害に気がついた具体的な単元などがあれば教えてください。
山本:計算のつまずきの中でも、特に九九で気づくということが多いです。
−− 九九は今、2年生からでしたっけ?
山本:そうです。時期として、早いですよね。まだ、足し算・引き算も十分にできていない子がたくさんいるのに……と思います。
足し算や引き算は、指を使ってする子がいます。答えが合っていれば、テストでは「◯」とされますから、足し算・引き算をすり抜けてしまう子がいます。そんな子が九九で引っかかってしまうことがよくあります。九九は覚えなければ答えが書けませんから、プリントやテストに「×」がつくようになり、それで親御さんが気づくんですね。
−− 九九は暗記をすればできてしまう可能性もあるのではないでしょうか。九九でつまずきがわかるのはなぜですか?
山本:「暗記をすればできる」といっても、覚えにくいものってありませんでしたか?